国語科「わたしはおねえさん」④発問の極意#11〈再構成発問と授業の展開例〉

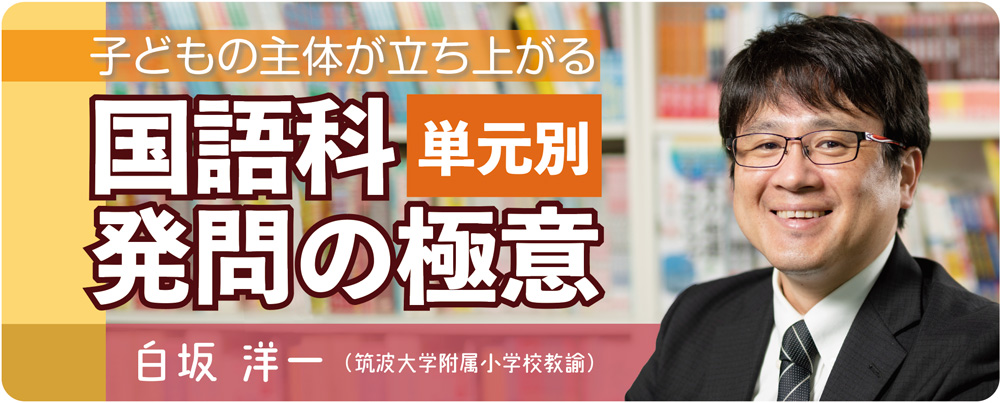
第3回では、物語「わたしはおねえさん」(光村図書2年下)をもとに、〈誘発発問〉と〈焦点化発問〉を取り上げました。第2回で紹介した〈きっかけ発問〉で書き出した短冊カードを出発点に誘発発問を展開していること、また、焦点化発問では、吹き出しや動作化を使って、中心人物の心情の変化をとらえる手立てを取り入れていることを紹介しました。
今回は、単元終末の発問について〈再構成発問〉を取り上げます。また、1時間を取り上げた授業の実際を紹介します。
執筆/筑波大学附属小学校教諭・白坂洋一
目次
中心人物すみれちゃんの変容を「歌づくり」で表現する
単元計画では、第三次で「感想文を書く」という言語活動を取り入れています。物語「わたしはおねえさん」の心に残った文をもとに自分の考えや体験を交えながら感想文を書くこと、そして、すみれちゃんシリーズへと読み広げ、心に残った文をもとに感想文を書くことを設定しています。
第二次において、物語「わたしはおねえさん」を読む上での再構成発問が
「すみれちゃんは、おべんきょうを終えた後、どんな新しい歌をつくったのでしょう?」
です。
第1回で、教材の特性の1つに〈「わたしはおねえさん」の歌〉を挙げています。中心人物のすみれちゃんは、歌をつくるのが好きな女の子です。物語中にも2つの歌が登場しています。例えば、コスモスの歌のように、自然と歌が出てくるというその様子からは、すみれちゃんは自分の思いや考えをすぐさま歌として表現できることが分かります。
しかし、本文中には、かりんちゃんとの出来事を表した歌は描かれていません。本文に描かれていない最後の場面(宿題が終わった後)を取り上げ、題名にある「わたしはおねえさん」をテーマにした歌を作成することによって、妹かりんちゃんとの出来事を通したすみれちゃんの変容を歌で表現することができます。描かれていないからこそ、2年生である読者の子どもたちはすみれちゃんに同化しながら、その変容を歌として表現していくのです。
歌づくりをする際には、題名と関わりをもたせていくとよいでしょう。題名には中心人物すみれちゃんが変容する出来事・エピソードが表現されています。妹のかりんちゃんとの出来事を通して、すみれちゃんは葛藤し、特に、「すみれちゃんは、もういちど、ノートを見ました。じっと。ずっと。」の1文には中心人物すみれちゃんの大きな変容が描かれています。この1文から題名「わたしはおねえさん」にも関わる、すみれちゃんのお姉さんとしてのあり方を考えることができます。
物語の冒頭には歌として「おねえさん」像が描かれていますが、妹かりんちゃんとの出来事によるすみれちゃんの変容を表すのに、冒頭の歌をアレンジしていくのも1つの方法です。

