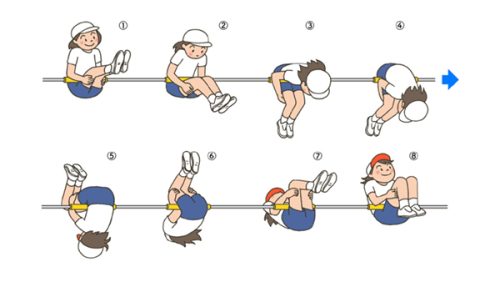小1算数「20より大きいかず」指導アイデア(1/16時)《10 のまとまりに着目して数える》
執筆/福岡県公立小学校教諭・阿部万優子
編集委員/国立教育政策研究所 教育課程調査官・笠井健一、福岡教育大学教授・清水紀宏
目次
本時のねらいと評価規準
(本時 1/ 16)
本時のねらい
10 のまとまりに着目し、具体物を用いた数学的活動を通して、20 より大きな数の数え方について理解する。
評価規準
10のまとまりとばらで数を捉え、その数を読むことができる。 ( 知識・技能)

問題場面
それぞれが とった ぼうは、なんぼんでしょう。
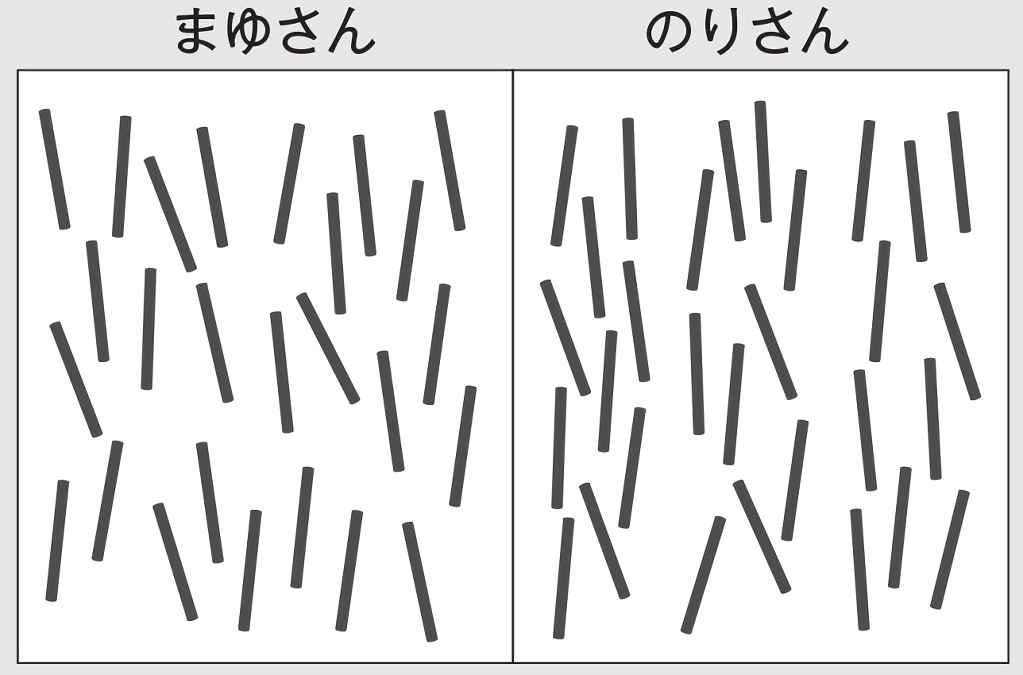
この2人が取った棒は、何本あるでしょう?
20 本よりも、たくさんあります。
今のままでは、わかりません。
10のまとまりを、つくったらいいと思います。
棒の数がすぐにわかるように、並べてみましょう(まゆさんとのりさんの棒と、同じ数の棒を配る)。
この問題に入る前に、子供たちを2人組にさせて、両手で棒をつかませます。どれくらいの棒を取ったのかを考えさせておくとよいでしょう。そうすることで、問題場面においても、ペアで数える活動を取り入れることがスムースだと考えられます。数える活動の際には、取った棒をすぐに数えることができるように、声かけを行います。
本時の学習のねらい
ぼうの かずが、すぐに わかるように ならべよう。
見通し
・5本ずつ数える。
・2本ずつ数える。
・10 本ずつ数える。
自力解決の様子
A:つまずいている子
数えた10 のまとまりを合わせてしまうなど、10 のまとまりの個数に着目できていない。
B:素朴に解いている子
10 のまとまりを正しくつくるが、10 のまとまりとばらについて、数え棒の配置が整理されていない。
C:ねらい通りに解いている子
10 のまとまりを正しくつくり、10 のまとまりを左側に、ばらを右側に置くなど、それぞれの個数が一目でわかるように、数え棒を配置している。
学び合いの計画
子供たちは、「20 までのかず」の学習で、20 までの数を10 のまとまりに着目して数えたり、数字で表したりしてきています。本時の学習でも、すぐに数がわかるためには、10 ずつまとめて数えればよいことを想起させることが大切です。
「20 までのかず」の学習から時間が経っているので、10 ずつまとめて数えることを忘れている子供もいるかもしれません。
そこで、全体交流の前にペア交流を仕組みます。10 のまとまりをつくっているペアと、そうでないペアを組ませることができれば、数え方にズレが生じ、友達同士で数え方を確認したり、友達の数え方を説明したりすることにつながります。
ノート例
イラスト/佐藤雅枝
『小一教育技術』2019年1月号より