「食育」を考える ~担任としてできること~

2005年に「食育基本法」が制定され、施行されました。これを機に、一気に給食が変わってきました。以来十数年を経て「食育」という概念がかなり浸透してきています。
栄養教諭さんや学校栄養士さんに
「食育」とは何でしょうか?
「食育」をどうとらえていますか?
と伺いました。この食育基本法の精神をもとに、こんな答えをしてくれました。
●食べることを通して心身ともに豊かに成長させること
●「知識」と「選択」で健全な食生活の実践力を鍛えること
●楽しく食べること
●考えて食べること
●食に興味をもたせること
いずれもシンプルでわかりやすいです。栄養教諭・学校栄養士さんが仕事をしていく上で、それぞれのフレーズがとても大切な矜持となっているようです。
基本的には、生きることは食べることだということを知ることです。だったら、どのようなものをどのようにして食べるかを考えることが大切であり、できれば誰とどんな風に食べるか、そしてどうすれば心が満たされる食べ方になるか、ということを考え、身につけることなのでしょう。まあ、学校でよく使うワード『知・徳・体のバランスや調和』ということになるでしょうか。
最近、コロナ禍でしっかり前を向いて、クラスメイトと食べているのに、「黙食」が推奨され、ただ食事をするというだけに終わっている傾向がないか危惧しています。しょうがないことですが、こういう時代だからこそ、もう一度「食育」を考え、担任としてできることはないか考えたいです。
【連載】マスターヨーダの喫茶室~楽しい教職サポートルーム~
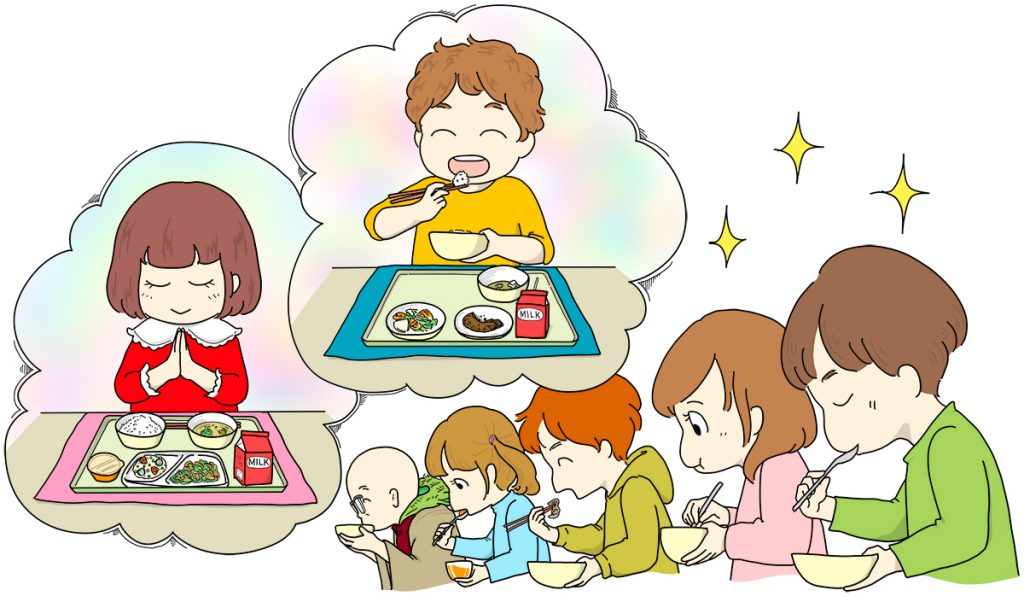
目次
1 「こ食」の問題
さて、「食育」を推進していくにあたり、最近「こ食」が課題になっていることを忘れてはなりません。
個食…複数で食卓を囲んでいても、食べている物がそれぞれ違う
子食…子どもだけで食べる
小食…ダイエットのために必要以上に食事量を制限すること
固食…同じ物ばかりを食べる
濃食…濃い味付けの物ばかり食べる
粉食…パン、麺類など粉から作られた物ばかり食べる
孤食…一人で食べる
*資料出典『保育所における食事の提供ガイドライン』(厚生労働省平成24年3月)
実はこの課題の解消になるのが、まさに「給食」です。日頃慣れ親しんでいるクラスメイトと担任のせんせいと同じ物を、調整された味付けで栄養バランスよく食べる。いいですねえ!
家庭的に課題のある児童には、本人にいくら「早寝早起き朝ごはん」とスローガンを連呼しても解決にはならないです。そして、家庭それぞれの置かれている状況が違います。チェックリストなどで、このことを促すのは一定の効果はあっても、なかなか効果がないですし、余計なお世話と一蹴されることも多いです。ほんとうに朝ご飯を食べることのできない児童もいます。その辺においてあった菓子パンやお菓子などを食べて登校しなければならない児童も多いです。そういった状況から、まさにセーフティネットとしての「給食」の存在があります。「給食」で、健康を保つ児童がいることも忘れてはならないです。究極的なことを言えば、命を維持するために何をどう食べるかということです。給食をとおして常に「食」を考える児童に育てたいです。
![]()
●「こ食」の実態を調べ把握すること(対話や簡単なアンケート、家庭訪問などでの話題など)
●「こ食」を解決できる自分なりの方法を考えさせること
2 食べられない児童たち
現代日本では、貧困が深刻化していることも忘れてはなりません。子どもの貧困率は、7人に1人とか6人に1人とも言われています。貧困には、「絶対的貧困」と「相対的貧困」がありますが、わが国でいう貧困は「相対的貧困」です。相対的貧困は、生活水準や文化水準を大幅に下回っている状態をさします。経済大国の中ではわが国はワースト第4位とも言われています。
さらに、ひとり親家庭の貧困率は半数を超えているというデータもあります。
一見、どの教室ものどかに見え、平和な給食シーンが展開されていますが、実はこういった家庭状況が背景にある児童がたくさん存在しているのです。
わたしが経験した、たくさんの事例の中で、3つほどお話しします。
お母さんが家を出ていき、お兄さんは行方不明。ほとんど収入のない自営の父と暮らしているA子がいました。父は近くの民生委員をしている商店主から、醤油を借りたり、味噌を借りたりしながら食いつないでいました。要するに、ご近所の善意で食事をもらっていたのです。
このA子とは、常に家庭状況を話していましたが、状況は本当に緊迫していました。
わたしはお母さんの勤務先を訪ねて、これからの見通しや、支援を依頼できる親族はいないかを聞いたりしました。なかなか状況が変わりません。
朝食は食べてこない、というより食べるものがないということで、わたしが持っていたスポーツ後の栄養補助食品や缶ジュースなどを提供していました。そして、A子はまさに給食でいのちをつないでいました。もちろん給食費は払えなかったです。後日社会保障的な給食費の支援を受けました。どうにか卒業までこぎつけ、PTA役員さんから中古の制服や学用品を提供していただき、さらに公的な支援をもらいながら預かってくれる家庭も決まり、中学校に進学していきました。
また、こんな児童もいました。お父さんが難病で亡くなり、残されたお母さんは看病疲れや生活の不安定さから精神疾患となり、服薬の副作用で朝はなかなか起きることができませんでした。
それで入学したばかりのB子は、準備も整わず、朝食もとれず、学校を休みがちでした。わたしは9時、10時に迎えに行き、学校への道すがら「朝ご飯は何を食べたの?」と聞くと「何も食べていない」という答えが多かったです。たまに、「昨日お母さんが買っておいてくれた、だんごをひと串だけ食べた。」などと言っていました。しかしながら、学年が進むにしたがってどうにか食べることは自立できていったようです。
そして、C男。シングルマザーに育てられており、自由奔放な母は育児放棄しがちでした。学校からの手紙類は一切読まない。手続などもしない。児童を休ませるとしても、一切連絡もしてこないという状況で、何度も家庭訪問をしました。でも、居留守状態でした。児童に食事のことを聞いても、その辺にあった菓子パンを食べたとかお菓子を食べたということで、きちんとした食事をとっていないようでした。偏食のため、どんどん太っていきましたが、どうにか量は満たされていたようです。今では給食を楽しみに学校に来ているようです。
こういった「こ食」の中で、しかも十分食べられないで生きている児童は、珍しい例ではなく、日本じゅうの教室にたくさんいます。担任としては、どれだけ給食で一日の摂取すべきカロリー量を補うことができるかを考え、児童の栄養状態を気にしてあげる必要があります。
![]()
●児童の家庭状況を正確に把握し打つ手を考えること(管理職との連携)
●児童の栄養状態に気をつけ体重の増減などを把握すること(養護教諭との連携)
●児童との対話を多くし困っていることや悩みなどを把握すること(教育相談担当との連携)
●食事の取り方や量などに気を配ること(栄養教諭との連携)

