「書くこと」ができていれば「読むこと」もできている 【全国優秀教師にインタビュー! 中学校編 中1〜中3を見通す! 「高校につながる英・数・国」の授業づくり #8】
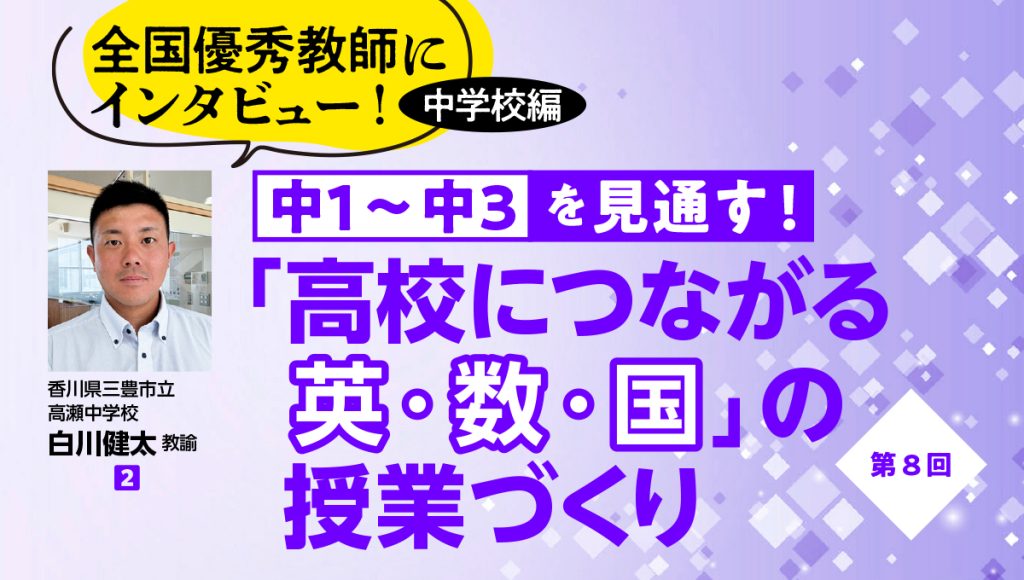
前回は、2023年度の全日本中学校国語教育研究協議会の香川県大会で授業公開を行い、同県の国語教育研究会もその授業力を高く評価する、三豊市立高瀬中学校の白川健太教諭に、「走れメロス」の単元構成について紹介をしてもらいました。今回は、その単元構成の意図について聞いていきます。

目次
「文章量の多い作品を読むのが嫌い」だから国語が嫌い
白川教諭は、前回のような単元構成を工夫する意図について、次のように説明します。
「前回、単元を紹介した『走れメロス』は、国語の教科書の中に載っている文学的な文章の中では、ドラマチックで比較的読みやすい文学作品だと思います。その理想を描いた演劇のようでおもしろい文章ですら、最初の通読の時間から諦めてしまう生徒たちがいるのです。
実際に私が担当する生徒たちにアンケートを取ったところ、『国語の授業が嫌い』と答えた生徒の約8割が『文章量の多い作品を読むのが嫌いだから』と答えています。そこには高度情報化が進み、情報媒体が多様化しているこの社会において、文章を読み味わう時間をもつことが困難になってきているという現実があるでしょう。実際に『1ページ以上、文章が読めない』という子供も少なくないのです。そういう子供たちが、いかに文章を読みたくなるようにするか、という仕掛けを私はいつも考えています。
先に紹介をした実践は、自分の中で出たその答えの1つで、原作を読み切ることがむずかしい生徒もいることを考え、まずまんがから入ったのです。ただ、原作を読ませずにまんがから入ることに抵抗感のある先生は少なくないだろうし、国語の教員ならなおさらだろうと思います。実際に原作至上主義のような考え方はあり、この提案授業に対しても『まず原作を読まずして、どうして改変作品を読むのか』という意見もあったのです。
しかし、今の生徒たちはいきなり原作の文学作品から入っていく子は非常に少なく、まず興味をもたせることからスタートしないと、授業についてこられる生徒のほうが少数派になってしまうでしょう。もちろん、興味・関心を惹くことばかりを重視しすぎてもだめですが、言葉に向かわせる前段階のハードルを下げることを考えないと、なかなか全員が参加できる授業にはならないと感じています。
ですから、私はよくまんがやアニメのようなサブカルチャーを取り入れたり、歌詞を教材として使った授業をしたりもしています(次回、紹介)。そこで考えているのは今の子供たちのニーズに合致するところと、教えるべき内容や育むべき力の折衷案というところなのです」


