離職に悩む同僚教師をどうサポートすべきか?
『5年3組学級経営物語』1月の回でテーマとして取り上げた”教員の離職”。教育行政の間でも若手教師の離職対策が議論されていますが、「もう教員を続けられない」という悲痛な声は絶えず発せられています。『学級経営物語』作者の大和大学准教授・濱川先生が、自身の長年の教職経験の中で対応してきた具体的な事例をもとに、同僚の離職問題に直面したときの接し方をアドバイスします。
執筆/大和大学教育学部准教授・濱川昌人
濱川昌人(はまかわ・まさと)元大阪市公立小学校校長、2020年より大和大学教育学部准教授。「特別活動」「総合的な学習」「生徒指導」等を担当。2016年、2017年に『教育技術』学級経営ページを執筆するかたわら、教育を小説的手法で解説する「4年3組学級経営物語」を連載。そのシリーズをウェブに引き継ぎ、連載執筆している。
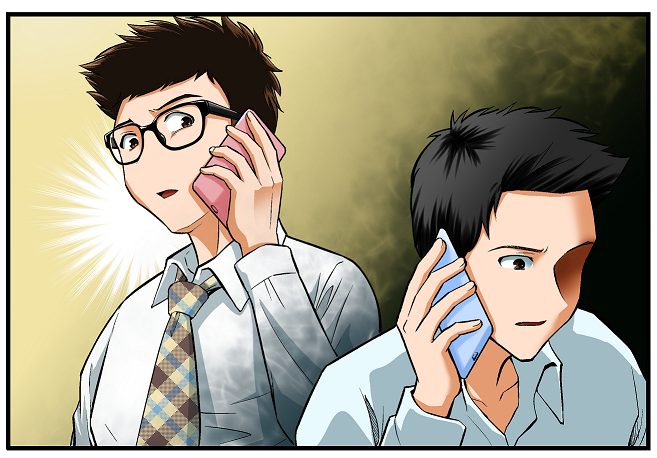
離職をテーマにストーリーが展開する第19回はこちら ⇒ 友人の教員離職と、キャリアデザインのはざまで…【5年3組学級経営物語19】
目次
誰にでもある「教師をやめたい」と思う経験
学級経営上の課題、保護者からの苦情、職場の人間関係の摩擦…。また、家庭事情等で職務が思い通り遂行し難くなる…。様々な理由から自信を無くし、心が折れそうになる。そして、「学校に行きたくない」「もう辞めたい」という思いが心を過る。そんな辛い経験は、誰でも一度くらいはあるでしょう。
そして、絶対忘れられないのは、そんな大変な時に温かく適切にサポートしてもらった思い出です。私も新任の頃、先輩等のアドバイスで心が落ち着き、解決の糸口を見出せたことがあります。難題を乗り越え、「君も後輩の相談を聞いてやるんだぞ!」と温かく微笑んだ先輩の笑顔もはっきり覚えています。その様な体験が、以降の同僚との関わり方に大きな影響を及ぼしました。
「ストーブ談義」の効用
昔の職員室には、「ストーブ談義」と称される教職員同士で助言しあい、励ましあう場がありました。
単なる雑談や、お説教等で時間が潰れたこともあり、鬱陶しいと思ったこともあります。けれど、そこには困難を乗り越える知恵や心が落ち着く温もりがあり、困った時はサポートしてもらえる安心感がありました。新任としては「よく分からない教職生活」に馴染むための良い機会でした。何よりも、困ったことを気軽に相談できる場、いろいろな先生と繋がる場でした。
その効用は意見が分かれます。けれど管理職になった時、まずストーブ談義のよさを思い出しました。そして、「和やかで相談しやすく、自分の居場所がある職員室をつくろう」と私は呼びかけました。
とくに新任や転任者、対人関係が不得手な教職員には、とても大事です。誰にも相談できずに悩む同僚がいても無関心だったり、プライバシーを過度に尊重したり…。そんな職員室では離職を考える同僚がいても、適切にサポートできないでしょう。

