主体的に行動する子どもの姿を見る力が、大人についていますか? 【木村泰子「校長の責任はたったひとつ」 #19】

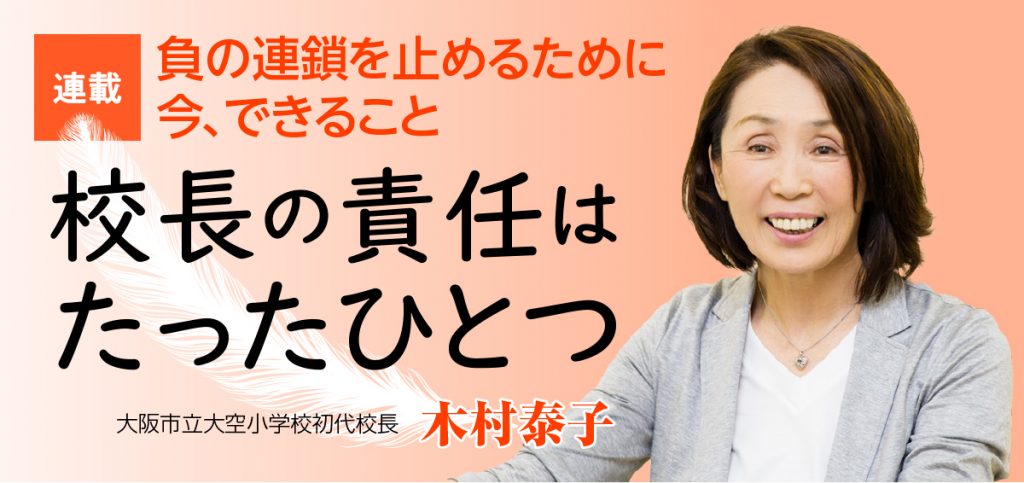
不登校やいじめなどが増え続ける今の学校を、変えることができるのは校長先生です。校長の「たったひとつの責任」とは何かを、大阪市立大空小学校で初代校長を務めた木村泰子先生が問いかけます。第19回は、<主体的に行動する子どもの姿を見る力が、大人についていますか?>です。
ある中学校で遭遇した「無言」の空気
子どものどんな行動を「主体的」と言うのかについて、全教職員で対話し、共通理解をはかっているでしょうか。
「無理しないで行ける学校」をつくることは、全ての子どもが主体的に行動できることにつながっています。
先日、ある中学校で授業をさせていただきました。500人近くいる全校生徒が教員に引率されて体育館に入ってきました。誰一人声を出していません。全員が「無言」で指示された場所に座り、授業者である私のほうを向いています。私は、正直戸惑いました。今から全校生徒に話をする者としてはとてもやりやすい。全員が「無言」で私のほうを向いて聞こうとしているわけですから。
そこで、まず一つ目の問いを出しました。
「自分の言葉」で語っていますか?
この問いに関しても、全員が「無言」です。「この授業に正解はありません。自分の言葉で語ることがテーマですよ」と伝えても誰も発言しようとしません。おそらく正解を求める発問に対しては、生徒たちは答える力をもっているでしょう。ところが、正解がないと言われる問いには何を言っていいか分からないと思ったようです。やる気がないとか授業に正対していないとかの空気ではなく、私が生徒に出会ったときに戸惑ったように、生徒たちもこの授業に戸惑ったのだと思います。「手を挙げないで、発言しようと思ったら立って、周りを見て自分だけだったら発言してください。周りに発言しようと思う人がいたら、互いにコミュニケーションをとって譲り合ってくださいね。私は指名しません」と初めに伝えたので、この授業のグランドルールにも躊躇していました。
しばらく体育館に「無言」の空気が張り詰めていたのですが、一人の生徒が立って自分の言葉で語りました。すると、その学年の生徒たちがクスクスと笑いました。気になりながらも次の問いを出すと、誰も動かない「無言」です。生徒同士も話さない中で、先ほどの生徒が立って自分の言葉で語りました。その瞬間、周りの生徒たちは、今度は声を出して体を揺らしながら笑いました。「無言」のルールが解き放たれたのですね。さすがに、私は授業者としての責任を感じ、生徒たちに問いかけました。
今の笑いは人を楽しく幸せにする笑いですか? それとも誰かを傷つける笑いですか?
その瞬間、また体育館の中に張り詰めた緊張感が戻り、全員が「無言」になったのです。この集団の中で、自分から自分らしく自分の言葉を語ると、みんなに笑いものにされる。それなら、何も言わない、動かないのが一番なのかもしれません。生徒たちにとってこの「無言」のルールは、自分をさらさず目立たず自分を出さないことを守るためのものかもしれないと思いました。私自身がこの学校の生徒だったらと想像したら、やっぱり「無言」のルールをひたすら守ってしまうかもしれないとも思わせられました。
読者のみなさんがこの学校の校長であれば、目の前の生徒たちの事実をどのように見られますか?
私はたった1回、目の前の生徒に出会い、授業をさせていただいた大人です。生徒たちが何を感じ、どんなことを学んでいるかは分かりません。ただ、私自身の学びにはかけがえのないものがありました。教員の指示を的確に聞いて指示通り行動する生徒の姿は見事に育っている。500人もの中学生が誰一人声を出さずに教員の指示通り行動するのですから。言い換えれば声を出したら指導される。この空気になじめない生徒はこの集団には入れないでしょう。この学校に来ていない生徒たちは30人を超えるということでした。
授業を終えて体育館を出ると、廊下には「無言」と書かれたポスターが貼られていました。生徒たちが校内で常に目にしている掲示物が「無言」なんですね。
生徒の事実から何を学んだか?
授業の後、校長・教頭と生徒の事実から互いに何を学んだかを本音で対話しました。決められたことを自ら進んで行う「自主性」が育てられている生徒に、やるべきことは何かを自分で考えて行動する「主体性」をいかに獲得させるかの課題はとても困難な気がしますが、やるしかない。当然、しばらくリハビリ期間は必要ですが、生徒の方向転換は非常にたやすい。
困難なのは教員たちのこれまでの「指導」を問い直すチャレンジができるかどうかです。この日から、校長と教頭はタッグを組んでチャレンジを始められました。
もし、講師が講話をすることがこの授業の目的で、生徒に話を聞かせたいという目的をもっておられたら、「素晴らしい生徒が育っている」と高い評価をされたことだと思います。学校の授業の目的が「自主性」を育てることなのか「主体性」を育てることなのかを全教職員で合意していないと、子どもが育つ事実は生まれません。そのためにも500人の生徒が主体的に学びに向かう姿はどんな姿なのかを、常に職員室の雑談で対話を重ねることが不可欠のように思います。
私自身、学ばせていただいている者として、評価したり批判したりすることはたやすくできるでしょう。それでは何一つ未来の学校づくりにはつながりません。自分だったらこの学校の環境の中で何をするか、何から行動し始めるかと「当事者性」をもって初めて自分の学びに返せるのだと再認識させていただきました。
学校は失敗するところです。失敗をやり直すことで成功体験につながり、社会で「生きて働く力」になるのです。「みんなの学校」をつくる過程で何度失敗してやり直しをしたか分かりません。校長から失敗し、やり直しの行動を見せることが今求められている気がします。

1 授業の目的が「自主性」を育てることなのか「主体性」を育てることなのかを、全教職員が共通理解する必要がある。
2 生徒が主体的に学びに向かう姿とはどんな姿なのか、職員室の雑談で対話を重ねていくことが重要。
3 校長から失敗し、やり直しの行動を見せよう!

木村泰子(きむら・やすこ)
大阪市立大空小学校初代校長。
大阪府生まれ。「すべての子どもの学習権を保障する」学校づくりに情熱を注ぎ、支援を要すると言われる子どもたちも同じ場でともに学び、育ち合う教育を具現化した。45年間の教職生活を経て2015年に退職。現在は全国各地で講演活動を行う。『「みんなの学校」が教えてくれたこと』(小学館)など著書多数。

