学校を支えるみんなの手で、子どもたちを変え、地域を変え、社会を変えよう~映画「みんなの学校」に学ぶ、学校と社会のあり方~
- 連載
- 大切なあなたへ花束を


学校教育は、だれのためにあるのですか? と聞かれたら、何と答えますか? もちろんそこに通っている子どものためです。でも、答えは果たして、それだけなのでしょうか?
「学校はあるものではなく、つくるもの」これは木村泰子さんの言葉です。
学校に通うすべての子どもが一日の学びを終え、納得して「さようなら」と帰り、また翌日安心して「おはよう」と登校してくる学校をつくるのは、教員だけでは無理です。地域の大人たち、そして保護者の皆さんも一緒になって、「学校観」を変えるときなのです。そんな学びの1つをご紹介したいと思います。
【連載】大切なあなたへ花束を #19
執筆/みんなの学校マイスター・宮岡愛子
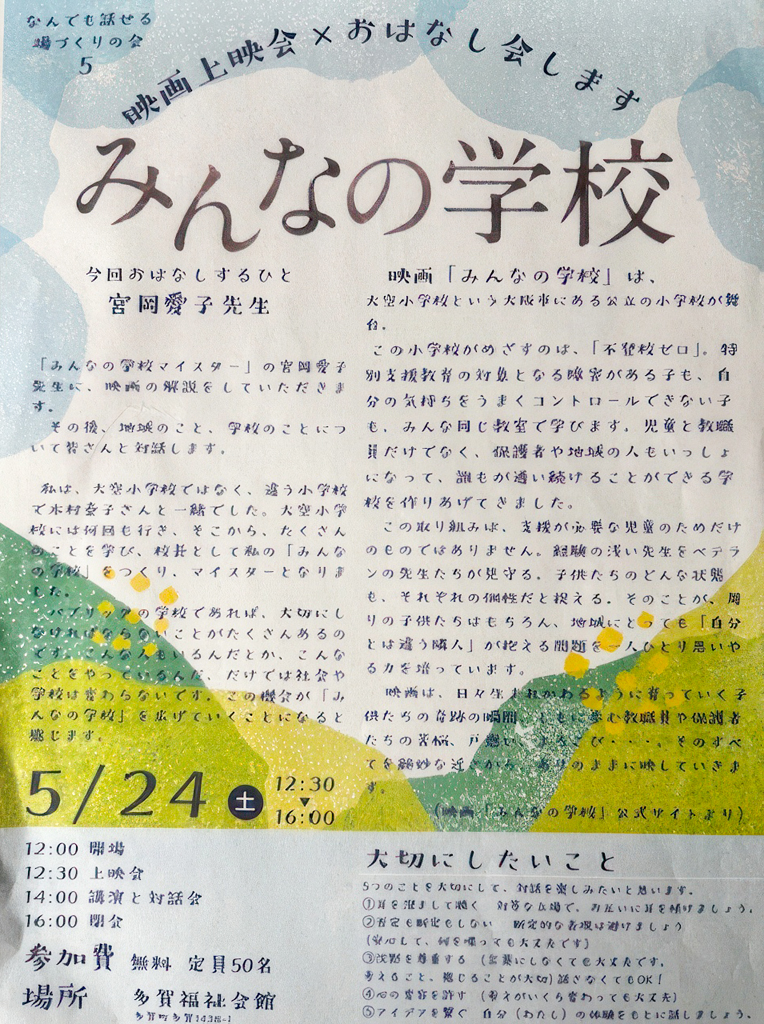
なんでも話せる場作りの会で
(令和7年)5月24日、わたしは滋賀県多賀町を訪れ、みんなの学校マイスターとして、皆さんとお話をする機会に恵まれました。
わたしをこの場につないでくださったのは、「なんでも話せる場づくりの会」事務局の音田直記さんです。
なんとも素敵なネーミングだと思いませんか? この「なんでも話せる場づくりの会」は、地域の皆さんが対話し、学び合っていける場づくりを目指して活動されているとのことです。
学校と地域の関わり合いは、この社会にとって今最も大切なテーマの一つであることは間違いありません。「みんなの学校」の映画を上映し、その後の対話を通して、自分たちの地域を考えていきたいという、音田さんの熱い思いが感じられる会でした。
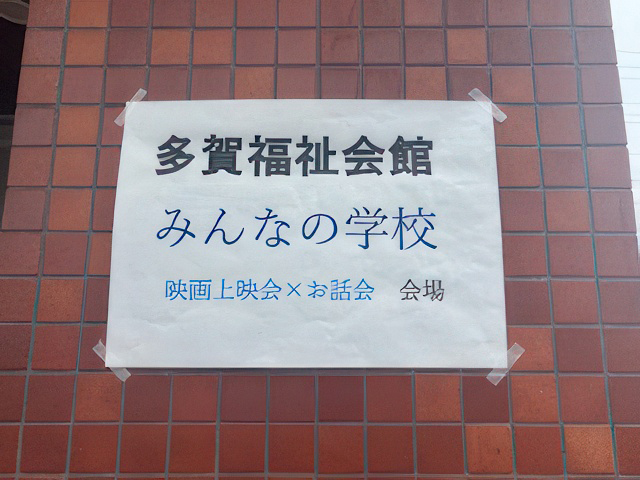
本会には、地域からさまざまな方が参加されました。滋賀県内の小学校の先生たち、三重県や滋賀県甲賀市で地域活動されている方々、高島市の議員さん、彦根市のフリースクールの運営者さん、親子活動の関係者、地域学校協働本部の方、退職教員、不登校の子どもの保護者さん、そして、地元多賀町の小学校の保護者の方や、地域活動をされている方などです。
まず、映画「みんなの学校」を観ることから始まりました。この映画は2015年に公開されているので、今年で公開後10年となります。私も10回ぐらい観ているでしょうか。
今回も、何度も観た映画だと思えないくらい、改めて強い感動を覚えましたが、これまでとは異なる感情が生まれたことが、自分として少し驚きでした。
何が違っていたのでしょう? それは、わたしが変わったからだ、と思い至りました。
今までは、教員として、校長として、「こんな学校をつくっていこう!」と観ている自分がいました。だから、子どもが自分から語る場面や、卒業式で泰子さんが子どもに話す場面が心に残っていたのです。でも、今回は、私が社会教育士になり、地域の住民になったことで、観るポイントが全く変わっていたのを感じました。
自分でも不思議だったのですが、今回、心に残ったのが、親の会でそれぞれの保護者が、円になって順番に話をしている場面でした。
ある一人の保護者が
「小学校を卒業したら、中学校では特別支援学校に行く」
と話します。大空小のような中学校はなかったからです。保護者として、いろいろな葛藤があったのだと、気持ちが痛いほど分かりました。
それを受けて、堀智晴大阪市立大学教授(当時)が、とても残念そうに話していたのが忘れられません。
大空小学校で子どもたちが共に学んできたことは大きい。これからの30年、このように共に学ぶ学校教育を続けていたら地域が変わってくる…といった言葉でした。
そして、この場面から、わたしの知る、とある地域のことも思い出していました。
その地域で高齢者施設や作業所をつくろうという動きがあったとき、地域住民が大反対をしたことを聞いたのです。結局、高齢者施設も作業所もどちらもつくられることはありませんでした。
その地域に住む発達障害と言われる子どもたちは、(もちろん保護者の考えもあるでしょうが)地元の学校に通うことはなく、特別支援学校を選んで通っていたのでした。
社会は一朝一夕には変わりません。変革の炎はゆっくりとあたりに広がっていきます。だからこそ、今は小さくとも、それに関わる人々は、その炎を絶やしてはならないのだ…。
もし、子どもたちがいつもいっしょが当たり前で共に学んでいたら、その子どもたちが大人になる30年後には、きっと地域のあり方が変わっているはずです。
もう一つ心に残ったのは、地域の人が子どもから暴力を受けるという場面でした。
子どものことを気遣う地域の方に対して、その気遣いをうまく受け止められなかった子どもが暴力を振るってしまったのです。
これは地域によっては大問題に発展することです。
場合によっては警察沙汰になるでしょう。学校も教職員総動員で謝罪や対応に走らねばならなかったりします。
しかし、大空小のある地域の皆さんは、「やったことは悪いが、その子の気持ちはこうだったのだ」と、非常に大人らしい受け止めをされていたのです。
同じ地域に住む一人として、このような対応ができるかと、改めて考えさせられました。
立場の違いは当然あります。しかし、地域に住み、学校を取り囲む大人たち一人ひとりが、それぞれ誠実に助け合いの気持ちをもって行動すること。その人の輪こそ大切なのだと思いました。
さて、映画のあとは、私が話します。
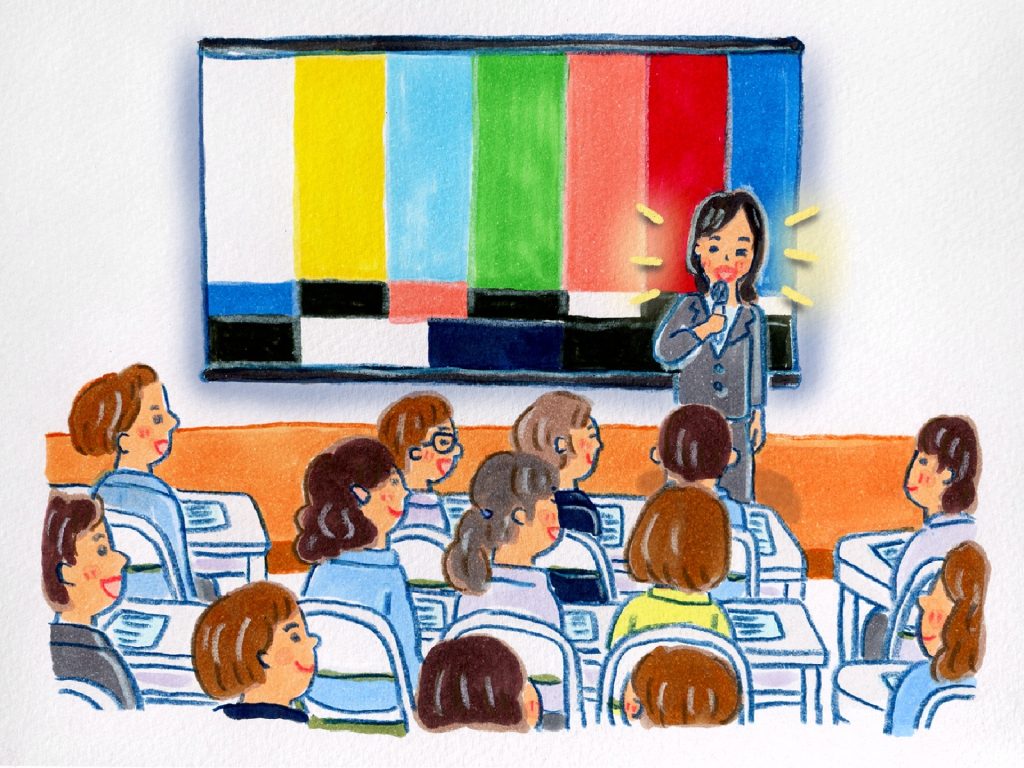
子どもの成長を支えるのは…
やはり皆さんが気になっているのは、映画に出ている子どもたちがどうなっているか? ということです。映画の公開から10年経っているのですから、10年後の子どもたちについて伝えることから始めました。わたしは、泰子さんから聞いた一人一人の子どもたちの話をします。どの子も自分らしく自分の選んだ道を歩いていました。
ある子は中学3年生になったとき、「学校の先生になりたいな」とつぶやいたそうです。
「おれみたいな、すぐ人をどついてしまうし、おれなんかあかんねんと思うところやけど、地域の人は○○はいい子やで、○○は自分の行動を変えるだけでいいねんで ○○はいい子や。この言葉でおれはまだいけると思えた。だからおれは子どもらにかえさなあかん」
というのがその理由でした。
またある子どもは、泰子さんに
「今のおれがあるのは地域の人のおかげや。地域の人がいなかったら生きていないかもしれない。俺には夢が二つある。はたらいてお金をためて大空に住んで地域の人に返すこと、おれみたいなやつのために学校の先生になること。小学校の先生になって大空をつくりたい」
と伝えたそうです。
すごくないですか?
小学生の頃に子どもが地域の人にかけられた温かい言葉や、かけてもらった思いやりは子どもの心に残り、必ずや大人になってから返そうとすることがよくわかります。
つまり、子どもがいかに「パブリックな環境」で6年間を過ごしたか? ということこそ大切なのです。
それは、「みんなとちがっていいよ 自分は自分のままでいいんだよ 自分らしくていいんだよ」ということを、幼い心が体験から身にしみて体験できるということです。
それこそが「みんなの学校」なのだと伝えました。
その後、グループでの対話を入れながら、「みんなの学校をつくる」「私がつくったみんなの学校」という2つのテーマで話を続けていきました。

最後にいただいた感想をいくつか紹介します。
●「みんなの学校」は2度目の鑑賞だが、自分の立場が変わると観る視点も変わり、映画の印象がガラッと変わった。子どもが小学校に行くようになり、学校の今の在り方に疑問を持つこともあり、文句から意見に変えていくようになりたいと思った。「保護者、地域が土になる 先生だけの責任ではない」と関わっていく一歩が踏み出せればいいなと思った。
●映画とお話を一つのきっかけとして対話ができたことが何よりよかったです。地域で対話を重ねながら当事者として学校や地域をつくる主体に自分自身もなっていきたいです。
●みんな一人一人がありのままの自分を受け入れてもらえているから、みんなが輝ける。それは本当にそう思います。映画の子どもたちがどう成長されたのかも、とても気になっていました。お話を聞く中で、人に理解される経験を通して、人を理解できる力につながっていくのだと、改めて感じています。
ご意見やご感想をありがとうございました。
私も音田さんや、参加された皆様から、たくさんのことを学ばせていただきました
自分の住む地域で、その構成員として何ができるかを考え、主体的に行動していきましょう。私たちは、教員や校長という肩書をなくしたら一人の大人、一人の「人」なのですから。
学校教育は、地域をも変える力があるのです。
編集部注:映画「みんなの学校」の詳細はこちらのリンクからご覧ください。上映会等随時開かれており、また自主開催も可能です。
イラスト/フジコ

宮岡愛子(みやおか・あいこ)
みんなの学校マイスター
令和7年度あかし教育研修センタースーパーバイザー。社会教育士。私立の小学校教員として教職をスタートするが、後に大阪市の教員となり、38年間務める。教員時代に木村泰子氏と出会い、その後、木村氏の「みんなの学校」に学ぶ。大阪市小学校の校長としての9年間は「すべての子どもの学習権を保障する」学校づくりに取り組んだ。現在は、「みんなの学校マイスター」として活動している。

