総合的な学習の時間で学んだこととリンクして学ぶ単元 【全国優秀教師にインタビュー! 中学校編 中1〜中3を見通す!「高校につながる英・数・国」の授業づくり #30】
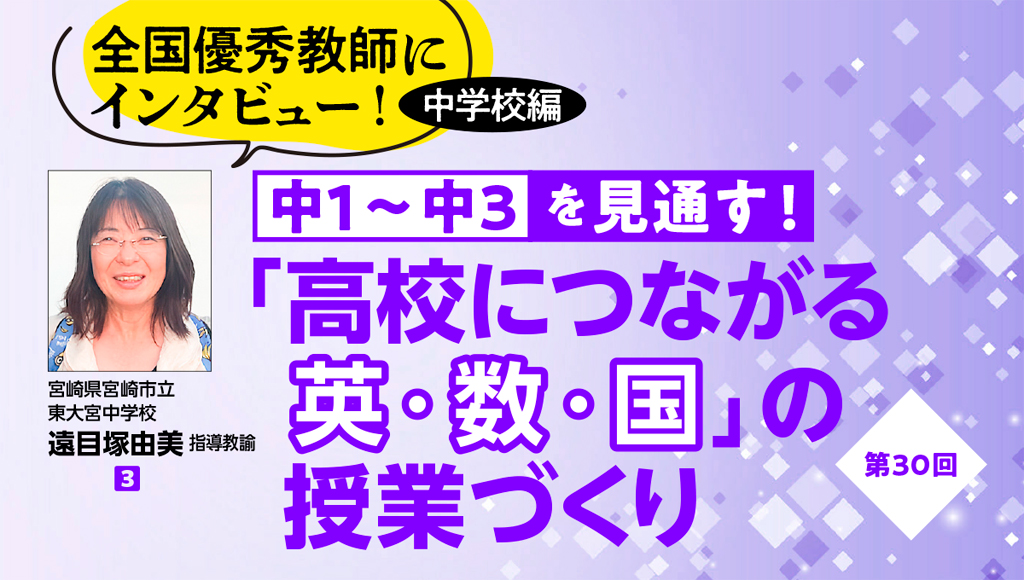
前回は、宮崎県のスーパーティーチャーである、宮崎市立東大宮中学校の遠目塚由美指導教諭に、単元・授業づくりの考え方について聞いていきました。3回目となる今回は、2年生の “Universal Design” の単元を紹介していくことにしましょう。

遠目塚由美指導教諭
目次
教材を通して何を学べるかということを常に大事に
今回、紹介していく2年生の “Universal Design” の単元は、前回の単元づくりの考え方でも紹介したように、子供たちが自分ごととして問いに向き合い、学習していけるような単元構成にしたそうです。地元の東大宮地区は誰もが住みやすい町になっているか、という問いから始まり、どんなところが問題でどのように改善したらよいかを各自が考え、発表をしていくのだと言います。そのとき、ポスターセッションにワールドカフェに近い学習方法を取り入れた形で発表を繰り返しながら、表現力をブラッシュアップしていった後、改めてユニバーサルデザインについて自分なりの意見をまとめさせる、と遠目塚指導教諭は話します。
「この単元の1つの特徴は、総合的な学習の時間(以下、総合学習)で学んだこととリンクして学んでいくことです。まず内容知としての、ユニバーサルデザインという意味では、1年時の総合学習で学んだSDGsなどとリンクしています。それ以上にここで大事にしたのは、やはり総合学習で学んだ方法知である、ポスターセッションなどの方法を生かして学んでいくことです(5/9〜7/9時)。
この3時間の各時間で生徒たちはグループ発表とポスターセッションを行います。次の時間、またその次の時間も相手を入れ替えて行います。つまり、3時間で、グループ発表3回、ポスターセッション3回の計6回各自が発表の練習をすることになります。そうした発表や聞き取りを繰り返すことで、英語で発表することに対して自信が生まれ、表現のスキルもアップさせることができます。もちろん、教材を通して何を学べるかということは常に大事にしています。ここでは、教材を通してユニバーサルデザインについて学ぶので、それは大事にしていくのですが、教科書内に『ユニバーサルデザインとは何か』という、英文での端的な説明が書かれています。それを読んでしまったら、『ユニバーサルデザインってそういうものなんだね』と生徒たちは納得し、そこで終わってしまいます。それでは深い学びにつながっていきません。ですから、問いを身近なものにして、自分ごととしてその問いを追求していく過程で、身をもってユニバーサルデザインとは何かについて考えていくわけです」

