学年で統一するとは?【伸びる教師 伸びない教師 第53回】
- 連載
- 伸びる教師 伸びない教師

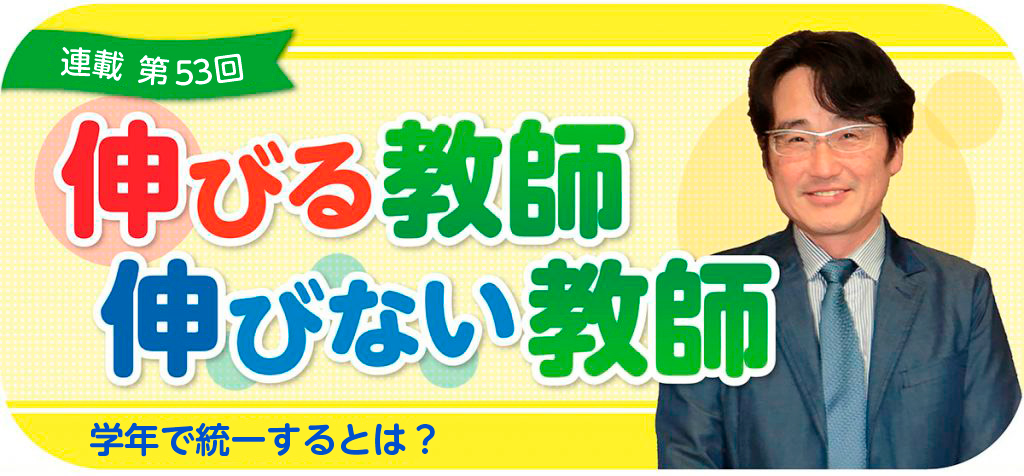
豊富な経験によって培った視点で捉えた、伸びる教師と伸びない教師の違いを具体的な場面を通してお届けする人気連載。今回のテーマは、「学年で統一するとは?」です。学年で何を統一するか、学級の個性はどうするか。学年で統一する際の視点についての話です。
執筆
平塚昭仁(ひらつか・あきひと)
栃木県公立小学校校長。
2008年に体育科教科担任として宇都宮大学教育学部附属小学校に赴任。体育方法研究会会長。運動が苦手な子も体育が好きになる授業づくりに取り組む。2018年度から2年間、同校副校長を務める。2020年度から現職。主著『新任教師のしごと 体育科授業の基礎基本』(小学館)。
目次
何のために学年で統一するのか
以前、異動したばかりの教師から新しい学校についてこんなことを聞きました。
「学年で統一するところが多くて自分でやりたいことができない……」
話を聞いてみると、1学年4学級あり、授業の内容、授業で使うプリント、まる付けの仕方、教室のレイアウト、掲示物、子供の持ち物……、いろいろなことをどの学級も同じように進めなくてはならないとのことでした。
学年で統一している理由は、「ある学級だけ特別なことをすると保護者からクレームが来るから」だそうです。
確かに学年が同じ歩調で進むことで、子供たちに同じような指導をすることができます。特に、1~2年目の若い教師にとってはありがたいことだと思います。しかし、ある程度、経験を重ねた教師からすると、先程のような声が聞こえてくることになります。
私も若いときに、異動した教師と同じことを感じていたので、自分が学年主任になったら学年で統一することをなるべく少なくしたいと思っていました。自分の中では、それぞれの学級が担任独自の学級経営で成り立っていれば、学年としても成り立つものであると考えていました。また、その中で互いが刺激し合い、切磋琢磨しながらよい学級をつくり上げていくことこそが大切だと思っていました。
学年での統一を必要最低限にした結果
私が初めて主任を任された5学年は4学級あり、若いけれども力のある教師がそろっていて、よい学年がつくれそうな気がしていました。学年で統一することは必要最低限にして、それぞれの教師の個性が表れるよう主任として配慮しました。
子供たちはとても素直で、落ち着いた学年でした。
もちろん、小さな問題はありましたが、学年全体として大きな問題となるようことはありませんでした。それぞれ力のある担任だったので、学級内で何か問題があっても担任の裁量で解決できていたからです。そのため、学年全体で集まって何かを話すことも年に数回でした。
5年生からの2年間、4人の担任はそのまま変わらず卒業式を迎えました。
ところが中学校に入学してしばらくたった頃、卒業した子供たちの学年が荒れているとの噂を聞くようになりました。
授業が成り立たない、教師に反抗する、服装や素行が乱れているなど、小学生のときの子供たちからは信じがたいようなことばかり耳にしました。
「あんなに素直だった子供たちがどうして」という思いが込み上げてきました。
当時の中学校が荒れていたとはいえ、そこまで荒れるには、小学校時代の自分の指導にも何か問題があったのではないかと悩みました。
思い当たったのは、学年としてのまとまりでした。
それぞれの学級が独立して成り立っていたため、学年全体で何かを統一することはまれでした。そのため、学級のルール、善悪の判断基準は、それぞれの学級でバラバラだったのです。ルールや善悪の判断基準の統一がされないため、結果、学年という100名を超える集団の思いがバラバラだったのではないかと反省しました。


