支援を要する子・気になる子Q&A|理想の授業と次年度への引き継ぎ

支援が必要な子どもに対して、正しい知識と子どもを見る目で、支援のセンスを磨いていきましょう。岡山県公立小学校教諭・南惠介先生に教えていただきました。問いに対する答えを自分で考えながら、読み進めてみてください。
執筆/岡山県公立小学校教諭・南惠介

目次
Q1 支援が必要なお子さんが入りやすい授業のスタイルとは?
新学習指導要領で言われる「主体的・対話的で深い学び」(以下、ここでは便宜的に「学び合い」とします)とインクルーシブ教育はそもそも親和性が高いと考えています。
まず、支援が必要な子どもの短所が長所となります。例えば、「ずっとじっとしているのが苦手」な子どもは、「ずっと活動的に動いてくれる」子どもと捉えられるようになります。「出し抜けに発言する」子どもも、「ひらめきをどんどん発表してくれる子」となります。
授業の形が変わることで、求められる「よさ」は変わり、たくさんほめる場面が出てきます。また、教師による一斉指導の場面が減ることで、その教師の「教え方」では理解しづらい子どもに対する、子どもたちどうしの「個別支援」が、あちこちで見られるようになり、いろいろな方法で教えてもらえるようになります。
また全員が指示を聞いていなくても、同じグループの子どもたちが、後からその子によりわかりやすい表現で伝えてくれます。ですから、「聞くのが苦手」な子どもも、子どもたちから簡単に「支援」を受け、スムーズに活動に入ることができるのです。
そのような日常の積み重ねの中で、それぞれの「苦手なこと」「できないこと」「支援や配慮すればできること」を子どもたちは自然に理解し覚えていきます。
もちろん、「学び合い」で何もかも解決するとはいきませんが、講義形式の一斉授業よりは、支援の面から言えばずいぶん楽になると思います。
低学年だから無理だと思われる方もいるかもしれません。しかし、幼稚園や保育園ですでに、協同的に遊んだり活動したりして、いろいろなことを学んできています。低学年だから無理、ではなく、もしかすると、他の学年に比べ一年生のほうが「学び合い」には適しているとさえ思うことがあります。
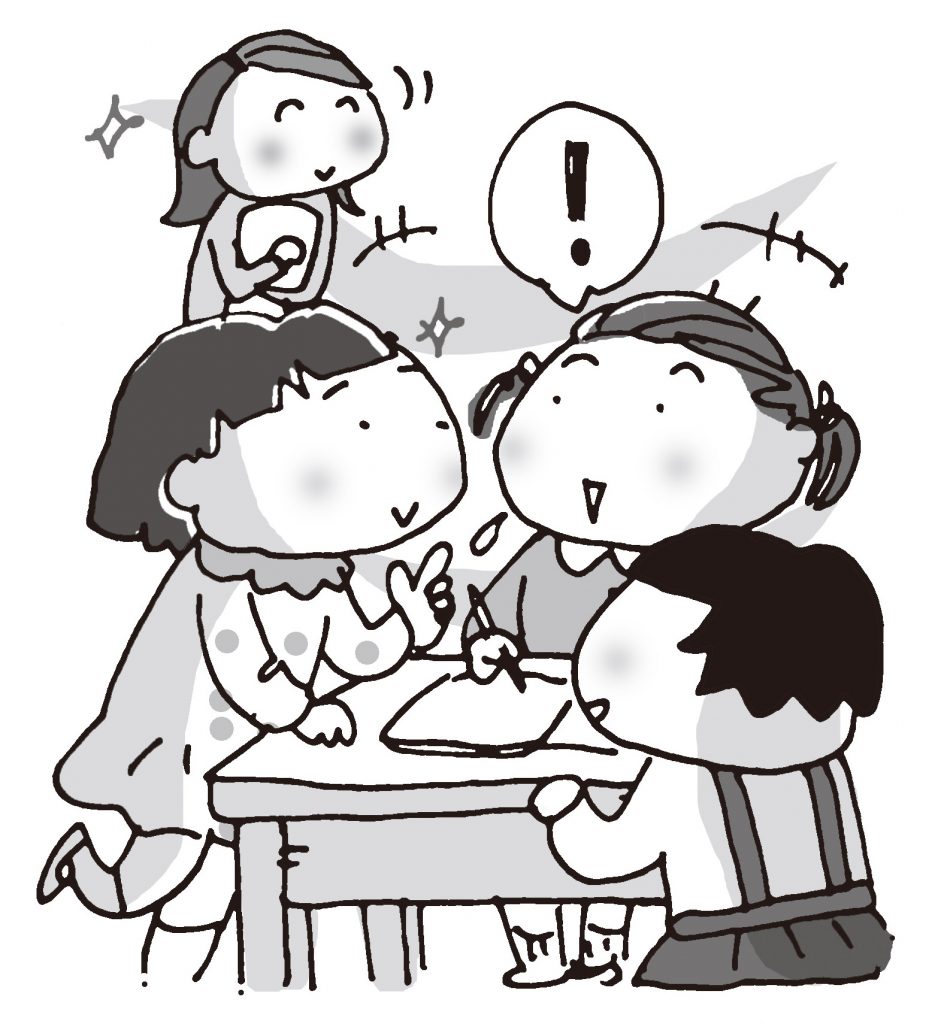
私は、実際に、入学三日目から短い時間での教え合い活動を入れてみたことがあります。7つの園から入学してきていたので、多くの子が知らないどうしの学級でしたが、見事に「学び合い」は成立していました。
その間、私は教室をぐるぐる回りながら「教えるの上手だね」「友達の説明がよく聞けるんだね」「いっぱい話ができるんだね」「そういうふうに道具を使うといいんだ」などと、その子たちの特性に合わせて声をかけていきました。
少なくとも「じっとしていなさい」とか「ちゃんと話を聞きなさい」というような注意や叱責はしなくてすみます。他の学年と比べ、幼いがゆえに教師とのかかわりをもちたがる子どもも多いでしょう。しかし、それは他の場面で補い、短い時間でもよいので、いろいろな場面で「学び合い」をさせていくことを試すことをおすすめします。

