【連載】令和型不登校の子どもたちに寄り添う トライアングル・アプローチ♯4 具体的にどうアプローチするのか

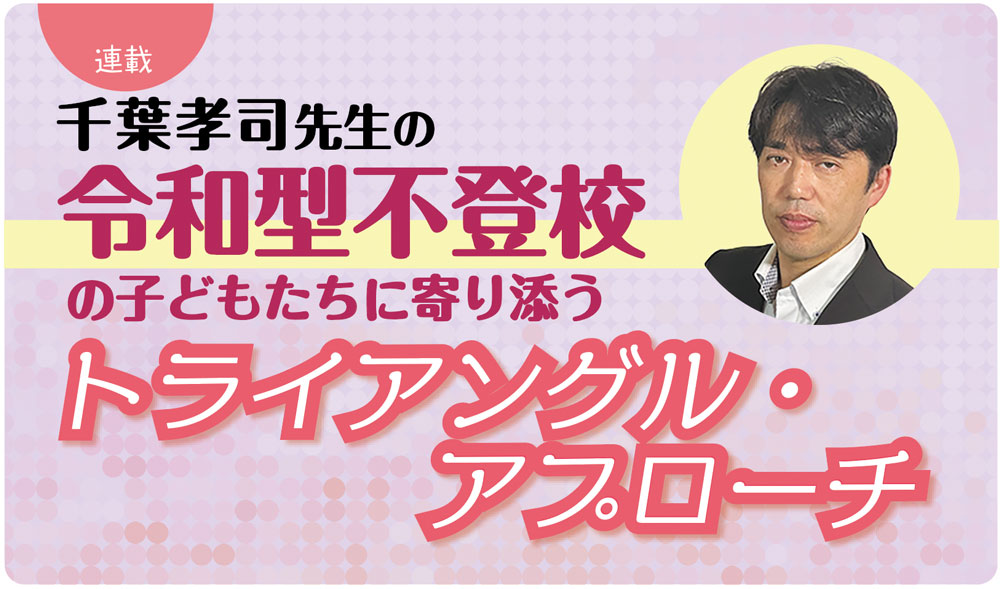
不登校児童生徒数が増加を続ける背景には「令和の子どもたちと、昭和型の学校システムとのミスマッチ」がある――と、不登校・いじめ対応の第一人者・千葉先生は言います。この連載では、そんな令和型不登校への対応を「トライアングル・アプローチ」と名付け、三角形を組み合わせた模式図を用いて解説、提案します。いよいよ今回からは実践編。千葉先生の温かい言葉かけモデルを、ぜひ参考にしてみてください。
執筆/千葉孝司(元・北海道公立中学校教諭)
目次
事例(架空事例)をもとに考える
トライアングル・アプローチは、実際どのように行えば良いのでしょう。日本全国で起きていそうなケースをもとに考えていきましょう。
以下は、担任の先生からの相談事例(架空事例)です。
小学5年生の担任です。クラスのAさん(女児)の欠席が10日ほど続いています。
お腹が痛いと言って休んでいるのですが、最近、親から本当の理由を聞きました。
Aさんはもともと勉強を苦手としていたのですが、授業中に「そんなのもわからないの?」と誰かに言われたらしいのです。クラスで確認したところ「そんなのもわからないの?」という言葉は、Aさんではなく他の子に向けられたもので、誤解だということがわかりました。
早く誤解を解いて、学校に来させたいのですが、お腹が痛くて会えない状況が続いています。同僚は体調が悪いのなら来なくていいんじゃないかと言いますが、それでは解決になりません。
直接会えない状況なので、親には事実を伝えているのですが、どんなふうに伝わっているかもわかりません。まずはAさんと直接話せるように、親から本人にプッシュしてほしいのですが、そんな様子も感じられません。どうしたら良いのでしょう。
(30代 男性M 小学校教諭)
「学校に来させよう」をアップデートする
Aさんの欠席が長引いたらどうしようと焦る気持ち、本人や周囲に対してじれったく思う気持ち。
担任ならそんな気持ちを持つのは当然です。でも、まずは深呼吸をしてみましょう。今の状況を許せないから不安になります。不安なままだと広い心を持つことが難しくなります。不寛容な態度は、周囲に不安感を増やしてしまい、ものごとがうまく進まないことにつながります。
トライアングル・アプローチの第一歩は、安心を与えるということです。まず子どもの安心について考えていきましょう。
職員室の中で不登校の子どもが話題に上ったときに、「学校に来させよう」という言葉がよく出てきます。
「学校に来させよう」の主語は、「私たちが」かもしれません。「我々教員が、頑張って子どもを学校に来させよう」という考えです。そこからは原因を取り除いて、それでも来なければ説得しようという考えが出てくるのではないでしょうか。つまりこういうことです。
不登校―原因+説得=登校
実際には不登校は、原因を取り除いても解決しないケースが多くあります。説得に至っては逆効果です。つまり、上の式は間違っているのです。この間違った式で努力しても効果は出ません。
だからと言って「来ても来なくてもどちらでもいいよ」というのも何か違います。そもそも行きたくても行けないのが不登校だからです。
実際はこのようなものでしょう。
不登校+安心+自信=登校
「学校に来させよう」ではなく、「子どもが学校に来るためには何を加えたら良いのだろう」という考え方です。

