インタビュー/森万喜子さん|「そろえる」のをやめて「働き方改革」をもっとクリエイティブに【今こそ問い直す!先生を幸せにする「働き方改革」とは⑨】

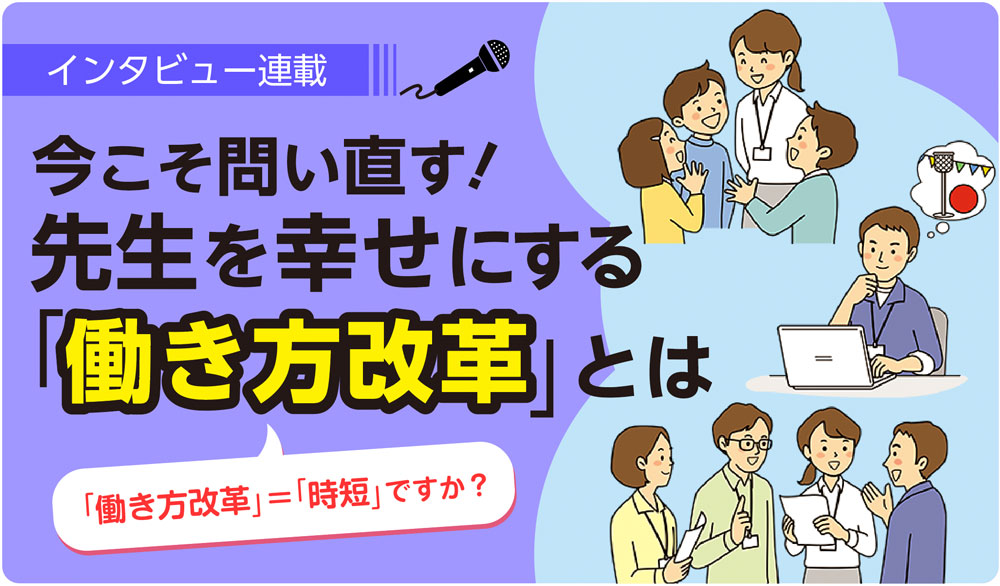
全国の学校で、今進められている「働き方改革」。ともすると時短ばかりが強調されがちですが、本当の意味で教師の仕事にやりがいや楽しさを感じられる改革になっているのでしょうか。学校教育のオピニオンリーダーの方々に改めて「働き方改革」の本質を語っていただきながら、子供も先生も皆が幸せになる「これからの教師の働き方」について考えていきます。連載第9回は、元小樽市立朝里中学校校長の森万喜子先生にお話を伺いました。
〈プロフィール〉
森万喜子(もり・まきこ)
北海道生まれ。北海道教育大学特別教科教員養成課程卒業後、千葉県千葉市、北海道小樽市で美術教員として中学校で勤務。教頭職を7年務めた後、2校で校長を務め、2023年3月に定年退職。前例踏襲や同調圧力が大嫌いで、校長時代は「こっちのやり方のほうがいいんじゃない?」と思いついたら、後先かまわず突き進み、学校改革を進めた。「ブルドーザーまきこ」との異名をもつ。校長就任後、兵庫教育大学教職大学院教育政策リーダーコース修了。現在は、執筆活動や全国での講演の他、文部科学省学校DX戦略アドバイザー(2023~)、文部科学省CSマイスター(2024~)、青森県教育改革有識者会議副議長として活躍中。単著に『「子どもが主語」の学校へようこそ!』(教育開発研究所)がある。

目次
「働き方改革」に対して感じている疑問
今、学校で行われている「働き方改革」を見ていると、疑問を感じることがいくつかあります。その中でも特に気になるのは、「在校等時間」の数値だけを重視してしまう、計りすぎです。
全国のどこの学校も教育委員会に対して教員の在校等時間の報告をしています。もしもその数値が高ければ教育委員会から「あなたの学校は在校等時間が長いね」などと指摘されるため、それを避けるために一生懸命頑張って働きかけている管理職が多いのではないでしょうか。そのような学校では、「早く帰る」ことが「働き方改革」の目的になっているように見えます。その前に、なぜ早く帰れないのかを考えてみなくてはいけないと思うのです。
教員は全員がマニュアル通りに同じ作業をしているわけではありません。子供たちが生活する場ですから、日々トラブルが起きるので「時間だから今日はここまで」と打ち切れない対応も生じます。「こうしたほうがいいんじゃない?」とクリエイティブな仕事をしている場合もあります。教員は、免許を取るために大学でたくさんの単位を取得しなければいけない専門職ですから、その人の裁量や知見に委ねられている部分があります。教科書の指導書通りに授業をやって、余計なことはしなくていいから帰ってね、というのが馴染まない職場であり、よりよい教育を求める教員だからこそ帰れないことを分かってあげたいところです。
また、在校時間を短くするために、教員が本当は学校にまだ残っているにもかかわらず、帰ったことにして仕事を続ける学校もあると聞きます。子供たちに「うそはダメ、改ざんはダメ、隠蔽はダメ」と教えているのに、教員たちはうそをついています。苦しまぎれとはいえ、それが当たり前になっている学校もあるようですが、「それっていいの?」と私は問いたいのです。
管理職にしてほしいこと① 職員室の心理的安全性を確保する
そもそも「働き方改革」の本来の目的は、教育の質の向上です。それには先生方が元気で楽しくいてくれないと困ります。その目的を達成するために、管理職にしてもらいたいことが三つあります。
一つ目は、職員室の心理的安全性を確保することです。
学校で何を一番大事にするのかと考えたときに、私は子供の命に関わることだと思うのです。子供が朝、元気に学校に来て、下校時間に「今日もいろいろなことがあったけど、明日も頑張ろう」と、そんな気持ちで帰れることが大事だと思っています。
その部分を大事にするためには、子供を規則できつく縛るのではなく、学校として「絶対に譲れないこと」と、「これは緩い感じでいいんじゃないの?」ということなどを分けて考える必要があります。それには教員間で状況・背景・評価・提案の議論やコミュニケーションが求められるのですが、それらが今、「働き方改革」の影響もあって圧倒的に不足しています。
合意形成のためのコミュニケーションが少ないと、若い先生方は「マニュアルがほしい」と言います。「これはよい、これはダメと教えてくれたら、その通りに指導しますから」というのです。しかし、マニュアルをつくって教員がその通りの対応をするのがいい場合も、そうじゃない場合もあるはず。私は「あなたの考えはどうなの?」と問いたくなります。
私は教員がクリエイティブであることを大事にしたいと思っています。ですから、若い先生も含めて、みんなで議論を重ね、合意形成を図ることを大事にしたいです。そのときに心理的安全性が保たれていなければ、誰も意見が言えず、声の大きい人の意見が通ることになります。それではイノベーションは起きないでしょう。
職員室の心理的安全性を確保する、といってもそれほど難しいことではありません。大事なのは雑談ができることです。例えば、放課後の職員室で学年の先生方が、「今日1日どうだった?」「あの子が今日こんなことを言っていたのよ」「え、すごいじゃん。この間からあの子は変わったよね」などと話をすることが大事なのです。そういった何気ない雑談から、まるでパズルのピースがうまくはまるかのように、「あの子のあの行動はそういうことだったのか……」と気づくのは、 中学校ではよくあることです。ですから、どんなに忙しくても日ごろの何気ないコミュニケーションの時間を排除してはいけないと思うのです。
しかし、コロナ禍もあり、「働き方改革」もありで、相談する、愚痴をこぼす、雑談をする時間を学校はもてずに今に至るのです。その結果、誰にも話せず一人で困り果てて潰れてしまう教員が出てきます。ある日突然、先生が学校に来なくなって、その穴埋めで他の先生がまた忙しくなってしまい……というループにはまっていませんか?
だからこそ、普段は雑談ができて、困ったことがあるときには「今、困っているんです」と言えて、それを聴いた人が「お互い様」と言ってお手伝いしてくれるような、そういう職場をつくる必要があります。
職員室の心理的安全性を確保するのは校長と教頭の仕事です。具体的には、雑談ができる時間と場所、おやつなどのちょっとしたしかけを用意してはどうでしょう。
例えば、私の校長時代は、校長室のドアを開けっぱなしにしておいて、「好きに使っていいよ」と言ってありました。私が校内を回って戻ってくると、校長室のテーブルで何人かが話をしていて、「すみません。ちょっと借りていました」と言われたこともあります。それでいいのだと思います。私の校長室には話が弾むように、お菓子が常に用意してありました。
それから、校長は個々の職員と1対1で面談をすると思うのです。そのときに、「先生は何を大事にしていて、どんなことをしたいと思っているの?」と聞いてみることをおすすめします。校長には一人一人の職員が何を大事にしているのかを知っておいてほしいからです。それを知っていれば、ちょっとした会話の中でも、その先生の発言に対して「なるほど。〇〇先生は国語の先生で、言葉にこんなこだわりがあるから、そういう切り口がありますね」などと納得できます。
さらに、職員室のコミュニケーションを活性化させるために、先生方が互いに大事にしているものを聞き合う機会を校内研修などでつくるのもいいと思います。たとえ15分間であったとしても、互いの大事にしているものが分かると、リスペクトが生まれます。共通点が見つかったら距離も近くなりますし、よい人間関係が築けるかもしれません。組織とは、そうやってつくられていく側面もあるのですが、やはりコロナ禍の影響も大きかったようですね。

