高学年の担任経験者に聞く学級運営のコツ
五年生は、心身ともに大きく成長し、思春期に突入する時期。今回は、小五担任経験者の先生方にお集まりいただき、ご自身の体験から、子ども心理理解、保護者対応などの注意点とともに、小五を受け持つ醍醐味、面白さについて語っていただきました。
子どもの言動にアンテナを張り、丁寧な声かけを
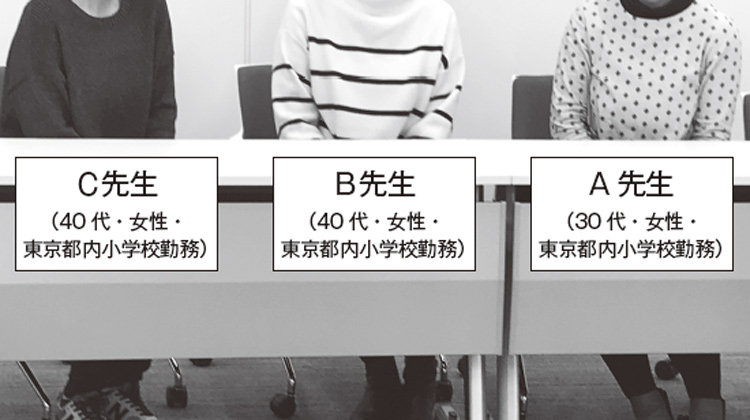
六年生の引き立て役に回る役回り
――学校では五年生はどのような学年ですか?
A先生:五年生になると、委員会活動などが始まり、学校の中でも、低学年や中学年を引っ張っていく立場になります。目標のイメージとしては、低学年は「言われたらできる」、中学年は「言われなくても自分のことはできる」で、高学年になると、「人の世話までできるようになる」。そこまで意識させるようにします。
C先生:確かに高学年として学校を引っ張っていく立場になるのですが、ちょっとかわいそうな立ち位置でもありますよね。委員会でもやはり中心になるのは六年生。一年生の世話は六年生がやり、五年生は、中間管理職的立場で、どうしても六年生の引き立て役になってしまう。
B先生:五年生は、頑張ってもなかなか光が当たらない立ち位置の学年。だから、上手にほめて、声がけをして、モチベーションを上げてあげることが大事ですよね。

