分析|益川弘如 子供の意欲を高め、深い学びを実現する授業とは? 【緊急分析! PISA調査最新結果 「読解力躍進」の真実 #2】
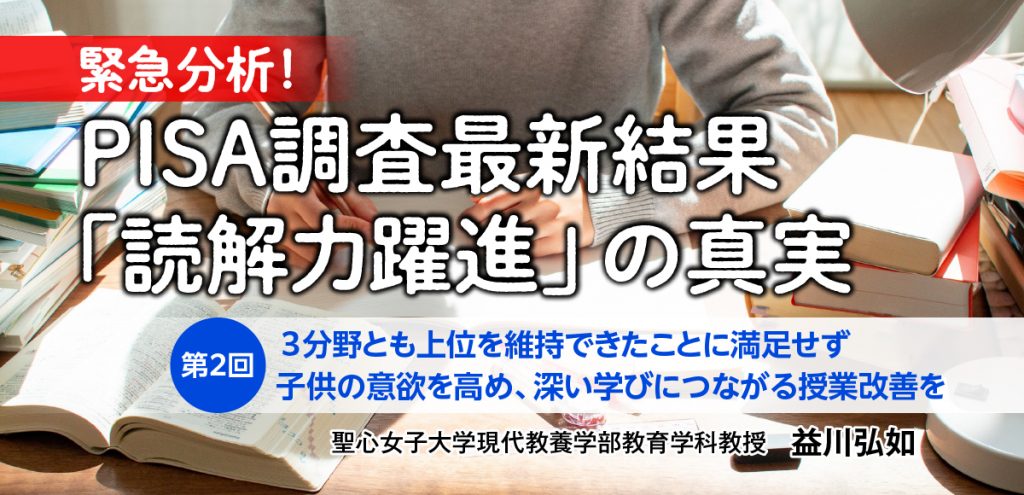
PISA調査2022の結果が、公表されました。今回は、読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシーの3分野とも順位が上昇し、ほっとした方も多いのではないでしょうか。なぜ順位が上がったのかについては、文部科学省やOECD(経済協力開発機構)がすでに分析していますが、もっと多面的な見方をしたいと思い、国内の有識者に意見を聴いてみることにしました。結果を分析するとともに、今後の課題を明らかにする2回シリーズの第2回目は、学習科学・教育工学の観点から、対話を通した深い学びを実現する学習環境について研究している聖心女子大学の益川弘如教授に話を聴きました。
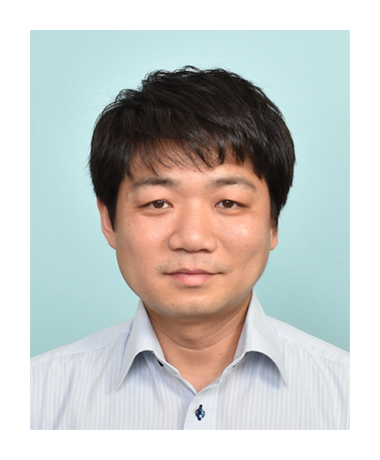
益川弘如(ますかわ・ひろゆき)
博士(認知科学)。中京大学情報科学部認知科学科助手、静岡大学教職大学院准教授などを経て2017年4月より現職。専門は学習科学、認知科学、教育工学。主体的・対話的で深い学びを通して資質・能力をいかに育むか、先生方や生徒たちの学習観・授業観を変えていく授業づくりと学習評価、研修の取組について実証的に研究を進めている。主な著書・訳書として、『21世紀型スキル―学びと評価の新たなかたち』(北大路書房、2014)、『学びのデザイン:学習科学』(ミネルヴァ書房 、2016)などがある。
■ 本企画の記事一覧です(全2回予定)
●分析|田中博之 日本の高校生の学力は、ほぼ「世界一」だと言える理由
●分析|益川弘如 子供の意欲を高め、深い学びを実現する授業とは?(本記事)
目次
順位の変動はそれほど気にする必要はない
PISA2022の全参加国・地域の中での日本の順位を前回と比較しますと、読解力は15位から2位へ、数学的リテラシーは6位から5位へ、科学的リテラシーは5位から2位へと上昇しました。
日本が3分野すべてで上位を維持できた要因について、国立教育政策研究所(以下、 国研)は「OECD生徒の学習到達度調査 PISA2022のポイント」の中で分析しています。それによると、コロナ禍における休校期間が日本は他の国々に比べて短かったことなどが要因として挙げられていますが、私はそれよりも他国の学力が相対的に下がったことが、一番大きな影響を与えているのではないかと思います。
ではなぜ、日本の子供の学力はなぜ下がらなかったかというと、学力を保障するために国の支えがあったことが大きかったのではないでしょうか。この調査に参加した日本の高校1年生は、中学生のときにコロナ禍の影響を受けていますが、休校期間中にGIGAスクール構想が動き出しました。すべての小中学生に 1人1台端末が配備され、必要に応じてWi-Fiのルーターの貸し出しをした自治体もあります。調査結果の中で、社会経済文化的背景(ESCS=Economic, Social and Cultural Status)、つまり、生徒の家庭環境による影響が他国よりも小さかったことにも、その効果が表れています。コロナ禍で各自治体の皆さん、学校関係者の皆さんが子供の学習環境の整備に真剣に取り組まれた結果だと思います。
また、3分野の中で、特に読解力の全参加国・地域での順位が、前回の15位から2位へと大きく上昇したため、どうしてだろうと気になっている方もいるかもしれません。その原因について国研の資料には、前回のPISA2018で課題とされた、複数の課題文から必要な情報を探し出したり、情報の信ぴょう性を評価したりしたうえで自分の意見を説明するようなタイプの問題の点数が微増した、というようなことが書かれていますが、それだけでこれほど順位が上がるのだろうか……と疑問を感じます。順位が上がった要因は何かといった議論になると、 多くの方が様々な仮説を述べられますが、おそらく様々な要因が関係していますので、「これが原因で読解力の順位が上がった」と判断するにはデータが足りないと感じます。
そもそもPISA調査の各分野の順位の変動については、一定の順位まで上がっている国々であれば、それほど気にする必要はないと考えます。
PISA調査を行っているOECDは、世界中の子供たちが将来社会で活躍できるように、どの国も一定水準の教育をしてほしいと願っています。そのために課題のある国は改善してほしいことから、あえて順位を付けています。日本は常に比較的上位にいますので、順位について議論すべきフェーズではないと思います。調査問題の中身を見て、子供たちがより良い学びをして社会に巣立ってもらうためにはどうしたらいいか、それを考えるための材料を探すことが大事でしょう。
この結果に満足してはいけない理由
今回の調査結果を見て思ったことは、まず「主体的・対話的で深い学び」に向けた授業改善を続けていらっしゃる地域や学校の先生方は、自信を持ってそれを続けてください、ということです。
その一方で、現行の学習指導要領が完全実施になっても、一斉授業での基礎基本の指導でとどまっている学校もあります。そのような学校の先生方には今後頑張っていただいて、「主体的・対話的で深い学び」の方向にもっとシフトしてほしいと願っています。
私が今、危惧しているのは、「3分野とも前回よりも順位が上がったから、今のままの授業を続けていけばいいのではないか」と考える先生方が出てくることです。
確かに日本は、全参加国・地域の中で読解力は2位、数学的リテラシーは5位、科学的リテラシーは2位でした。3分野全てにおいて上位を維持できています。
しかし、PISA2022で出題された問題を見てみますと、中には正答率が2、3割程度の問題もあります。日本の中高校生は教科書で様々なデータの扱い方を学んでいますし、全国学力・学習状況調査もPISA調査の問題を意識して作成されていますので、もう少し正答率が高くてもいいのではないかと感じます。ですから、相対的に順位が上がったか下がったかではなくて、学習指導要領で目指している日本の教育の姿に近づいているのかどうかを、 PISA調査の結果から丁寧に読み取っていく必要があります。

