分析|田中博之 日本の高校生の学力は、ほぼ「世界一」だと言える理由 【緊急分析! PISA調査最新結果 「読解力躍進」の真実 #1】

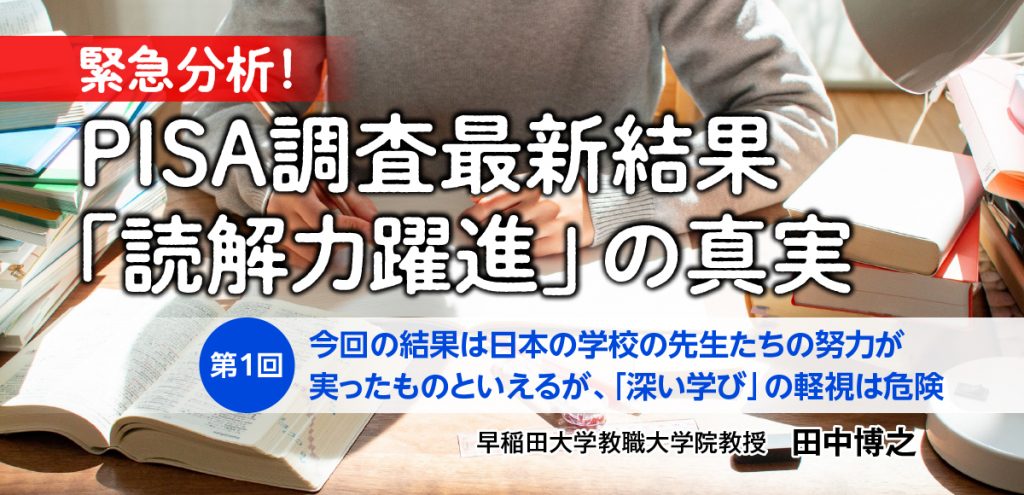
PISA調査2022の結果が、公表されました。今回は、読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシーの3分野とも順位が上昇し、ほっとした方も多いのではないでしょうか。なぜ順位が上がったのかについては、文部科学省やOECD(経済協力開発機構)がすでに分析していますが、もっと多面的な見方をしたいと思い、国内の有識者に意見を聴いてみることにしました。順位が上昇した理由を分析するとともに、今後の課題を明らかにする2回シリーズの第1回目は、早稲田大学教職大学院の田中博之教授に話を聴きました。

田中博之(たなか・ひろゆき)
1960年北九州市生まれ。大阪大学人間科学部卒業後、大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程在学中に大阪大学人間科学部助手となり、その後大阪教育大学専任講師、助教授、教授を経て、2009年4月より現職。2007~2018年度、文部科学省の全国的な学力調査に関する専門家会議委員。現在、21世紀の学校に求められる新しい教育を作り出すための先進的な研究に取り組み、全国の小中学校に助言を行っている。『アクティブ・ラーニング「深い学び」実践の手引き』(教育開発研究所、2017)など著書多数。
■ 本企画の記事一覧です(全2回予定)
●分析|田中博之 日本の高校生の学力は、ほぼ「世界一」だと言える理由(本記事)
目次
今回の順位をどう見るか
PISA調査とは、OECD(経済協力開発機構)が進めているPISA(Programme for International Student Assessment)と呼ばれる国際的な学習到達度に関する調査です。読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシーの3分野について、3年ごとに調査を実施することになっていますが、新型コロナウイルス感染症の影響で、2021年に予定されていた調査が2022年に延期されました。日本からは高校1年生約6,000人が参加し、2022年6月から8月の間で実施されました。
2022年度のPISA調査に参加したのは、81の国と地域です。全参加国と地域の中での順位を見てみますと、読解力は前回の15位から3位へ、数学的リテラシーは6位から5位へ、科学的リテラシーは5位から2位へ、というように、どの項目についても順位が上昇しています。
一方、OECDの加盟国は37か国です。これは経済的規模が世界で上位の国々なのですが、その中での日本の順位を見てみますと、読解力は2位、科学的リテラシーは1位、数学的リテラシーは1位です。
少し専門的な話になりますが、PISA調査は IRT(Item Response Theory)と呼ばれる統計の高度な手法で実施しています。問題の中に、過去に出題した問題が一部含まれていて、過去の同年齢の生徒たちがどれくらい答えていたのか、との比較もしています。
国立教育政策研究所が公表した資料の中で、「統計的には、読解力及び科学的リテラシーは有意に上昇、数学的リテラシーは、有意差はない」と分析していますので、統計的に信頼性のある形で読解力と科学的リテラシーの学力が上昇したことが証明されました。
つまり、今回のPISA調査で日本の学校教育の成果を国際的な学力調査で実証したことになり、日本は、OECD加盟国の中では、ほぼ世界一学力の高い国になったと言っても構わないと思います。
この結果は、日本の学校の先生方が取り組んだコロナ禍での休校期間中の様々な指導のあり方、休校明けの指導の仕方の工夫などが相まって導かれたものです。先生方の努力が身を結び、それが統計的に証明されたことは、大変喜ばしいと思います。
文部科学省とOECDは三つの理由があると分析
今回、読解力と数学的リテラシーと科学的リテラシー、3つの分野すべての順位が上昇した理由を、文部科学省は三つあると分析しています。OECDもほぼ同じ分析結果を出しています。
一つ目は、 新しい学習指導要領の影響です。小学校は2020年度から、中学校は2021年度から全面実施となり、高等学校は2022年度の入学生より年次進行で実施されました。この学習指導要領では、「主体的・対話的で深い学び」が推奨されています。つまり、課題解決的な学習、あるいは、問題解決的な学習をすべての教科で推奨しています。
PISA調査で求められるのは、ただ計算問題を解ければよい、 基本的な単語の意味がわかればよい、といった基礎的な学力ではありません。どの分野でも複数のデータ、複数の写真など、様々な複数の資料を組み合わせながら、共通点や相違点を見つけて、そこから情報を読み取ることが求められます。記述したり、選択肢を選んだりするときも、複数の資料からの読み取りに基づき、 かなり高度な思考力、判断力、表現力が求められますので、課題解決的な学習や、問題解決的な学習を経験していないと答えられないはずです。
それから、対話的な学びで、グループの中で意見を練り上げること、例えば、よい意見を取り入れて、自分の意見を修正したり改善したりする、 そういう粘り強い取組を行ってこないと成果を出せないと思います。
以上のことから、一定程度は、学習指導要領の改訂に基づく授業改善が進んだ結果である、と言えると思います。これには私も同意します。
二つ目は、コロナ禍での日本の中学校の休校期間が、諸外国に比べて短かったことです。今回、調査に参加した生徒たちは、中学校で休校を経験しています。休校期間は自治体によって異なりますが、私の知る限り、多くの学校では1か月程度だったのではないかと思います。生徒への質問調査で、「新型コロナウイルス感染症のため3か月以上休校した」と回答した生徒の割合が、日本は15.5%であり、OECD平均(50.3%)よりも少なく、世界の中でも日本は休校期間が極端に短かったことがわかりました。そのことがよい結果をもたらし、学力が上昇したと文部科学省やOECDは分析しています。
三つ目は、ICTを活用する力の向上です。2015年実施のPISA調査から、CBT(Computer Based Testing)、コンピューターを使ったテストに変わりました。生徒はコンピューターでマウスを動かしながら、資料を検索したり、組み合わせて比較したりして、回答をコンピューターに入力したり、選択肢を選んだりするわけですが、前回、2018年の調査の段階では、コンピューターのテストを受けたことがある生徒は、おそらく1割もいなかったのではないかと思います。そのため、前回はそれが不利に働いたのでしょう。
今回の調査の前に、日本の小中学校には1人1台の端末が配備されていました。調査に参加した高校1年生の生徒たちは、中学3年生のときに、端末を使っていたと思われます。
そして、高校1年生になると、1人1台の端末の所持を義務づけていた高校が多かったのではないかと思います。PISA調査が実施されたのは6~8月ですから、1学期の短い期間ではありますが、授業で使っていたのではないでしょうか。
このように、前回の調査に比べると、日本の高校1年生のICTリテラシーは格段に上がっていました。つまり、学力そのものが高くなったわけではありませんが、コンピューターでのテストによりよく回答することができるようになったということです。これも前回よりも順位を上げた理由の一つだと言えます。

