提言|赤坂真二 不登校急増の今、学校が取り組むべきことは? 【不登校、コロナダメージを克服するために 今こそ、学校全体で「学級経営」を! #01】
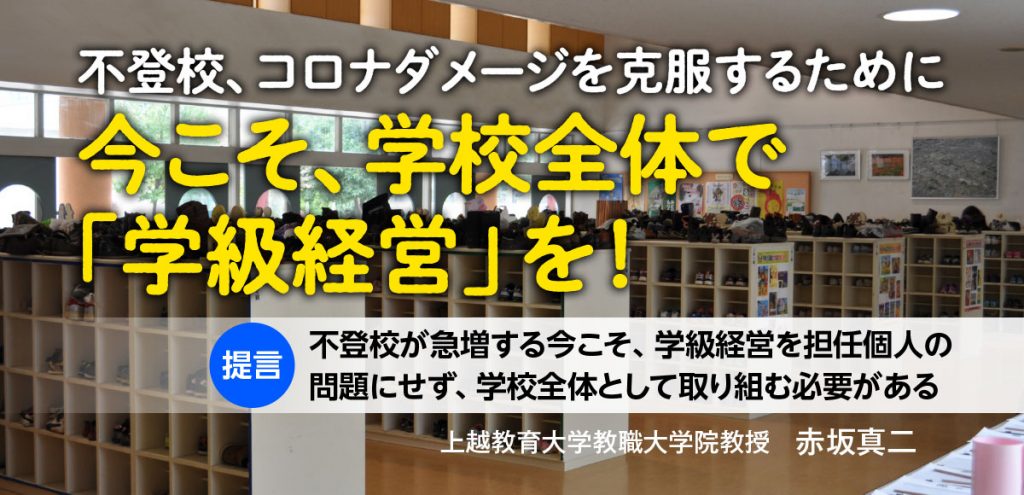
コロナ禍をきっかけに、小中学校では不登校の児童生徒が急増しています。原因は子供によって様々だとは思いますが、子供が友達とうまく関われなくなり、学校が居心地のよい場所ではなくなっていることが、一因だといえるのではないでしょうか。そこで、もっと居心地のよい学級、学校にするために、学校が今、すべきことは何だろうかと考えたときに、たどり着いたのは学級経営でした。今、求められる学級経営の在り方について考える4回シリーズの第1回目です。今回は、学校全体として学級経営に取り組むことの重要性を、上越教育大学の赤坂真二教授に語っていただきました。

赤坂真二(あかさか・しんじ)
新潟県生まれ。19年間の小学校での学級担任を経て2008年4月より現所属。現職教員や大学院生の指導を行う一方で、学校や自治体の教育改善のアドバイザーとして活動中。2018年3月より日本学級経営学会、共同代表理事。『学級経営大全』(明治図書出版、2020年)など著書多数。
■ 本企画の記事一覧です(週1回更新、全4回予定)
●提言|赤坂真二 不登校急増の今、学校が取り組むべきことは?(本記事)
目次
ある小学校の日常から見えてくるもの
これは、ある小学校の教頭先生から聞いた話です。この学校では現在、荒れたクラスがいくつかあり、子供による暴言や暴力の事案が毎日起きているのだと言います。
子供たちからよく聞かれる言葉は、「あいつが先に『死ね』って言ったのに、 なぜ自分は言っちゃいけないの? 言わないままじゃ負けだろう」です。これがこの学校の子供たちのスタンダードな言い分なのだそうです。人にはそれぞれ感情があるのですから、折り合いをつけ、勝ち負けではなくwin-winになるための方法を探っていかなくてはいけないのですが、子供たちはコロナ禍の3年間に人と関わってこなかったために、関わり方を学んできていないのです。
学校が荒れてくると施錠しなければいけない場所が増えてきます。用具室などから、危険な物を持ち出し、教室内で振り回したりするので、 あらゆる箇所を施錠しないと子供が守れないからです。この学校でも校内のいろいろな場所を施錠しています。施錠しないと子供の安心・安全が守れないような状況では、学習意欲など湧いてこないでしょう。
この学校の先生方は、子供たちの問題行動の上澄みの部分を捉え、怒りで押さえつけてしまっているようです。その結果、子供たちは先生に不信感を募らせているのではないでしょうか。しかし、先生たちに悪気はないのです。手を抜いているわけでもなく、正しいと思うこと、つまり、教科指導を一生懸命やり、 教師の使命として、秩序を保たなければいけないと思い、厳しく指導をしています。ただ、学級経営や児童の発達について学んだ経験のある人が少なく、「なぜこの子は暴れなければならないのか」を考えてみる、子供の話を聴く、といった児童理解に基づく指導や、人とつながることが大事だと子供が感じるような学級経営が行われていないのです。
子供たちが問題行動をすると、当然のように先生は保護者に連絡します。すると、家では保護者が子供を怒りで押さえつけようとします。学校で先生が子供を叱り、家では保護者が叱るわけですから、子供たちは自分の感情の持って行き場がなくなり、それでまた学校で暴言や暴力に走る、という悪循環の中にいます。
このエピソードからわかることは、学級経営の視点がない中で教育活動を行っていくと、結局、教科指導に偏った教育活動が主になって、社会性の育成がほとんどされないままになってしまうことです。これはこの学校だけの話ではなく、今、日本中の多くの学校で同じようなことが起きているのではないでしょうか。
今こそ、学級経営に注目すべき理由
コロナ禍の影響もあって、子供たちがつながれなくなっている今こそ、学校が取り組む必要があるのは学級経営です。その主な理由を、今回は四つ挙げておきます。
一つ目は不登校の問題です。文部科学省の「令和4年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」によると、小中学校を30日以上欠席した不登校の状態にある子供は、前年度から5万4000人、22%増え、29万9048人となりました。10年連続で増加し、過去最多となっています。
しかし、ここには不登校以外の理由で休んでいる長期欠席者の数は含まれていません。つまり、それらの長期欠席者を合わせると、約46万人が30日以上学校に行っていないのです。別の調査では、「隠れ不登校」と言われる、教室外登校、部分不登校、教室にはいるけれども教育活動に関与できていないような、どちらにもカウントされていない子供たちの存在が明らかになっていますので、実質的な不登校状態の子供たちは、100万人に近いと推察されます。
気になるのは、子供たちが不登校になる原因です。文部科学省の調査で、これまで不登校の要因に関する質問に答えていたのは、学校の先生でした。そのため、不登校の要因は、長い間、情緒的混乱であり、本人の個人的要因であるとされてきたのです。
しかし、文部科学省は令和2年度に、前年度に不登校になった経験のある小学校6年生と中学校2年生に対してアンケート調査を実施しました。その結果、不登校の引き金になったこととして、教師の存在や友人関係などが挙げられました。
先日、ある大学生が、自身が小学校時代に不登校になったときの心情を具体的に教えてくれました。彼女は子供の頃、学校に居場所がなかったというのです。競争的な価値観の中では、同じ学級の友達は、みんなライバルでした。みんなに話を合わせなきゃ、協力しなきゃ、勉強を頑張らなくちゃ、などといろいろなことが要求される中で、できないと感じることが増えてきて、だんだん自信がなくなったそうです。どうやったら自分はここにいられるのだろうかと、存在理由を探す日々を送っていましたが、そのうちに、何をどうしていいかわからなくなり、無気力になっていった、とのことです。
この例からもわかるように、不登校になる子供は、関係性要因から情緒的混乱に陥っているのではないかと推察されます。教室内の人間関係を調整していくのは、学級経営のカテゴリーです。学級経営として、人間関係形成能力の育成や人間関係を調整する方法を、カリキュラムの中で学んでいくことが、不登校を予防、軽減していくことにつながるのではないでしょうか。つまり、教師の存在やその指導行動は、不登校やいじめの要因になることもありますが、解決の切り札にもなりえる、ということです。
今、学級経営に取り組むべき二つ目の理由は、大人には見えないコロナダメージが、子供たちの中に蓄積されているからです。
例えば、コロナ禍という想定外の事態を経験したことで、もともともっていた価値観が揺らいでしまった子供もいると予想されます。自然災害などに遭遇し、多くの人々が命を落としていく理不尽な現実に直面すると、人間は努力をすれば報われる、正しい行いをすれば報われる、といった価値観が揺らいでしまうものだからです。
子供たちは今、何が大事なのかがわからなくなっていますし、保護者もわからなくなっているのではないでしょうか。そのため、人と人のつながりが大事、誰かを幸せにすることが自分の幸せにつながる、などと私たちがコミュニティを作っていくときに、大事にしてきた価値観が失われている可能性があります。
コロナ禍には、自宅からオンラインで教室の様子を映像で見られましたし、youtubeによる有名講師の授業も受けられました。1人1台端末によって子供たちの学力は保障されましたが、社会性やコミュニケーション能力は育ちませんでした。
子供たちがコロナのダメージから回復するには、人と人がつながることが大切であるという価値観を学級経営という営みの中で形成していく必要があります。
三つ目は、ウェルビーイング(well-being)です。ウェルビーイングとは、身体的、精神的、社会的に満たされている状態を表します。幸福(happiness)がより短期的で個人的なものであるのに対し、ウェルビーイングはもっと包括的で、個人のみならず個人をとりまく「場」が持続的によい状態であることが求められます。
2023年3月に公表された次期教育振興基本計画の中には、「ウェルビーイングの獲得的要素と協調的要素を調和的・一体的に育む日本発のウェルビーイングの実現を目指すことが求められる」と書かれています。
獲得的要素とは、自由と選択に基づく個人的な幸福を追求していくという、北米的な幸福観であり、協調的要素とは周りの人と一緒に幸せになるという、日本的な協調的幸福観を指します。日本人の多くは、自分一人で幸せになることに対して、少し後ろめたさや抵抗感を持ち、みんなで幸せになりたいと願っています。自分だけではなく、身近な周りの人たちと一緒に楽しい気持ちになること、大切な人の幸せを願うこと、平凡でも安定した日々を過ごすこと、そういった幸福感を大事にする人たちが多いのです。
つまり、人間関係ができていない環境では、日本人のウェルビーイングは低くなるということです。
もちろん、子供たちが人間関係のつくり方を学ぶのは、学級経営の場面だけではありませんが、教科指導では、あくまでもその方法論として人間関係の形成に取り組むのであり、これに対して特別活動は、よりよい人間関係の形成が主目的となります。現学習指導要領では、学級活動の機能によって学級経営を充実させることを求めていますから、子供たちのウェルビーイングを向上させるために、学級経営をもっと重視する必要があります。
四つ目は、学力とのかかわりです。学ぶ力と言ってもいいかもしれません。結局、学習とは社会的な営みなのです。例えば、友達に「ここを教えて」と言われて教えるとします。そして「ありがとう」と言われると、「教えてよかった」と感じ、「もっと勉強しよう」と思うでしょう。また、話合い活動の中で、自分の話をよく聞いてくれて、「〇〇さんは、そういう風に考えているんだ。面白いね。もっと教えて」と言われたら、気持ちよく話せますし、「もっと勉強しよう」と思えるものです。
このようにして、認知能力(学力など数値で測れる能力)と非認知能力(協調性や計画性、コミュニケーション能力など、数値で測りにくい能力)は、往還しながら高まっていきます。双方が高まることによって、ウェルビーイングが高まり、学習へのモチベーションが上がっていく、そういう構造にあります。
そのため、つながる力が弱くなると、学力が向上しないのです。 認知能力を、学力向上の一丁目一番地とするならば、それを高めるにはつながる力が必要であり、それは人間関係形成能力ですから、学級経営の営みの中で、身に付けられる力なのです。
また、学習意欲はクラスの学習規律、秩序が整っているときに高まることが、研究によって明らかにされています。この場合の秩序とは人間関係から作られるものであり、みんなで気持ちよく勉強できる環境をつくって一緒に勉強するから学力が高まるのです。つまり、学習意欲と秩序と人間関係は、全部つながっています。学級経営の営みの中で良好な人間関係をつくることがいかに大事なのかがわかっていただけるのではないかと思います。

