根本的に大事なことは何かを考えながら、授業をしなければダメ 【授業づくり&学級づくり「若いころに学んだこと・得たこと」第29回】
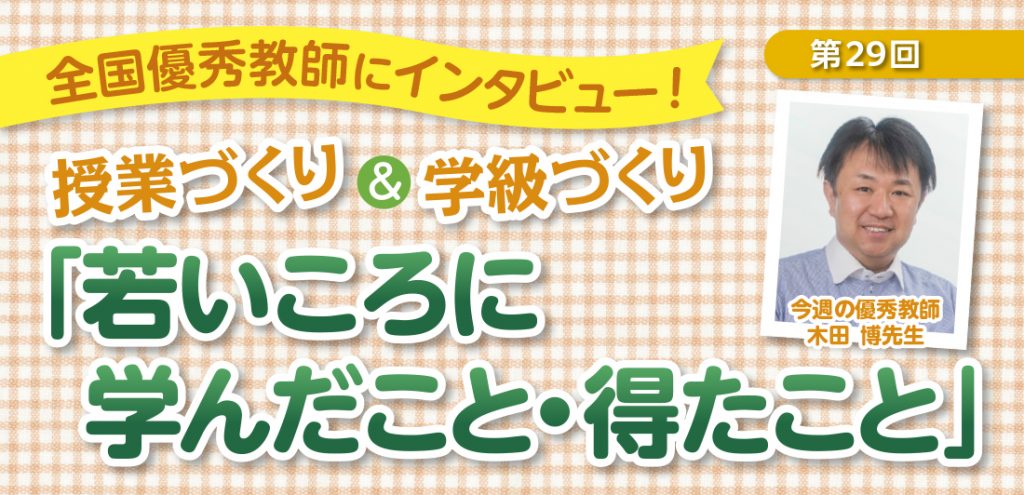
前回は、鹿児島市立学校ICT推進センターの木田博所長が教師を志したきっかけや、若手時代に学級づくりなどで失敗を通して学んだことを紹介しました。今回は、社会科を専門教科として選び、教科指導に力を入れていったことを中心に紹介していきます。
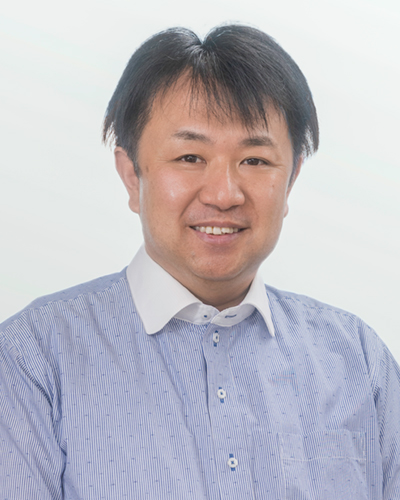
目次
一つの答えというものがないから、社会科を専門教科に
前回、初任校で学級づくりでの失敗から学んだことなどをお話ししましたが、その初任校時代に小学校教育研究会の社会科部に入って、教科研究をしていくようになりました。きっかけは当時、お世話になっていた先生からの声かけでした。「木田君は大学時代に何を専攻してたんだ?」と聞かれたので、「教育学科で教科の専門はないんです」と答えたら、「じゃあ、どんな教科が好きなんだ?」と問われるので、「高校のときに日本史の点数だけは良かったので、社会科は好きなほうです」と答えたのです。すると「じゃあ、社会科の研究会に来いよ」と誘われ、入会することになりました。
きっかけはそのようなことでしたが、私が社会科を専門教科として選んだのは、一つの答えというものがないからです。例えば、算数の授業をやっていくと基本的に答えは一つです。もちろん問題の解決の仕方は様々ありますが、答えは一つですし、最終的に「これができるようになる」ということがはっきりしています。そのため比較的、得意な子、不得意な子が分かれやすい傾向があるのではないでしょうか。
それに対して、社会科の場合はシンプルな一つの答えというものがないわけです。もちろん、「鎌倉幕府が成立したのは何年ですか?」と問われれば、今なら「1185年です」と答えるのが正解になるわけですが、それすら以前は、「1192年」でした。とすると、「幕府が成立したというのはどういうことなのか?」というむずかしい問いが生じます。守護・地頭を置いたからなのか、征夷大将軍に任命されたからなのか、あるいはもっと別の統治機構を設置したからなのかと解釈が多様にあり、時代や研究の進捗によっても変化し得るものでしょう。そういったことを、子供たちと一緒に考えていくのがとても楽しいのです。
さらに社会科というものは、「これからどうするか」を考える教科でもあります。歴史について学んだことも、これからの問題を考えるときに、「そう言えば、似たような状況が過去にあったぞ」と、そこから学んで、現在のこと、未来のことを考えるわけです。例えば4年生になると、ゴミについて学習するわけですが、ちょうど私が若手の頃、鹿児島市でもゴミの有料化の問題がありました。それについて、有料化するとゴミが減るという考え方もあれば、それとは異なる考え方もあって、何を選択することがより良い未来につながるのか、子供たちと多面的・多角的に考えていく時間がとても楽しかったのです。教育学者で社会科がご専門の上田薫先生(東京教育大学教授、都留文科大学学長など)が、ご著書の中に「授業の価値は、その時間で何ができるようになったかではなく、どれだけ真剣に考えたかだ」という趣旨のことを書かれていましたが、それは私が社会科を教えるときの根幹にあります。

もちろん、教科ごとに覚えなければいけないこともあるわけですが、そういうことはできるだけ楽しくやろうと考えていました。例えば、理科で方角を覚えるのに、「北向いて、右手は東、左西。お尻は南」と、メロディを付けてダンスしながら覚えられるようにしていましたし、植物の発芽と成長でも「発芽の条件は~」と、踊りながら歌っていました。ただ繰り返して言って覚えるのはつまらないし、何かの動作や歌と一緒にして覚えると、エピソード記憶になって忘れないわけです。おかげで当時、担任していた子供と10年後に会ったとき、「先生、僕は高校入試のときにも発芽の条件は間違えなかったし、今も忘れていませんよ」と言われたこともあります。

