すべての教員が仕事と子育てを両立できる風土づくり・環境整備に取り組む【連続企画「学校の働き方改革」その現在地と未来 #08】
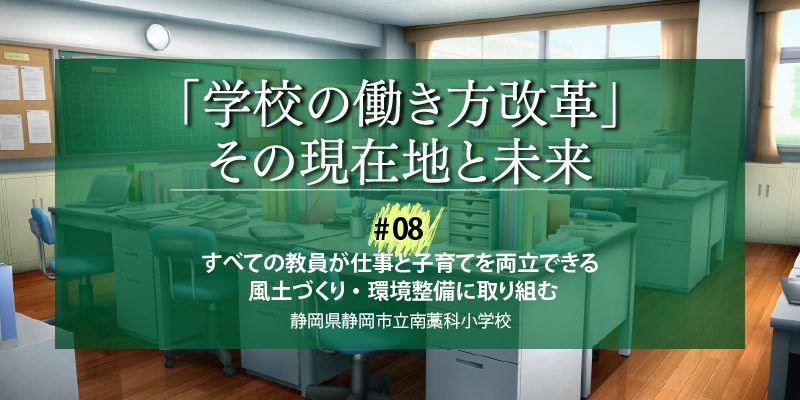
静岡市にある南藁科小学校(児童数128名)では現在、育児休業制度や部分休業制度を誰もが気がねなく取得できる環境の実現に向けて、様々な実践が行われている。2021年の赴任当初より、子どもが主体の学校づくりと同時に、教員たちが仕事と子育てを両立できる職場づくりに力を注いできたという小澤美加校長に話を聞いた。

静岡市立南藁科小学校
静岡市の北西部に位置する公立小学校。「自ら学び、共に高め合う 児童生徒」を学校教育目標に掲げ、豊かな地域の自然やあたたかな人との出会いを大切にしながら、自己肯定感や自己有用感を高める教育活動を進めている。
この記事は、連続企画「『学校の働き方改革』その現在地と未来」の8回目です。記事一覧はこちら
目次
学校だけの問題ではなく、必要なのは「全員の一歩」
「子育ては楽しく幸せなこと。学校も楽しく幸せな職場です。どちらの楽しさや幸せも味わえるのが、本来、教員のあるべき姿のはずなのに、この2つを両立させようとすると途端に難しくなるのはなぜなのか。私自身も育児の大変さを経験しましたが、教員としてのキャリアを通じて、同じように苦労されたり悩まれたりしている先生を見るたびに、この状況は決して良くないと思い続けてきました」
そう語る小澤校長が最初に行動を起こしたのは、教頭として赴任した前任校でのこと。休暇が取得しづらい学校の雰囲気を、管理職の立場で、改めて認識したときだった。
「とても取組と呼べるようなものではなかったと思いますが、先生たちには『休むことは悪いことではない』ということを伝え、長期休業中でなくても休暇を申請しやすい雰囲気づくりに努めました」
そして、少しでも教員の時間外労働を解消するために、勤務開始時刻より前に登校してくる子どもの保護者に対して、勤務体制が整っていない時間帯に子どもが登校してくることの保安上のリスクを説明し、登校時刻を遅くしてもらえるように働きかけたという。
「登校時刻の問題は、時間外勤務の問題、ひいては育休や部分休を取得しづらくしている理由にもつながるわけですが、とても学校だけで変えられるものではないというのが私の考えです。保護者、保護者の勤め先、そして社会全体が少しずつ変わっていく…、そうした『全員の一歩』が必要だと思っているので、私自身はその中で『学校の管理職としてできることは何かを考える』というスタンスで課題と向き合うことにしたのです」
学校の管理職として自分にできることを考える
一方、そのときの経験から、大それたことはできなくとも、管理職の適切なリーダーシップ次第で変えられることはあると手応えも感じたという小澤校長は、南藁科小学校に赴任後、改めて育児休業制度や部分休業制度の取得についても課題整理を行うことにした。
「最近は静岡市でも男性教員の育休取得率が向上するなど、事態は少しずつ良い方向に向かっていますが、それでもまだ『誰もが』とはいえない状況です。では、まだできない理由は何なのかと考えてみたところ、本校では次のような課題があることが見えてきました」
1)教員不足
2)職場の理解
3)保護者や地域の理解
4)時間外労働
5)経済的な負担
そうした中で、小澤校長が手始めに取り組んだのは、「職場の理解」を改めるために組織文化の変容を図ることだった。自分の子どもの授業参観へ行くことをためらっている教員がいれば、「自身の研修にもなるのだから、むしろ行くべき」と促したり、部分休業の取得が決して悪いことではないという認識を職員室全体で共有できるよう、休暇の理由をあえてオープンにするようにした。その結果、最近では、子育てに限らず、必要なときに気がねなく休みを申請する教員が増えてきているという。
「本人が伏せたい場合以外は、できるだけ皆に理由を知らせるようにしています。特に、入学式や卒業式といった行事への参加を理由に休まれる先生がいる時は、『今日は◯◯先生がお子さんの卒業式で休暇をとられています。おめでとうございます』と祝福のコメントも添えて、これはよい行いだと印象づけることも心がけています」

