事務職員主導の「職員室リノベーション」が教職員の意識も変えた【連続企画「学校の働き方改革」その現在地と未来 #07】
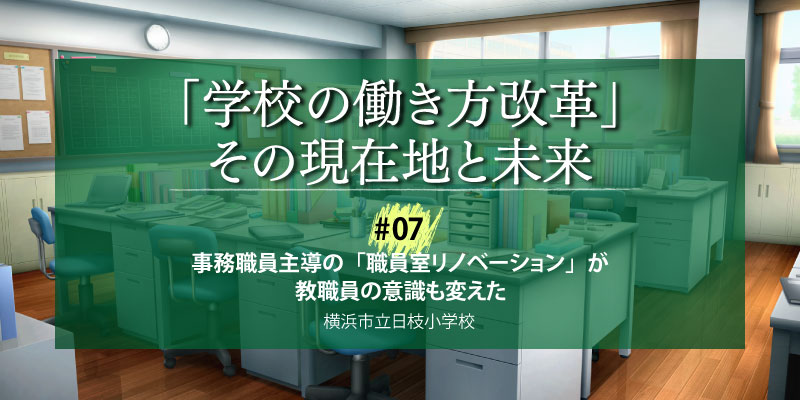
学校事務職員の上部充敬氏は、職員室のレイアウト変更などの「職員室リノベーション」や教職員の協働のあり方を試行錯誤しながら「働き方改革」に取り組んできた。共有机を導入したり、消耗品を文具店のように「見える化」したりすることで、職員室での働きやすさの向上につなげた。のみならず一連の試行錯誤のなかで教職員の間に意識の変化が起こり、働き方の変化につながっていくことを実感。上部氏はその取組と思考の変化を『チームで協働してリノベートする職員室の「働き方改革」』という本にまとめた。職員室のリノベーションが、どのような経緯で学校の働き方改革につながっていったのか、上部氏に聞いた。

横浜市立日枝小学校
横浜市立日枝小学校の事務職員・上部充敬氏。
この記事は、連続企画「『学校の働き方改革』その現在地と未来」の7回目です。記事一覧はこちら
目次
職員室リノベーションの始まり
上部氏が職員室リノベーションを軸にした働き方改革に取り組んだきっかけは、前任の富士見台小学校でたびたび目の当たりにしたある光景だった。
当時、インターネットは普及していたが、まだ安定していなかった。同校の教職員たちは接続を試みるも「今日はつながらない。今日はできない」とそのままにすることがあった。上部氏はそのたびに、「え、諦めちゃうの」と思ったという。
「それだけでなく、『パソコンがプリンターにつながらない』『〇〇の書類がない』と探しまわっていることもよくありました」
上部氏はこうした光景を見るたび「初任校で学んだことをもとに何か役に立てないか」と忸怩(じくじ)たる思いを募らせる一方、「きっと何かおもしろいことができる」とも思っていた。
すると、そんな様子を同じ思いで見ていた当時の校長が、上部氏に「環境改善をやってみないか」と声をかけたのだった。上部氏は8名の教職員とともに、「職員室レイアウト変更プロジェクト」への挑戦をスタートした。
「僕たち学校事務職員は税金で買ったものを最大限に活かすのが仕事。ですから改革はやっぱりモノから入っていくのがやりやすい。買ったものの配置でどのような変容が起きるのか、それを楽しむことから始めました」
外部コンサルタントや企業から学び、フィードバックを重ねる
上部氏は、教職員の共有の机を職員室の中央に置くという校長のアイデアをもとに、モノの場所をどう整理していくかというところから、徐々にレイアウトを“見える化”していった。
「これまで、年度末に職員の席替えで机を動かすことはあっても、何かを仕掛けるためにレイアウトをいじったり、それをトータルコーディネートしたりすることはありませんでした」
そのため、実際にリノベーションを実行するまでには1年の歳月をかけた。課題を抽出しながら「こうなったら望ましい」というビジョンを共有し、そのためにすべきことを議論していった。
上部氏たちは、仕事場のレイアウト変更でどのような変化が生まれるかを知るために、学校施設についての意見交換会に参加したり、企業やコンサルティング会社などに積極的に接触。事例や職場環境改善のポイントなどを学び、蓄積していった。
「当初は、学校に外部の人間を入れることに否定的な意見もありました。でも僕は、外部の人の視点や意見は大切だと考えていました。というのも、今職場で起こっている問題は、現状の教職員や組織の考え方から生まれるわけで、現状の考え方をする人たちだけで話し合っても解決はしないんです。違う視点をもった人から学んで視座を上げないと、解決策は見いだせない。それは当時の校長が教えてくれて、最初から積極的に僕らを外に連れ出してくれたんです。このおかげで、初年度以降、様々な方から学ぶたびに、感謝の思いとともに、学校をよりよくしていこうという思いが学校外にもたくさんあることに気づきました。実際に企業のサポートを受けたり、学校外の方から学ぶ経験を積むたびに、その思いは強くなりました」

