「今日は昨日より、良い先生になりたい」 【授業づくり&学級づくり「若いころに学んだこと・得たこと」第18回】
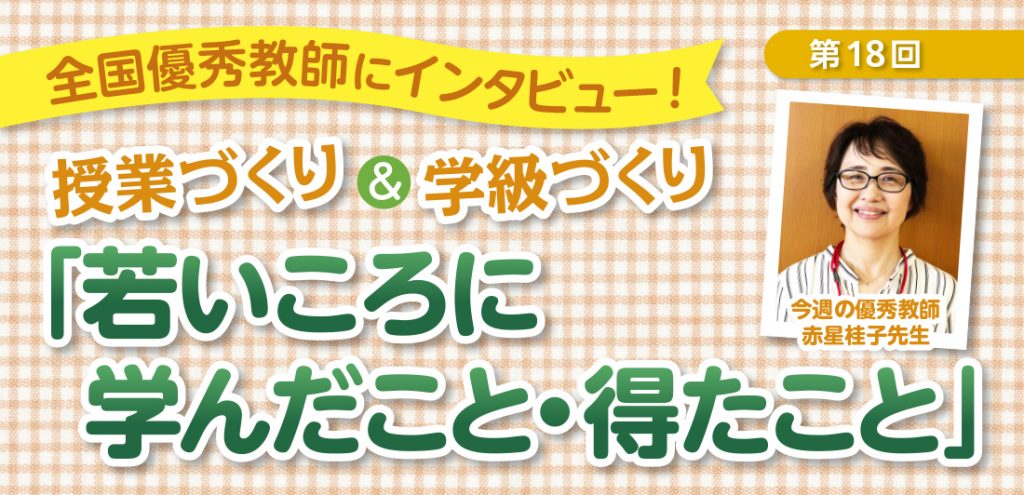
前回、熊本県の授業名人(小学校・道徳科)の赤星桂子指導教諭が、独自の学級経営を工夫していったことや、道徳の研究会の先輩方から学びながら道徳の授業づくりにのめり込んでいった過程を紹介しました。今回は、さらに独自の教材づくりに取り組んだことや、若手へのメッセージを紹介していきます。

目次
地域の方を招いて直接質問や対話をする
前回、道徳の授業づくりに取り組み始めた経緯をお話ししましたが、道徳の授業づくりということでは、道徳部会で学んだことを生かし、独自の教材づくりに力を入れた時期もありました。テーマは「身近にいる輝いている人」です。
例を挙げると、訪問看護師の保護者が筋萎縮性側索硬化症(ALS)の患者さんを看護されていました。その方は、かすかに動く脚でALS用のコンピュータを使って絵を描いておられ、その絵がとてもすばらしいという話を伺ったのです。私は「ぜひその方に会ってみたい!」と思い、早速、その保護者に連絡先を聞き、その患者さんに会いに行ってお話を聞きました。病気だからとふさぎ込むのではなく、明るく前向きに生きておられる姿に感動しました。そして、その精一杯生きる姿を道徳の教材にしたのです。
あるいは校区内の方で、捨てられた犬や猫を保護している方がいらっしゃると聞くと、やはりその方に会いに行って話を聞き、最終的にはその方と共に保護された犬や猫を学校に招いて道徳の授業をしました。そのように地域の人を教材にしていくと、やはりその地域だからこそ子供たちに響くところがあると思います。すばらしい教材のネタは身近なところにたくさんあるもので、それをキャッチする目が私たち教師には必要です。もちろん教材をつくるのは大変ではありますが、本物に触れると子供たちの目がキラキラして「本当にやってよかった」と思えるのです。
当時は今と異なり、教科書がなかったため、地域の方の力も生かした自作教材の授業を提案しました。現在は教科書があり、教科書教材を使うことが主流になっているので、教科書も大事にしつつ、それに関連する地域の方を招いて直接質問や対話をすることにより、子供たちの学びに向かう力を喚起するような形で実践してみてもよいのではないかと思います。

実は、こうした独自の教材をつくろうと考えたのは、自主的に研修に参加したことがきっかけでした。そのときにパワーポイントを使って、写真や資料などを貼り付け、言葉を添えて教材をつくっていくような授業づくりを勉強したのです。もし教材をゼロから文章だけでつくろうとすると、「最初のセリフは何にしたらいいか」などと悩んで、きっと「無理だ」と思ったはずでしょう。しかし、写真や資料と文章で構成するならば、「意外にできるかも」と思えるようになりました。
熊本県には、地域教材「くまもとの心」があります。その中の「道しるべ」という教材には、昔、旅人が行き倒れにならないように多くの道標を彫り、たくさんの人の命を救ったという話があるのですが、それを読んだら、「自分の目で見てみたい」と思うようになりました。実際にその場所に足を運び、地元の詳しい人を探して話を聞いたり、実際の道標の写真を撮ったりしたのです。そして、「人のために努力し続ける地元の人のことを子供たちに伝えたい」という熱い思いをもって授業をすると、実際に子供たちも「へ~っ、すごい!」と興味をもって学んでくれます。そんなとき、私自身も楽しくなります。そうした経験があったため、この勉強会を機に、独自の教材づくりに力を入れて取り組むようになりました。
全部の教科で教材づくりに取り組むということはむずかしいかもしれません。しかし、若い先生方も、まず自分の好きな教科、得意な教科で楽しく教材づくりに取り組んでみたら、授業のイメージも変わってくるのではないかと思います。

