「思考ツール」とは?【知っておきたい教育用語】
「思考ツール」とは、「どのような考え方で思考していくのか」をサポートするために用いられる手段です。思考ツールが求められるようになった背景や役割を解説するとともに、いくつかの例を紹介していきます。
執筆/創価大学大学院教職研究科教授・宮崎猛
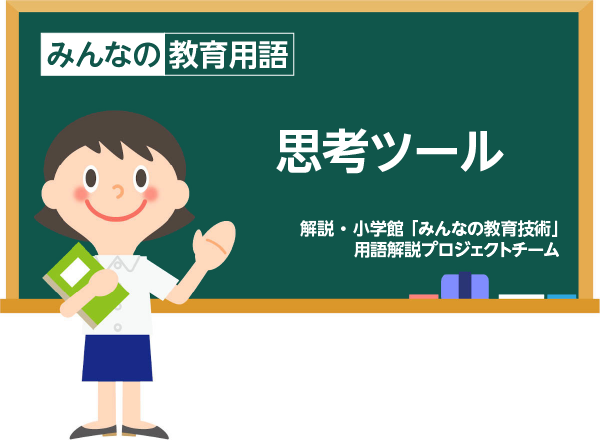
目次
思考ツールが求められるようになった背景
1980年代頃から「変化の激しい社会への対応」のキーワードとともに「思考力」の育成が強調されるようになりました。学習指導要領にも改訂のたびに「思考力」が学力の重要な要素として示されてきました。知識伝達型の教育では変化に追いついていくことができず、変化に対応する力の1つとして「思考力」の重要性が示されたのです。
一方、学校現場では、思考力はそれを捉えることの難しさなどから具体的にどのような方法で育成するかについての模索が続いてきました。現行の学習指導要領では「見方・考え方」を働かせることが求められ、「どのような視点で物事を捉え、どのような考え方で思考していくのか」を各教科で具現化していくものとされています。そこで注目されるようになったのが思考ツールです。思考力を育てるための思考実験なども奨励されるようになりました。
思考ツールの役割
学校では子どもたちの現在や将来の生活に必要な知識を伝授するほか、読み書き計算などのスキルや情報、知識を自ら獲得するための力、情報を吟味する力などを育成してきました。思考は知識や情報をより深く理解したり、検証したり、身に付けたり、すでにもっている知識と新しい知識を関連づけて蓄積したりするためなどに必要な働きや機能です。知識と思考は表裏一体のものと言えます。知識を整理したり、表現したりするための枠組みやプロセスを示したものが思考ツールなのです。思考ツールには様々な効用が期待されますが、一般に次のような目的で利用されます。
1 漠然としたイメージを意識させたり、明確にしたりする
2 ものごとの関連性や関係性を明確にする
3 複数の事実や意見、考え方などを比較したり、分類したりする
4 アイデアを生み出したり、広げたり、評価したりする
5 事実を多面的多角的に捉えたり、焦点化したりする
6 結論や自分の考えの理由を導いたり、意志決定したりする
7 なすべきことを見通したり、計画したりする
8 行ったことを振り返ったり、整理したりする
9 様々な事柄を順序立てたり、構造化したり、要約したりする

