新連載 「特活」という山脈の麓に立った日【玄海東小のキセキ 第1幕】
- 連載
- 玄海東小のキセキ
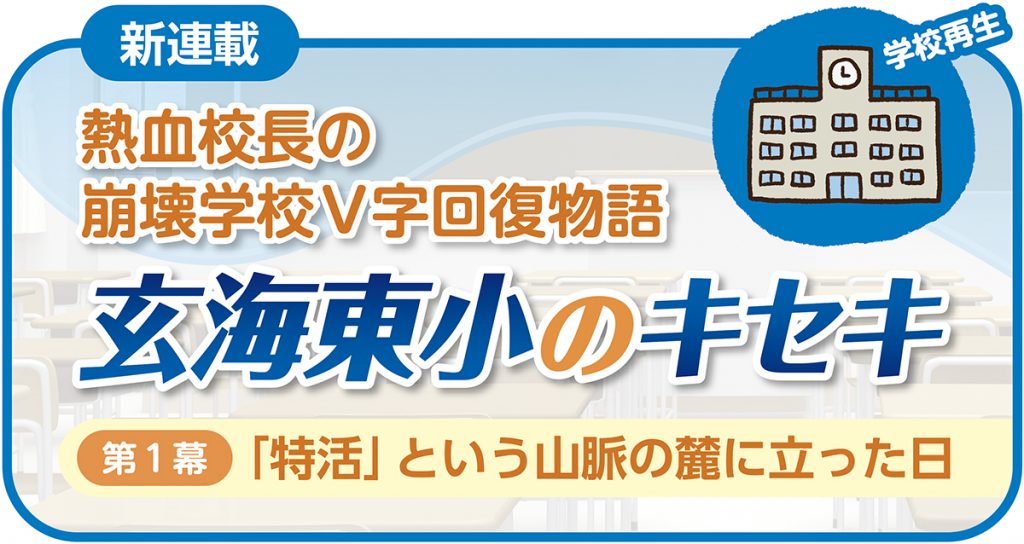
荒れた学校や学級を任せられたとき、あなたならばどうしますか? 脇田哲郎・福岡教育大学教授は校長時代に「子供が主人公の学校」を掲げて学校を立て直しました。人材の活性化や優れたリーダーシップがなければ組織は生まれ変わりません。脇田校長はどのように子供たちのやる気を引き出したのか。なぜ教師たちの行動が変わったのか。この連載では、特別活動を基軸にした脇田校長の学校づくりを追跡していきます。
目次
学級会の名人に誘われたすすきの
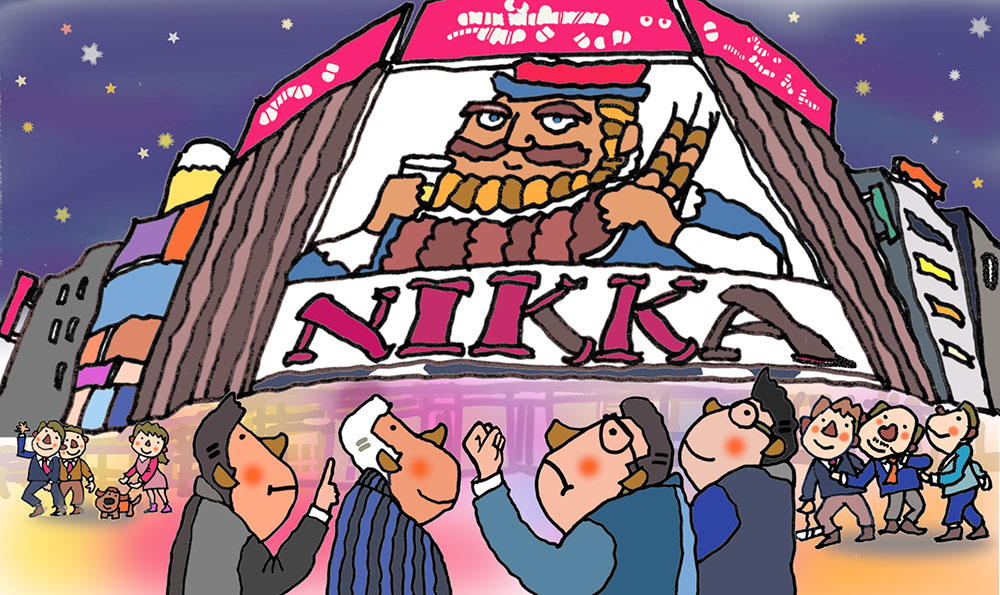
いつから特別活動に興味を持ったのだろう。「特活」と呼ばれている教科・領域のひとつのことだ。
教育雑誌の記者として私は、特別活動や総合的な学習の時間の実践記事を連載してきたが、教育雑誌のメインストリームは国語や算数などの教科にかかわる記事であり、私は少数派だった。取材してわかったのだが、それは学校現場でも同様らしく、小学校の教育課程に規定されている領域でありながら、特別活動や総合的な学習の時間を実践する先生から、「取り上げてもらってうれしい」という声を聞いたくらいである。この連載を始めるにあたって、なぜ特別活動に注目したのかを思い返してみた。
あのときが始まりだったと思う。
2008年10月17日のことだ。その晩、私は指定された二次会の居酒屋に向かって札幌の繁華街を足早に歩いていた。
朝、東京の羽田空港を出発するときには、日差しが強く、空気は湿気を含んでいたのに、札幌の空には秋雲がたなびき、吹く風はからっとしていた。夜ともなればちょっと肌寒かった。
札幌の繁華街といえば、すすきのである。すすきの交差点と呼ばれる交差点の東南角には、ニッカウヰスキーの大きな看板がある。大阪のグリコの看板を見れば道頓堀とわかるように、この看板もすすきのの代名詞になっている。それを目印にしながら交差点を南へと進み、何本目かの路地を西に折れる。目指す居酒屋には夜8時前に着いた。もう店名も店構えも忘れてしまったが、店内のことだけははっきり憶えている。
その居酒屋の店内は旗竿地のようになっていた。玄関からまっすぐにカウンター席が10席ほど並び、その通路の先には小上がりがひとつある。そして、その小上がりの周囲にはテーブル席が広がるという、一風変わったレイアウトになっていた。チェーン店ならこんなつくりにはしないだろうから、地元の有名店かもしれない。
通路に突っ立っている私に、小上がりのほうから「おーい、こっちだ」と声がかかる。そこに座る客がいかにも上機嫌な感じで手を振った。文部科学省教科調査官の杉田洋(ひろし)、宗像市教育委員会指導主事の脇田哲郎(てつろう)、福岡県の小学校教諭の大久保利詔(としのり)の3人が笑顔で迎えてくれた。
その日はずっと札幌市内の小学校で校長の取材をしていたのだが、偶然にも同校で全国特別活動研究協議大会北海道大会が開かれていた。学校玄関ホールは吹き抜けで、教室は扉のないオープンスペースになっているような開放的な小学校であったから、全国大会の会場としては申し分ない。その小学校には、全国から教員や学校管理職などが参加し、盛況を呈していた。
取材の途中で校内を見せてもらうことになり、教室を回ることになった。そのとき、急に声をかけられた。この大会に参加していた大久保の人懐っこい笑顔が目に入った。そもそも私はこの学校で研究協議大会が開催されることを知らないし、大久保はなぜ私がこの学校にいるのかを知らない。
私が大久保に、たまたまこの学校の校長を取材するために来たことを告げると、大久保はこの奇遇を喜び、「懇親会のあとは脇田先生と二次会になりますから、よかったら合流しませんか」と誘ってくれた。研究協議大会の終了後には、たいてい懇親会が催される。そのあとに会おうというのである。
大久保は特別活動の実践家として「福岡県に大久保あり」と、その名を知られている教師だった。地元の大学ではなく、わざわざ北海道教育大学を選んで進学し、応援団部に所属していたと聞いた。バンカラな雰囲気だったが、フォルクスワーゲンのライトブルーのゴルフを愛用するような都会的なところを併せ持っていた。
特別活動とは、国語や算数と並ぶ教科・領域のひとつで、学級会、運動会や修学旅行といった集団活動を通して自尊感情や人間関係力などを育む教育活動をいう。特別活動の基本は学級会における話し合い活動である。自分たちのクラスで何をしたいのか、自分たちのクラスをどうつくりあげていくか、自分たちのクラスの問題点は何かといったことを話し合うのだ。
子供たちは、意見を理由つきで述べるのは当たり前のこととして、提案された課題の解決に向かって意見を出すという目標到達的な思考だけでなく、意見が議題の提案理由や学級目標に適合するかという俯瞰的な思考もしなければならない。なかなかレベルの高い話し合い活動がそこでは求められる。
私は、大久保学級の学級会の授業を何度か見させてもらったことがある。そこで繰り広げられる子供たちの話し合う姿にはいつも驚かされた。
例えば、あまり意見を言わない子がいざ発言しようとすると、たいてい声が小さくなるものだ。そんなときには、「静かに、しーっ」「頑張れ」とクラスのざわつきを抑え、その子を応援するつぶやきが起こる。
また、大久保は子供たちに、議題の提案理由に沿うだけでなく、そこに過去の自分の体験を加えて話すことを指導していたから、子供たちはそれを試みようとする。しかし、それがうまくできずに自分の発言がしどろもどろになったりすると、「〇〇くんの言いたかったことを代わりに言います」とすかさずフォローする子が現れる。
大久保が受け持つクラスには、必ず支え合う子供の姿が見られた。どうすれば、このような子供たちに育つのだろうか。こんな学級をつくる教師はなかなかいない。
そんな大久保が師と仰いでいたのが、杉田、脇田のふたりである。このふたりもまた特別活動の分野で知らない人はいなかった。当時、杉田は文部科学省が定める学習指導要領をとりまとめる教科調査官であり、脇田は学習指導要領作成協力者のひとりであったからである。
だから、杉田や脇田が誘えば、いつも二次会には多くの人が詰めかけていた。しかし、この晩は少数であったから、私はちょっと驚いた。
遠足や運動会がなかったらどうする?

小上がりは畳2畳もなかったと思う。戸はなく、衝立のような板壁に三方を囲まれた座敷で、カウンター席を眺めながら飲む格好になる。
私が端に座ろうとすると、すかさず杉田と脇田が席を詰めてくれ、脇田が自分と大久保の間に座るように促した。座るとき、テーブル下で足が何かに触れる。見れば、空き瓶が2本転がっているではないか。北海道生まれの焼酎の鍛高譚(たんたかたん)だった。
座るやいなや私は杉田から話しかけられた。
「そういえば、『希望の会』の記事を書いてくれたんだよな」
「昨年ですね。福岡で行われた『希望の会』の様子を紹介させていただきました」
「希望の会」は、正式名称を「特別活動 希望の会」といい、杉田の呼びかけによって結成された特別活動の実践者や研究者の全国的なネットワークである。そこでは、学習指導要領や学習指導要領解説に反映させることを念頭に置いたシンポジウムや研究会などが定期的に行われていた。脇田はその福岡地区のまとめ役で、大久保は脇田を補佐していた。
杉田と大久保は、帆立の刺身などをつまみに鍛高譚の水割りを、脇田はそのお湯割りを飲んでいた。店内は客で混雑し、騒がしかったが、小上がりでの会話の声は聞きやすかった。
杉田は「サラブレッド」と呼ばれていた。杉田の父親も特別活動の実践家として知られた教師で、学習指導要領作成協力者として活躍された。親子2代にわたって学習指導要領にかかわったことになる。背が高くスマートさを感じさせる容貌が語りかける、機知とユーモアに溢れた講演は人気が高かった。
教科調査官にざっくばらんに話を聞けるチャンスはなかなかない。私は思い切って杉田に、「特別活動の魅力はどこにあるんでしょうか」と質問すると、杉田は即座に答えた。
「小学校のときの思い出といったら何を思い浮かべる? 修学旅行や運動会と答える人が多いよね、きっと。もし文部科学省から『学校行事を一切してはいけない』という通達が出されたら、どうするかと、ふと思うときがあるんだよ。そうしたら、学校には、入学式も卒業式もない、始業式も終業式もない、運動会も遠足もなくなってしまう。学校は授業を受けにくるだけの場所になる。それで本当にいいのならば、そうしてみたらいいと思う。そんな楽しいことがひとつもない学校に子供たちは喜んで来るだろうか」
立て板に水のごとく言い終わると、柔和な表情を浮かべた杉田は店内を見つめて焼酎のグラスを傾けた。別に私にその思考実験の返事を求めるふうもなかったが、そんな学校がつまらないことだけは私にも想像できた。
杉田に代わって、その結末を答えてくれたのは、脇田だった。鹿児島生まれで、日焼けした顔に見事な白髪を蓄えた精悍な感じのする人はこう語った。
「もしそうなったら、学校から多くの感動がなくなりますよ。習ったことがわかるようになったことやできるようになったことを味わう感動、学校生活のなかで友達から親切にしてもらってうれしかったときの感動、友達から感謝されたときの感動、額に汗して何かをやり遂げたときの感動、そういう感動を子供たちは味わうことも、それを友達と共有することもできない。大久保さん、できる子だけがかわいい?」
「いや、できる子もできない子も関係なくかわいい」
「そうやろ。そういう心の底から沸き起こってくる感動をどんな子供にも与えるのが教師の仕事、学校の仕事だよ」
運動会や遠足のない学校を考える──。まさか後年、杉田が言うような事態が現実のものになろうとは思いもしなかった。そう、2020年初頭に起きた新型コロナウイルス感染症の流行である。感染症の流行の前後で学校の状況は一変した。その年度末の多くの小学校では、下級生も保護者も来賓もいない、規模を縮小した6年生だけの卒業式が行われた。全国一斉の休業措置がとられると、春の遠足や5月の運動会を中止する学校が現れた。
その後、自治体の教育委員会の判断に従い、感染症の流行を理由に学校行事を一律中止にする学校と、感染症の拡大防止に対処しつつ、実行可能な学校行事を模索する学校とに大きく分かれた。味気ない姿が露わになった学校には、脇田が指摘したように、子供たちの歓声や感動が消えた。そして、子供たちが学校に集まって学習する意味が問われた。

