「授業」と「授業の外」の充実(上) ー目の先のことより、その先のことをー【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第48回】

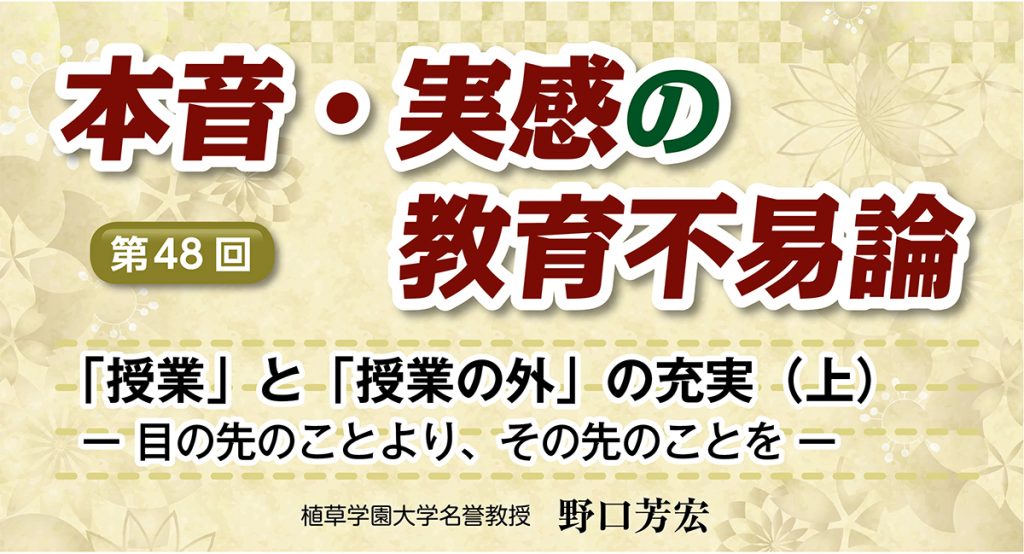
教育界の重鎮である野口芳宏先生が60年以上の実践から不変の教育論を多種のテーマで綴ります。連載の第48回は、【「授業」と「授業の外」の充実(上) ー目の先のことより、その先のことをー】です。

執筆
野口芳宏(のぐちよしひろ)
植草学園大学名誉教授。
1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、60年余りにわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVDなど多数。
目次
1 授業の「脱線」の功罪
大方の古いことは忘れてしまっているのだが、格別重要な訳ではないのに心に残っていてふとした拍子に繰り返し思い出されてくる些事がある。なぜなのかは分からない。恐らくそのことが自分のフィーリングや考え方や性格、性分というようなものと何らかの共通点があるからなのだろう。
高校生の折に、隣のクラスの担任が若くて、いつもにこやかな表情をしていたので少し羨(うらや)ましくなり、「若い先生でいいなあ」と言ったことがあった。ところが、そのクラスの友達は「そうでもないよ」と否定した。理由を問うと、「いつでも、すぐに授業に入るんだよ。授業の話しかしないんだよ。だから、何だか面白くないんだよなあ」と答えたのだった。思いがけない答えだったが、「そういう評価はあるかもしれないなあ」と妙に共感したような気分だった。私の共感した部分は、担任の人柄に対してではなく、「授業の話しかしない」のでは「何だか面白くないんだよなあ」という友達の受けとめ方に対してだった。
あれから70年近くも経っているというのに、あの場面がひょいと浮かんでくるのだ。思い浮かんでくると、懐かしさと同時にいつでも「それはそうだろうなあ。無理もないなあ」という思いになる。「授業」が先生の本務なのだから、「授業の話しかしない」でいい訳なのだが、この問題は案外簡単に考えてはいけないことなのかもしれないと思うようになった。
授業中に「脱線」と称して、先生が授業の本筋から離れた方向に話を進めてしまうことがある。その場合、脱線してしまった話の方が面白くて、心がそっちの方に靡いてしまうということもよくあった。しばしば脱線する先生の方が授業の人気が高かったりもした。脱線した話が低俗、野卑であれば真面目な生徒は怒り出すかもしれないが、反対に機智に富み、それなりの品のあるユーモアがあったりする場合には生徒も楽しめる。
脱線しても生徒や学生や子供からそれなりの満足と喜びを以て迎えられるような教師は、なかなかの力の持ち主だと言えよう。雑学などという言葉もあるが、本務外の多くのことについても話せるというのは、その教師が人間としてある種の厚みや重みを備えている証拠とも言える。

2 雨天時の「お話」の楽しみ
私が小学生の頃には体育館はなかった。体育館の代わりに講堂があった。講堂というのは「儀式または訓話・講演などをするための建物または部屋」である。そこで体操の授業をすることもあったが、それは本来の姿ではないので、雨が降れば体操の授業は中止になるのが普通だった。
そんな折には担任の先生はよく「お話」をしてくれたものだった。「お話」は、昔話だったり、先生が子供の頃の話だったり、先生の家の話だったりしたが、そのどれもが、その先生からしか聞けない話だったので面白く、体操のある日に雨が降るのを楽しみにしている子供もいたくらいだった。昔の先生は、「授業以外の話」をいっぱい知っていたし、話してもくれるゆとりもあった。
そして「その先生からしか聞けない話」には、その先生の人柄や好みや苦手のことや食べ物の好き嫌いなどが滲み出ていた。そんなことから子供たちは先生への親しみや気安さを育てもしたものだった。
私の子供の頃というのは4年生までが戦時下であり、4年生の8月以降は敗戦下ということになる。いずれも、日本が最も苦難の中にあった暗い時代と言えるだろう。
だが、子供たちも暗かったかというと、必ずしもそうとばかりは言えない。それなりの楽しみも、笑いも、競争も、勝負も、努力も、幸せもその時なりにあったのだ。子供の世界は、いつの時代でも子供の世界として健康に存在していたのである。
戦時下の親も、先生も、親であり続けようとしていたし、先生であり続けようとしていたと思う。優しさもあり、厳しさもあり、温かさもあり、冷たさもあった。今と大きく変わる訳ではない。だから、その頃のことを思い出してみると、今の子供に負けない楽しみも喜びもあった時代だったとさえ思われるのだ。

