リレー連載「一枚画像道徳」のススメ #26 祇園の夜桜|中條佳記先生(京都府公立小学校)

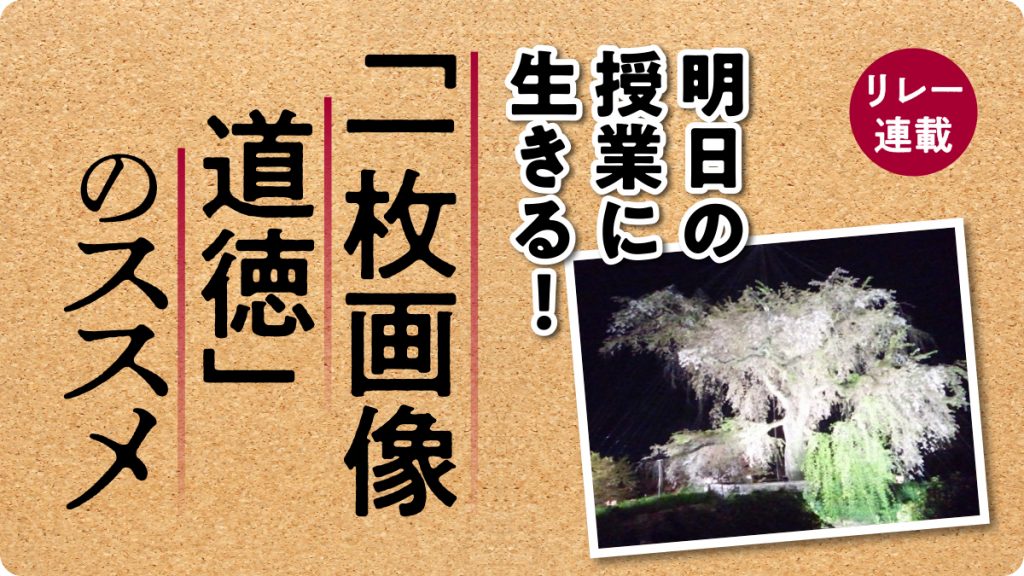
子供たちに1枚の画像を提示することから始まる15分程度の道徳授業をつくり、そのユニットをカリキュラム・マネジメントのハブとして機能させ、教科横断的な学びを促す……。そうした「一枚画像道徳」実践について、具体的な展開例を示しつつ提案する毎週公開のリレー連載。今回は中條佳記先生のご執筆でお届けします。
執筆/京都府京都市立百々小学校教員・中條佳記
編集委員/北海道函館市立万年橋小学校教諭・藤原友和
目次
ごあいさつ
みなさん、こんにちは。
京都市で小学校の教員をしております、中條佳記(なかじょう よしのり)と申します。
奈良、愛知での教員生活を経て、京都での教員生活がスタートしています。新たな先生方と出会い、学級の子供たちと出会い、保護者と出会い、日々、精進しております。
さて、コロナ禍で激減していた観光客が京都に戻りつつあります。
京都市内で観光地と訊ねられると、みなさんはどこが浮かびますか。寺社仏閣や城の名がいくつも出てくることでしょう。その中の一つ、東山区にあります八坂神社(やさかじんじゃ)。京都市民の誰もが一度は訪れたことがある場所です。
その東奥に、敷地面積86,641平方メートル、1886(明治19)年12月25日に設置された円山公園(まるやまこうえん)があります。
今回は、その円山公園内の中央部にあります通称「祇園の夜桜」こと、一重白彼岸枝垂桜(ひとえしろひがんしだれざくら)を題材写真に選び、道徳授業化しました。
1 「一枚画像道徳」の授業実践例
対象:小学5年
主題名:大切に守られ、愛されてきた桜について考えよう
内容項目:C-17 郷土の伝統と文化の尊重、郷土を愛する態度
「お花見をしたことある人?」と訊ねると、子供たちの手が挙がりませんでした。コロナの影響で、花見ができなかった、または忘れているのでしょうか。
しかし数名は手が挙がり、訊ねてみると「おじいちゃんおばあちゃんと行った」「家族で見に行った」などと答えます。
続いて、「お花見の花は?」と訊くと、「桜」と即答です。
そこで、以下の写真を提示し、以下の質問をします。
『これは、枝垂れ桜という木の写真です。さて、どこの桜でしょうか。近くの人と相談してもよいですよ』

写真を見せると、子供たちから感想や予想の声が上がりました。
子供の声
「めちゃきれい。」
「光ってて、白く見える。」
「こんな桜、見たことない。」
「これ、桜なん?」
「どこやろ~」
「あれ? 京都ちゃうか?」
「あっ、見に行ったことあるかも。」
『この写真は、京都の八坂神社の隣にある円山公園の枝垂れ桜です。4月です。』
と説明すると、子供たちからは、「そうなんやぁ!」「見てみたい!」「行ってみたい!」という声が上がりました。
発問1 この桜が枯れずに毎年咲き続けるのはどうしてでしょうか?
「桜の生命力」
「もともと強い桜だから」
「誰かがお世話をしているから」
「観光客がマナーを守っているから」
など、さまざまな考えが子供たちから出てきました。
『じつはこの桜を昔から守っている人がいて、いつも世話をしてくれているんだよ』と伝えると、
「あ~なるほど」「やっぱり、そうやったんやぁ」という声が上がりました。
発問2 この桜はもともとここに咲いていたのでしょうか?
この問いに対する答えは、「いいえ」が正解です。
じつはこの桜は、2代目です。
『それでは、どうして今もなおこの枝垂れ桜は咲き続け、【祇園の夜桜】とまで言われるようになったのか、について紹介します』と子供たちに伝え、歴史を説明します。
初代は、明治19年~昭和22年。
樹齢200年だった。
昭和22年に枯れてしまったが、事前に初代の種子を育てていた人がいた。
それは第15代桜守佐野藤右衛門氏。その手によって昭和3年に採取された種子が、畑で育成されていた。そして育った苗を、枯れてしまった初代の代わりに、昭和24年に植える。
それから現在まで、およそ70年以上が経つ。
最後に、『これからもこの桜が咲き続けるために、私たちは何ができるでしょうか』と問いかけ、グループディスカッションを促しました。
そうすると、子供たちなりの考えが出てきて、自分事としての話合いにつながっていきました。グループごとに意見を発表し、交流していきました。

