リレー連載「一枚画像道徳」のススメ #8 「一枚画像道徳」を読み解く|郡司竜平先生(名寄市立大学)

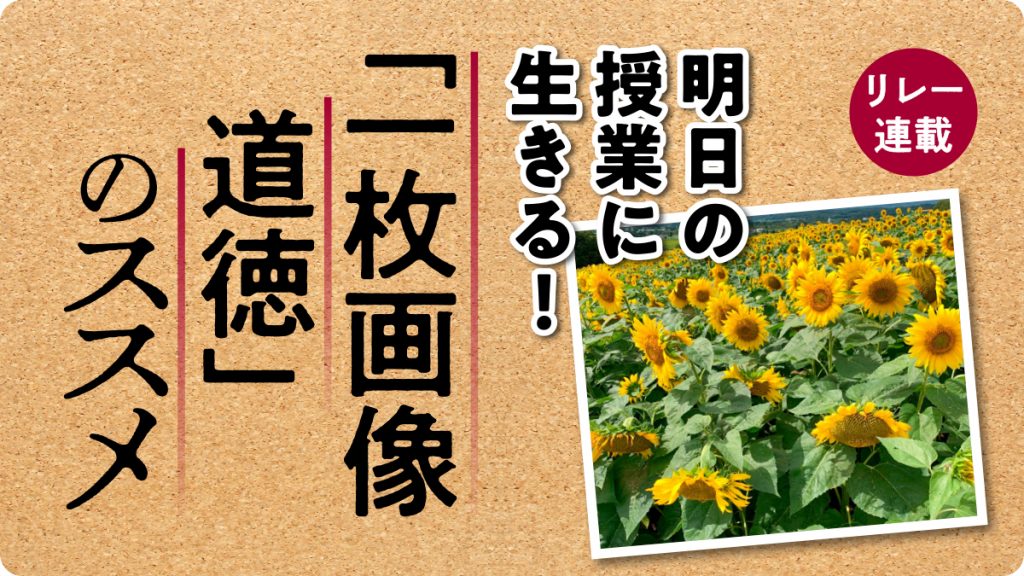
子供たちに1枚の画像を提示することから始まる15分程度の道徳授業をつくり、そのユニットをカリキュラム・マネジメントのハブとして機能させ、教科横断的な学びを促していく……。そうした「一枚画像道徳」実践について、具体的な展開例を示しつつ提案する毎週公開のリレー連載。第8回は、郡司竜平先生のご執筆でお届けします。
執筆/名寄市立大学保健福祉学部社会保育学科准教授・郡司竜平
編集委員/北海道函館市立万年橋小学校教諭・藤原友和
目次
はじめに
みなさん、こんにちは。
北海道・名寄市で大学の教員をしております、郡司竜平と申します。藤原先生と同世代でそろそろ中堅からベテランと言われる年齢に近づいてきた今春、特別支援学校教員から大学へきました。
特別支援教育の分野で長い時間を過ごしてきた私ですので、今回の連載メンバーからみると単位時間における道徳の授業づくりの専門性は決して高くはありません。
さて、そんな中で企画者の藤原先生がなぜ今回のリレー連載に私を入れたのか思案しているところであります。各先生が提案される「一枚画像」の分析についてだろうか、はたまた子供同士の関係性のことかなと思いを巡らせながら、徒然なるままに書き綴ってみようかと思います。
どんなところに着地することやらと自分でも思いますが、最後までお付き合いいただきご笑覧ください。
1 一枚画像を解釈するということ

道徳の時間に「一枚画像」を提示された子供たちはどのように「見る」のでしょうか。
連載第1回の藤原実践で提示された「一枚画像」をもとに皆さんで考えてみましょう。この実践では対象が6年生です。
この一枚画像を見た子供たちへの発問1「何か違和感はありませんか」が投げかけられると、
●なんか小さい
●乗っていても楽しくなさそう
●屋根がついている
●ゴンドラになっていない
●乗る人が横に並んでいる
と次々に自分たちの気付き、「?」を挙げてきます。そして、これはただ自分たちの気付きを挙げてきているのではないのです。この時点で既有の知識との比較がいくつか入っています。どうやらただ「見て」いるだけではなさそうです。
●なんか小さい →通常の観覧車の大きさとの比較
●乗っていても楽しくなさそう →通常の観覧車の楽しさとの比較
●ゴンドラになっていない →通常のゴンドラの形状との比較
発問1に対して、自分たちで画像の中の事象を「見て」解釈していると言ってもいいかもしれません。
では、同じ「一枚画像」を1年生に提示した場合はどんな反応が予想されるでしょうか(もちろん、発問の内容も変わるかとは思いますが)。
五つ考えてみてください。例えば、
●観覧車!
●人が5人いる
●観覧車(ゴンドラ)は全部で8こ
●黄色、ピンク、青、エメラルドグリーンの色がある
●観覧車(ゴンドラ)は同じ方向? を向いている
低学年を担当されている先生方、いかがでしょうか。
同じ「一枚画像」である「観覧車」を提示しても、発達段階の違いで、私一人が少し考えただけでも出てくる反応がこれだけ違うと予想することができます。いま実際に担当されている先生方であればもっともっといろいろな反応が容易に予想できるでしょう。
1年生の段階ですと、既有の知識と言ってもまだまだそれほど多くは持ち合わせていないでしょうし、さらにそれらと目の前の画像を比較し解釈するということはかなり難しいでしょう。発達段階から考えると、「一枚画像」の中にある具体物を挙げることが妥当でしょうか。
では、この違いをどのように考えればよいのでしょうか。
「発達段階が違うから」なのは当然なのですが、もう少し丁寧に考えてみましょう。
例えば、「一枚画像」をメディアとしてとらえると次のように考えることができるかもしれません。
中橋(2021)ⅰによるとメディア(ここでは一枚画像を指すとします)を介した記号化と解読には二つの側面があるとし、一つは「情報の記号化と解読」であり、もう一つは「意味の記号化・解読」です。
一枚の画像でつくる道徳の授業は、そこで用いる画像をメールに添付し、文字どおり「情報」として送り届けるだけではありません。
ですから、「情報の記号化と解読」ではなく、「意味の記号化・解読」にあたると考えられます。意味の記号化・解読では、同じ言語体系を習得しているだけではうまく意思疎通することはできません。
先生も子供たちもただ日本語を理解しているだけでは意思疎通できない、一枚の画像を提示してもその解読は難しいということです。
「互いの社会的・文化的な背景、価値観、既有の知識なども含め同じ記号体系をもっている時に、そこで編集・構成されたものを解読し、読解・解釈できる」ⅱ ようになるのです。
藤原先生は連載を始めるにあたり、1枚の画像でつくる道徳の授業を「子供たちの身の回りや学校内、地域にあるものなど、広く対象となる画像素材を集めて、道徳の授業に活用していこう」としています。
この「子供たちの身の回りや学校内、地域にあるもの」が先生たちと子供たちの「同じ記号体系をもっている」ことになるわけです。
1年生ですとまさしく「身の回り」が同じ記号体系になるでしょうし、6年生であれば「学校内、地域にあるもの」までを含めたところが同じ記号体系になるでしょう。少なくとも同じ地域に住み、暮らすことで「社会的・文化的な背景」を理解することができるかと思いますし、その地域で生まれ育った子供たちの「価値観」の一端を理解することができるかと思います。その前提条件がないと「一枚画像道徳」の授業は機能しないのではないかと考えます。
これを藤原(2022)ⅲ はその著書の中で以下のようにわかりやすく説明しています。
「教科書に掲載されるような偉人の伝記はあまりにも立派すぎたり、国を挙げた大事業ではスケールが大きすぎたりして、自分事として考えることは難しい場合もあります」(下線は郡司)。
そして、
「校区にある橋をかけた人達の協働やそこにこめられた願いについて考えること、馴染み深い公園が元々はどのような場所だったのか知ることには、子供たちも興味を持ちやすい」
としています。
つまり、
「同じ記号体系」を持つことで、先生が提示した「一枚画像」を子供たちが「解読し、読解・解釈できる」
ようになるのです。
「一枚画像道徳」が成立することになるのです。
ここに藤原先生たちが「地域教材における道徳」にこだわって取り組んできた一端を見ることができるように思います。
ただし、一つ注意が必要そうです。
それは、やはり目の前の子供たちがどのような「社会的・文化的な背景、価値観、既有の知識」をもっているのかを詳細に把握することです。「同じ記号体系」を持つことが大事です。
1年生には1年生の、6年生には6年生の記号体系があり、さらにそれはもちろん全国同一ではないわけです。
暮らす地域によって「社会的・文化的な背景」は異なるでしょうし、地域として受け継がれてきた「価値観」もそれぞれ異なるでしょう。先生たちがどんなに「これだ!!」と思い撮ってきた渾身の一枚画像であっても、子供たちが同じ記号体系を持ち合わせていなければ学びとして機能しないのです。

私が住む名寄市で今がまさに旬のひまわりの写真を撮り(名寄サンピラーパークにて、2022年8月22日 郡司撮影)、函館の藤原先生が担当する学級の子供たちに「一枚画像」として提示しても、それは学びとして機能する可能性は低く、ただ、「名寄のひまわりがきれい」と解読されるだけなのです。
さらに、例えばこの一枚を名寄市内の子供たちに私が提示したとしても「同じ記号体系」を持ち合わせていませんので、これもまた道徳の学びとしては機能しないでしょう。

