ボトムアップのよさと限界【妹尾昌俊の「半径3mからの“働き方改革”」第6回】
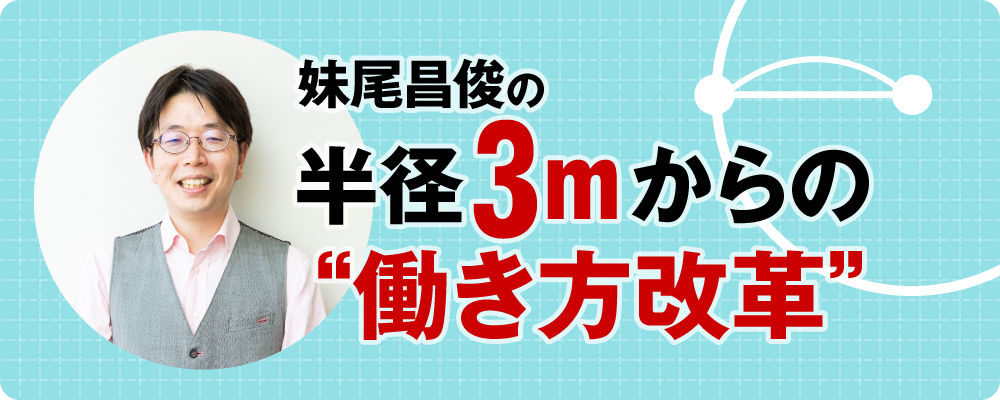
学校の“働き方改革”進んでいますか? 変えなきゃいけないとはわかっていても、なかなか変われないのが学校という組織。だからこそ、教員一人ひとりのちょっとした意識づけ、習慣づけが大事になります。この連載では、中教審・働き方改革特別部会委員などを務めた妹尾昌俊さんが、「半径3m」の範囲からできる“働き方改革”のポイントを解説します。
執筆/教育研究家・合同会社ライフ&ワーク代表 妹尾昌俊
目次
夏休み中はベルトコンベアを止める
この記事がアップされるのは7月頃だろうか。ちょっと気が早いかもしれないが、そろそろ夏休みが来るのが楽しみ、という子どもたちもいることだろう。そして、それは、先生たちもかもしれない。子どもとちがって、夏期休業中=休日ではないとはいえ、いつもよりは多少はゆとりがある。働き方改革の関連で言えば、夏休み中は、2学期以降あるいは次年度に向けて、改善策を練る一大チャンスである。
「学校はベルトコンベアみたいだ」。ある副校長から聞いた言葉だが、学校では行事や単元について、ひとつが終わったと思うと、またすぐ次のものがやってくるので、どうしても目の前のことで一杯一杯になりやすい。それに、多感な子どもたちを相手にしていて、予測不能なことも多々起きる。次々起きることに順次対応となりやすく、少し立ち止まって見つめ直したり、改善策を練ったりする機会は少ない。
ある程度は仕方ないのだが、これが、学校の多忙をさらに悪化させるという悪循環にもなっている。かつてトヨタ自動車が世界中を驚かせたことがある。それは、工場の一従業員にベルトコンベアをストップさせる権限を与えていたことだ。問題があれば、それを一番わかっている人がストップをかけて、改善を協議する。こののち、“kaizen”は世界共通語にまでなった。
教職員の参画、ボトムアップが大切な理由
さて、学校はどうだろうか。夏休み中にベルトコンベアを止めて、じっくり考え、行動に移せているだろうか。
具体的にはどうするか。校内研修などの時間を活用して、働き方改革や業務改善に向けたアイデアを出し合うワークショップを行うこともひとつだ。保護者や地域の方も教職員に交ざって、熟議するのもよい(感染症対策は講じながら)。
かなり多くの時間がかかっている業務やストレスが高いと感じることがあれば、それは改善のチャンスだ。しかも、そう感じているのはおそらくあなた一人だけではない。一人で仕事の仕方を工夫するだけでは限界もあるので、多くの関係者が集まって、しっかり議論することには意味がある。
それに、教師という職業の人の中には、自分が教えるということを日常にしているせいか、人から教わる、あるいは押しつけられると感じることを極度に嫌がる人もいる。何か学校として、あるいは教育委員会等として改善策を練るとしても、自分も参画して決めたことだという実感があるかどうかで、教師のやる気は違ってくる。
そこで、校長や教頭の役割として大事なのは、改善に向けたアイデアや今の働き方についての本音や悩みを出せる場をつくることだ。例えば、中学校や高校であれば、部活動を今の規模を維持するのか、できるのか、また、顧問をしたい人もいれば、したくない人もいること等について話し合う場を設けることが第一歩だ。「部活動ガイドラインがあるので、それを守りましょうね」などとトップダウン的に伝えるだけでは、なかなか浸透しないし、実行に移らない。
ボトムアップの3つの限界
このような教職員の参画、ボトムアップのよさとは裏腹に、限界もある。
第一に、なぜこういう話し合いをする必要があるのかという意味付け、価値付けができていないと、ボトムアップの場すら、負担感の重いものとなってしまう。本連載の第1回に、「Why働き方改革」というところをしっかり理解、共有していく必要があると述べたこととも重なる話である。
第二に、ボトムアップだけでは小粒な改善アイデアとなる可能性もある。前述のとおり、多くの教職員は目の前のことはよく見ているが、学校全体や学校経営についての意識が必ずしも高いわけではない。いわば、現場に根ざした“虫の目”はあるが、全体を俯瞰できる“鳥の目”にはなっていないこともある。こうすると、時間を要している大きなものにメスを入れようといった全体を見た発想にはなりにくい。
もちろん、身近なところから改善は進めていけるとよいのだが、小粒な改善だけで満足されても困る。なぜなら、それでは過労死ライン超えほどの超・長時間労働の実態を解消できないからだ。
校長や教頭の役割としては、次のことを大切にしてほしい。
●教職員の目線を上げること
●もっとチャレンジできることはないか問いかけること
●大きなものの改善・改革は時間を要するだろうが、確実に一歩一歩やっていこうと呼びかけること
第三に、アイデアを出したきりになってしまうことがある。ワークショップなどをすると、当日はそれなりに盛り上がって高揚感があるのだが、それきり。日常の目の前のことで手一杯となる中で、つい後回しになる、忘れられてしまうということがよく起こる。
そのため、校長や教頭としてやらないといけないことが2つある。ひとつは、たくさん出たアイデアの中から、優先度高く確実に実行したいことを決めることまでファシリテートすること。もうひとつは、実行すると決めたことが確実に進むよう、責任者を決めたり、工程表に落としたり、定期的に進捗を確認する場を設けたりすることだ。
ボトムアップのよさと限界を踏まえながら、実効性のある改善、改革を進める一歩に、夏休みを有効活用してほしい。
『総合教育技術』2018年9月号に加筆

野村総合研究所を経て独立。教職員向け研修などを手がけ、中教審・働き方改革特別部会委員などを務めた。主な著書に『変わる学校、変わらない学校』『学校をおもしろくする思考法』(以上、学事出版)、『こうすれば、学校は変わる! 「忙しいのは当たり前」への挑戦』(教育開発研究所)、最新著書に『教師と学校の失敗学 なぜ変化に対応できないのか』(PHP研究所)がある。





