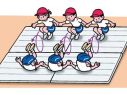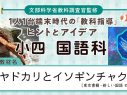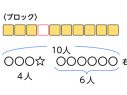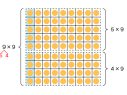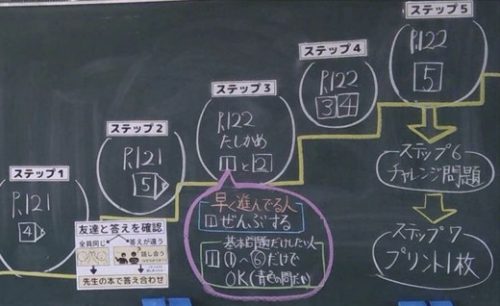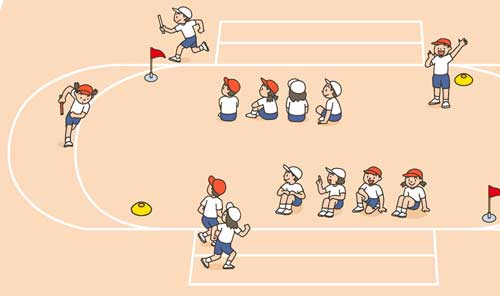小1算数「ふえるといくつ」指導アイデア(3/8時)《増加の場合の加法の計算》

執筆/埼玉県さいたま市立大砂土小学校教諭・播元和貴
監修/文部科学省教科調査官・笠井健一、浦和大学教授・矢部一夫
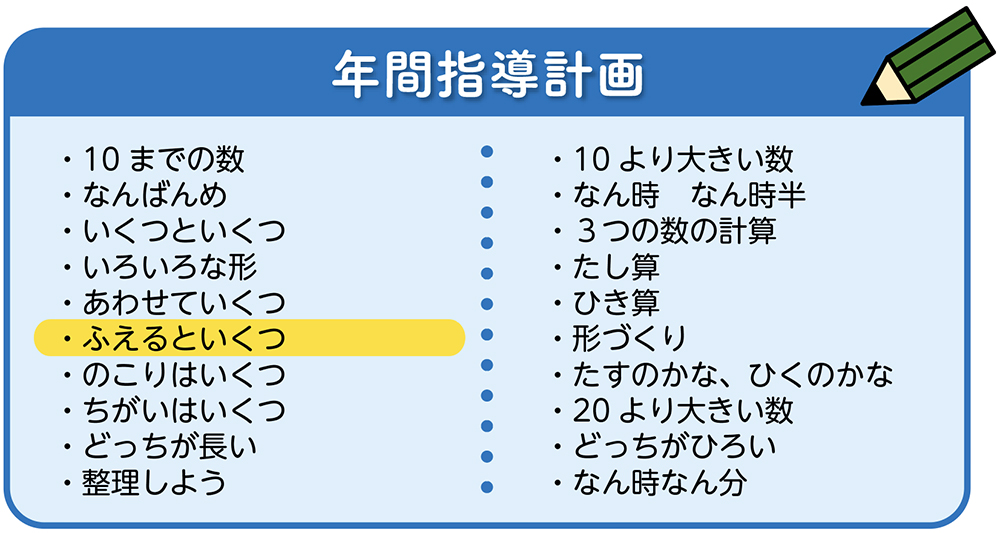
目次
単元の展開
第1時 合併の場合の数量の関係に着目し、加法の意味や式の表し方を考える。
▼
第2時 合併の場面を加法の式に表し、答えを求める。
▼
第3時(本時)増加の場合の数量の関係に着目し、加法の意味や式の表し方、計算のしかたを考える。
▼
第4時 増加の場面を加法の式に表し、答えを求める。和が10以内の加法の計算。文章問題を通した加法の意味理解。
▼
第5時 計算カードを使った、和が10以内の加法計算の練習。
▼
第6時 0を含む場面で、数量の関係に着目し、加法の意味や式の表し方を考える。
▼
第7時 お話づくりで、式の読み取りに着目して、加法の意味を考える。
▼
第8時 学習内容の習熟・定着。
本時のねらい(増加の場面)
増加の場合の数量の関係に着目し、加法の意味や式の表し方、計算のしかたを考える。
評価規準
増加の場面を加法として捉え、ブロック操作や加法の式に表して説明することができる。【思考・判断・表現】
増加の場合について、加法の意味を理解し、加法の式に表すことができる。【知識・技能】
本時の展開

えを みて おはなしを つくりましょう。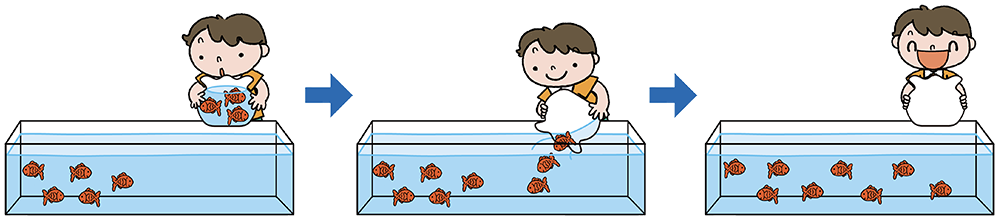
この絵は、何をしているところですか。
金魚を3匹入れています。
全部で8匹になりました。
5匹いた水槽に、後から3匹金魚を入れたのだと思います。
前の時間の絵と、どんなところが違いますか。
前の時間は、2人が一緒に水槽に入れたけれど、今日ははじめに5匹いたところに3匹付け足しています。全部で8匹になりました。
前の時間は、2人で合わせていたけれど、今日は一人の子が金魚を入れているところが違います。
なるほど。前の時間では金魚を合わせていたけれど、今日は金魚を増やしているのですね。どのようなお話がつくれますか。
「5匹の金魚と、3匹の金魚を合わせると、なん匹になりましたか」かな。
「合わせる」というのはちょっと違うと思います。「はじめ、水槽に金魚が5匹いました。そこに金魚を3匹増やしました。全部でなん匹になりましたか」だと思います。
確かに水槽の中では合わせた金魚の数になっているけれど、元いた金魚に3匹合わせてもいますね。では、お話に合わせてブロックを動かして、考えてみましょう。

お話に合わせてブロックを動かしながら、式を考えよう。
見通し
絵を見ると数が増えているから、たし算じゃないかな。
算数ブロックを使って考えてみよう。
ブロックを動かすと二つの数が合わさると思うので、たし算じゃないかな。
自力解決の様子
A つまずいている子
ブロック操作から答えは出せるけれど、なぜ、たし算なのか説明できない。
B 素朴に解いている子
お話の通りにブロック操作をして、答えを求められる。その操作から、加法の場面として捉え、たし算の式を書いている。
C ねらい通り解いている子
ブロックを説明しながら動かしている。また、「合わせている」「全部で」などの言葉を根拠として、問題場面をたし算の式で表している。
学び合いの計画
前時までに子供は、「5と3を合わせると8になります」「4と2を足すと全部で6です」など、合併の場面を加法の式に表し、答えを求める活動を行っています。
本時では、合併の場面と違って、「増加」という時間の経過を伴う場面を扱います。しかしながら、本時のねらいはブロックの動かし方は違うものの、ブロック操作や式に表して計算する活動を通して、「『どちらもたし算で計算すればよい』と子供が統合的に捉えられるようにすること」です。そのため、子供の考えや発言を前時までの「合併」と関連付けながら、学習を進めていくことが大切です。
具体的な活動としては、ブロック操作を伴う活動のため、近くの子供とのペア学習や1対多数の説明が効果的です。
イラスト/横井智美、やひろきよみ