係活動が活発化する「お昼のみんなから」|子供たちが前のめりになる学級経営&授業アイデア #9

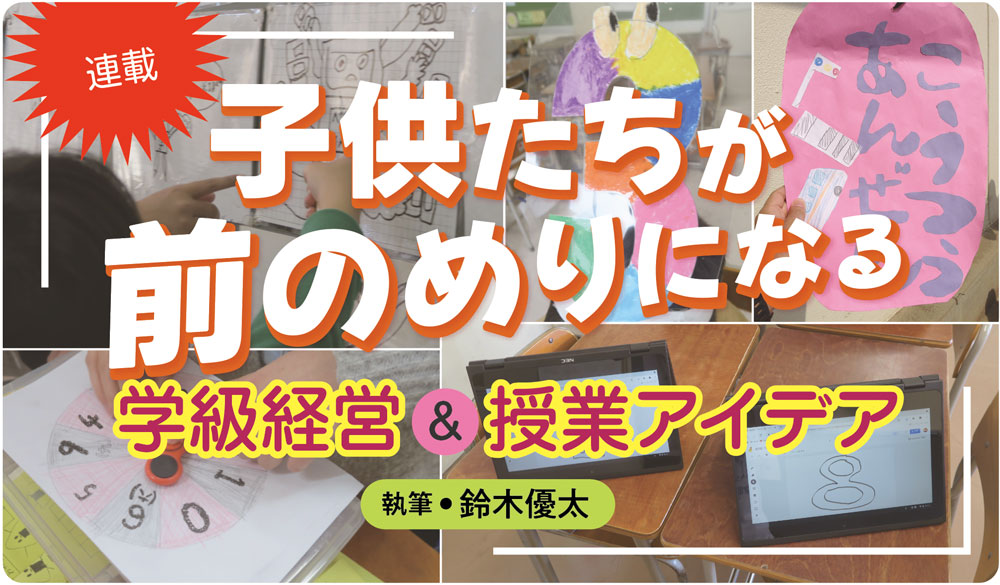
学級経営と授業改善について、アナログとデジタル、それぞれのよさを融合しながら唯一無二の実践を続ける鈴木優太先生の連載です。子供たちが熱量高く、前のめりに学習したり活動したりする学級づくりや授業のアイデアを、毎月1本紹介します。今回は、係活動が活発化する「お昼のみんなから」を取り上げます。
執筆/宮城県公立小学校教諭・鈴木優太
目次
係活動が停滞する原因
係活動、最近ちょっと停滞していませんか? 実はその原因、「声を出す場所」が足りないだけかもしれません。
朝の会や帰りの会に、「みんなから」というプログラムを取り入れている学級もあるでしょう。しかし、朝は全校朝会のために中止、帰りは職員会議があるために割愛。これでは、せっかくの係活動も盛り上がるはずがありません。
各係から発信する機会がないまま、一日一日と過ぎていくもったいない現実……。
そこで提案したいのが、「お昼のみんなから」です。
毎日の給食の時間に発信する「お昼のみんなから」

「お昼のみんなから」は、給食中の短い時間を活用して係活動の発信を促す仕組みです。給食時間は、全校行事や会議が入ることはまずありません。だから、毎日継続することが可能なのです。
発信内容は、「○○係からの発表」はもちろん、「みんなへのお願い」「お楽しみ会プロジェクトの提案」「児童会活動の連絡」など、子供たちに関わることであれば何でもかまいません。
給食の片付けが始まる10分前、子供たちが席に着いている時間帯にスタートします。例えば、13時5分がごちそうさまであれば、12時55分に開始します。
司会は日直が担当します。
【日直】みんなから!
【全員】みんなから!
発表や連絡がある児童が一斉に手を挙げ、日直がテンポよく指名します。当てられた児童とその係のメンバーは発表場所(配膳台から離れた場所)に素早く出ます。
【日直】Aさん
はい! ワクワクマンガ係です。マンガを描きました。貼っておくので見てください!
【全員】(拍手する)
【日直】Bさん
はい! ソロキャンプ係です。サバイバルクイズを出します。問題です!
【全員】デーデン!
(クイズを出題し、みんなが解答する)
【日直】Cさん
はい! ザ・お笑い係です。今からお笑いをやります。……これで終わります!
【全員】おもしろーい!
取組の成果を発表する場は、係活動のお楽しみ会「成果物発表会」だけではありません。日常の中で発信を重ねることこそが、係活動を動かすエンジンとなるのです。予定の影響を受けずに、毎日安定して実施できる「お昼のみんなから」によって、係活動は動き出します。
「短く×多く」が肝心
「お昼のみんなから」には、たった1つのルールがあります。
発表時間は「1分以内」
短いから、ダレません。例えば、お笑い係です。何をやっても、1分以内に「これで終わります」と言うだけで、温かい拍手に包まれます。多少スベっていたとしても、盛り上がった感じで終われる絶妙な時間設定です。そして、多くの係が発表できるようになります。
係活動が活発になると、希望が増えて発表が渋滞してしまうことがありますが、このルールならその問題も解消できます。続けていくと、子供たちはこの短さをうまく使いこなすようになります。最初は間延びしていた発表も、テキパキと話して「つまり!」とまとめる工夫が生まれ、要点を伝える力が自然と育っていきます。
子供が主役になって活動するための合言葉があります。
「短く×多く」
1分間ぎりぎりいっぱいまで発表する必要はないのです。わずか数秒でもOK。できれば毎日、なるべく多くの発信の打席に立つことを促します。発表がない日があってもかまわないのですが、子供たちに尋ねてみると「時間が短いから発表する気持ちになれる」のだそうです。
児童A「あと3分で『お昼のみんなから』だ」
児童B「あと1分!」
児童C「日直さん、『お昼のみんなから』だよ」
このように、「お昼のみんなから」の時間を心待ちにしながら、給食を楽しむ子たちも増えていきます。
話合い活動から生まれたアイデア
「係活動アクションプランシート」に、発表回数を事前に宣言するのがおすすめです。行ってみると、宣言回数を超えて毎日発表し出す子たちもいます。
「ミニホワイトボード係コーナー」のように、子供たちが自由に発信や交流できる環境を教室に設けることも大切です。掲示した内容を「お昼のみんなから」で、紹介することも促します。
実は、これらはすべて子供たちの話合い活動から生まれたアイデアです。
係活動の発表時間が十分に取れない。……さてどうしよう?
問題が出てきたときこそ、必要感のある話合いのチャンスです。「お昼のみんなから」も、子供たちの提案から始まりました。
発表希望が集中してしまう渋滞問題に直面したとき、「じゃあ、1分発表にしよう!」と学級のルールになりました。 タイマーで計ったこともありますし、「大体1分以内」でいいんじゃないとゆるやかにやっていたこともあります。「発表予約掲示板」を設ける案が採用となったこともありますが、「書いているより、どんどん発表したほうがよいね」とやっぱり廃止となったこともあります。
「みんなから」は帰りの会にも時間がありますが、「なるべくならお昼に発表しよう」と話し合いました。「ごちそうさまの10分前、給食を確実に食べ切れる人が発表する」――そんな小さな約束も、自分たちで決めました。
試行錯誤の連続ですが、自分たちで決めたことを守ろうとする姿に、学級がひと回りもふた回りも成長していく手応えが感じられます。
係活動が動き出す条件は、「声を出す場所」があること
「お昼のみんなから」は、そんな発信の文化を生み出す小さいけれど確かな仕掛けです。今、係活動が少し停滞していると感じたら学級システムを見直すチャンスです。
子供たちに、こう問いかけてみましょう。
「係活動、最近ちょっと停滞していませんか?」
そして、「こんな方法があるんだけどやってみない」とアイデアの種をまき、実際に行ってみるとよいでしょう。給食の10分間を活かすだけで、教室の空気は一変します。子供たちの声が日常に溢れ、前のめりな雰囲気が満ちていく。誰かが発表し、みんなが聴き、拍手が起こる。こうして、学級は1つになっていくのです。

鈴木優太(すずき・ゆうた)●宮城県公立小学校教諭。1985年宮城県生まれ。「縁太(えんた)会」を主宰する。『教室ギア56』『教室ギア55』(共に東洋館出版社)、『「日常アレンジ」大全』(明治図書出版)など、著書多数。
参照/鈴木優太『教室ギア56』(東洋館出版社)、鈴木優太『教室ギア55』(東洋館出版社)、鈴木優太『「日常アレンジ」大全』(明治図書出版)、多賀一郎監修、鈴木優太編、チーム・ロケットスタート著『学級づくり&授業づくりスキル レク&アイスブレイク』(明治図書出版)、鈴木優太編、チーム・ロケットスタート著『小学6年の学級づくり&授業づくり 12か月の仕事術』(明治図書出版)
【鈴木優太先生 連載】
・子供たちの可能性を引き出す!学級経営&授業アイデア(全12回)
・自治的な学級をつくる12か月のアイデア(全12回)
・子供同士をつなぐ1年生の特別活動(全12回)
・どの子も安心して学べる1年生の教室環境(全12回)
【鈴木優太先生 ご著書】
教室ギア56(東洋館出版社)
教室ギア55(東洋館出版社)
「日常アレンジ」大全(明治図書出版)
学級づくり&授業づくりスキル レク&アイスブレイク(明治図書出版)
小学6年の学級づくり&授業づくり 12か月の仕事術(明治図書出版)

