一緒に過ごしながら少しずつ進む-「クールダウン」の物語-|インクルーシブ教育を実現するために、今私たちができること #18

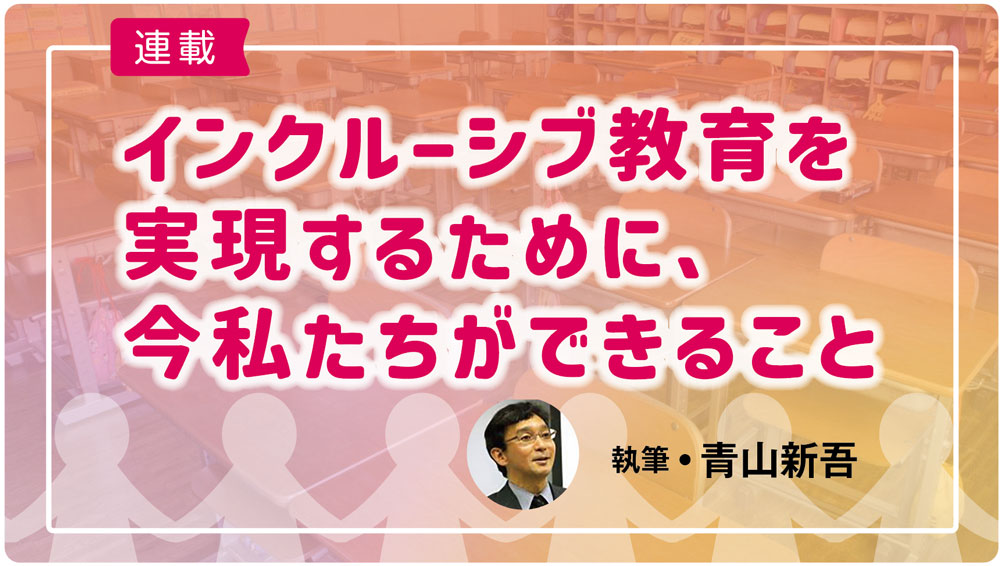
「インクルーシブ教育」を通常学級で実現するためには、どうすればよいのでしょうか? インクルーシブ教育の研究に取り組む青山新吾先生が、現場の先生方の悩みや喜びに寄り添いながら、インクルーシブ教育を実現するために学級担任ができること、すべきことについて解説します。
執筆/ノートルダム清心女子大学人間生活学部児童学科准教授・インクルーシブ教育研究センター長・青山新吾
目次
インクルーシブ教育とは何か
野口晃菜(2022年)は、「インクルーシブ教育」の対象は虐待をされている子ども、外国にルーツのある子ども、貧困状況にある子ども、性的マイノリティの子ども、障害や病気のある子ども、不登校の子どもなどのマイノリティ属性の子どもを含むすべての子どもたちであるとしています。そして、すべての子どもたちを包摂する教育を目指すプロセスがインクルーシブ教育であり、そのためには、これまでの教育システムを変えていくことが必要だとしています。本連載では、インクルーシブ教育を実現するためには、通常学級の教育が変わっていくことが求められているという前提に立っています。
今回は、インクルーシブ教育を進めていく際に必要な「一緒に過ごす中での育ち」について考えます。
ある小学校の縦割り活動で-クールダウンスペースへ向かう-
ある小学校の縦割り活動での話です。1年生から6年生までの子どもたちが、学年をまたいで活動します。その日は、班ごとに決められた教室に集まって、あそびの計画を決める時間でした。
教室にやって来た子どもたちは、持ってきたバッグなど、自分の持ち物を所定のスペースに置いてから、教室につくられたフリースペースに集まる流れになっていました。そこにやってきた3年生のこうたくん(仮名)は、持ち物を置いたものの、その場所が不適切な位置だったため、バッグから中身がこぼれ落ちてバラバラになってしまいました。
気にせずその場を離れようとするこうたくんの様子を見ていた周囲の子どもたちが、
「こうたくん、バッグから出てるよ」
「こうたくん、置く場所がちがうよ」
「こうたくん、ちゃんとしないと……」
などと声をかけたようです。
しかし、こうたくんは何も反応することなく周りからの声をスルーしました。
ちなみに、その教室には、隅っこに「クールダウンスペース」として小さなついたてとイスがおいてありました。こうたくんは、一見穏やかな表情と雰囲気でクールダウンスペースに向かい、スペースに置かれたイスに腰かけていたのです。

子ども同士のやりとりから見えること
それを見ていた6年生のある子どもが、クールダウンスペースにいるこうたくんのところに行って彼の手を取り、散乱した荷物のところへ連れていこうとしました。
こうたくんの様子が「一見」穏やかであり、周囲の子どもたちの声を聞こうとしない姿に見えたのかもしれません。そのために「クールダウンスペース」をうまく使って落ち着こうとするこうたくんではなく、周囲のことばをスルーして、「クールダウンスペース」で勝手に過ごすこうたくんに見えたのでしょうか。
こうたくんは、
「うるさい!!」
「話しかけるな、イライラする!!」
と怒り出して、ことばを荒らし出したと言います。
6年生の子どもはビックリしたことでしょう。彼は、悪気があったわけでもなく、また意地悪をしようとこうたくんに声をかけたのではない様子だったからです。彼は、こうたくんが時々自分の感情を調整しにくくなることは知っていたと思われます。でも、その場のこうたくんの雰囲気が「穏やか」であったこと、こうたくんに声をかけた周囲の子どもたちの気持ちを考えたことから、こうたくんが片付けられるようにして、集団の中に入れるようにしようとしたのだと思います。
「一緒に」過ごして進むお互いの理解
一方、こうたくんは、自分のことを知って、自分で言動を調整しようとする姿を見せていたと思われます。ここだけを見ると、こうたくん個人の成長です。しかしよく考えてみれば、こうした姿を学校の中で自然に見せているということは、これまでの周囲、他者との関係の中で同様の場面を経験しながら、学んできたことが想像できます。
今回は、こうたくんがいつも生活しているホームクラス(学級)の場面ではなく、時々活動が行われる「縦割り活動」場面でのことでした。そのため、子どもたち同士の関わりの経験量が少なく、お互いを知り合い理解していく「途上」であったと考えられます。それゆえ、お互いの理解や声のかけ方に「ズレ」が生じたことは否めないでしょう。
また、「クールダウンスペース」という場所の考え方を共通して理解していくことも大切だと考えられます。「クールダウンスペース」は、活用する人の雰囲気や姿で「正しく」使っているとか「正しくない」とかを判断するものではないからです。
しかし、こうたくんのホームクラス(学級)においても、最初は同じようなことが起きていたのではないかと考えられます。教師が一度説明したら子どもたちは「理解」するとか、教師の「指導」によって「理解」するのではなく、「一緒」に生活を重ね、様々な出来事ややりとりを重ねることで、「少しずつ」お互いに理解していくものだと思います。
もちろん、だからと言って「一緒」の場にいれば、相互に理解していけるほど簡単なものでもないはずです。
今回の場面で考えれば、
・自分で「クールダウンスペース」に向かったこうたくんの考え、行動
・一緒に活動できるよう、こうたくんが片付けて、みんなが集まっているところに来てもらおうと考えたであろう6年生の気持ち
・声をかけたのにスルーされたと思い込んでいるであろう周囲の子どもの気持ち
を整理して受け止め、お互いの関係をよい方向に向けるための教師の「指導・支援」が重要です。
対立軸を強調して「分断」を強めるのではなく、「ことば」を上手に使いながら「関係」が少しずつ緩やかに紡がれるように支えていくことで、インクルーシブ教育が少しずつ進んでいくのだと思います。
このようなやりとりを意図的に重ね、学校が子どもたちにとって安心して周囲と関われる場所になるよう取り組んでいくことが、学校を変えていくために、今私たちができることなのかもしれません。
【参考文献】
・青山新吾・岩瀬直樹『通常学級でインクルーシブ教育を実践するってどういうこと』(学事出版)
・青山新吾『エピソード語りで見えてくるインクルーシブ教育の視点』(学事出版)
・野口晃菜・喜多一馬『差別のない社会をつくるインクルーシブ教育 誰のことばにも同じだけ価値がある』(学事出版)P15ーP34「インクルーシブ教育とは」

青山新吾(あおやま・しんご)ノートルダム清心女子大学人間生活学部児童学科准教授、同大学インクルーシブ教育研究センター長。岡山県内公立小学校教諭、岡山県教育庁特別支援教育課指導主事を経て現職。臨床心理士。臨床発達心理士。著書『エピソード語りで見えてくるインクルーシブ教育の視点』(学事出版)、編著『特別支援教育すきまスキル』(明治図書出版)など、著書・編著多数。
【青山新吾先生 著書】
『エピソード語りで見えてくるインクルーシブ教育の視点』(学事出版)
『インクルーシブ教育を通常学級で実践するってどういうこと?』(岩瀬直樹との共著/学事出版)
イラスト/高橋正輝

