難しい保護者クレームとの向き合い方

保護者クレーム対応の実践スキル 危機を絆に変える技術⑨
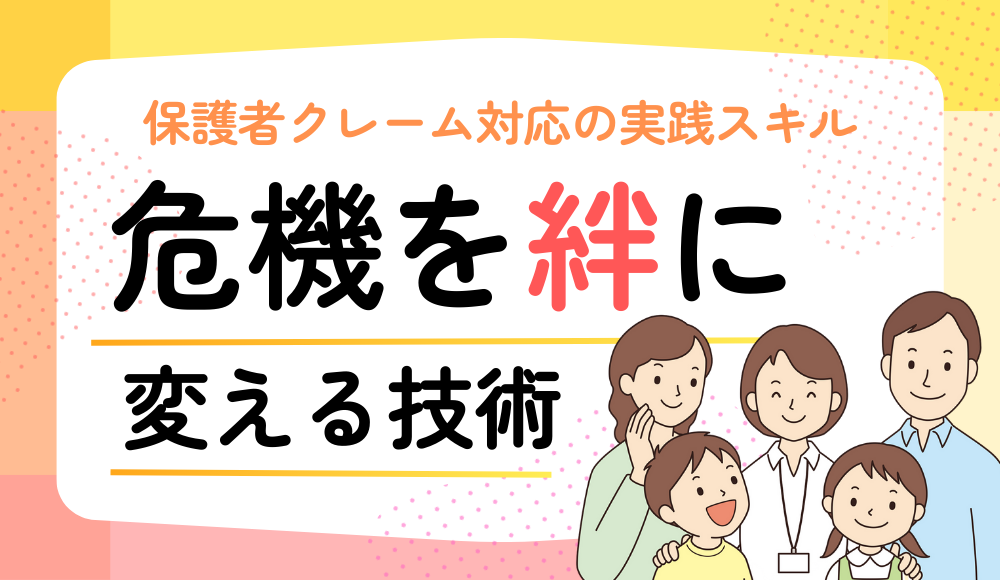
教育現場には通常の対応方法では解決が困難な「難しいクレーム」も存在します。感情的な状況が長期間継続する場合、複数の問題が複雑に絡み合っている場合、あるいは要求内容が現実的でない場合などがこれにあたります。今回は、このような困難な事案に対する戦略的なアプローチについて詳しく解説していきます。複雑な状況を整理し、長期的な視点で解決に導くための実践的な方法をお伝えしていきます。
執筆/一般社団法人日本未来教育研究機構 代表理事・熱海康太
目次
難しいクレームの特徴と分類
難しいクレームには、いくつかの共通した特徴があります。まず、感情的な要素が強く、理性的な話し合いが困難な状況が継続することが挙げられます。保護者の怒りや不安が極めて強く、通常の受容や共感だけでは感情の鎮静化が困難な場合です。 次に、要求内容が現実的でない、または学校の権限を超えている場合があります。「担任を替えろ」「加害児童を転校させろ」「学級を解散しろ」といった、学校として応えることが困難な要求がなされる場合がこれにあたります。
複数人対応の戦略的活用
難しいクレームに対しては、複数人での対応が効果的です。ただし、単に人数を増やすだけでは効果は期待できません。戦略的な役割分担と連携が必要です。基本的な構成としては、主対応者、副対応者、記録者の3人体制が効果的です。主対応者は対話の主導権を握り、相手との信頼関係構築に集中します。副対応者は主対応者をサポートし、必要に応じて専門的な説明や補足情報を提供します。記録者は会話の内容を詳細に記録し、事実関係の整理や今後の対応検討に活用します。
時間管理と構造化されたアプローチ
難しいクレームでは、時間の管理も重要な要素です。長時間の対応は、双方にとって疲労を蓄積させ、建設的な話し合いを困難にします。一般的には、30分から1時間程度を一つの区切りとし、それを超える場合は一度中断して、次回の約束を取ることが効果的です。
文書での回答に関する注意点
難しいクレームでは、保護者から「文書で回答してほしい」という要求が出されることがあります。しかし、文書での回答は多くのリスクを伴うため、慎重な検討が必要です。
文書回答の最大のリスクは、内容が第三者に開示される可能性があることです。近年、学校からの文書がSNSで拡散されたり、他の保護者に見せられたりするケースが増加しています。文書の内容が一人歩きしてしまうと、学校全体の信頼失墜につながる可能性があります。 法的な要求がある場合や、組織として文書回答が必要と判断される場合は、十分な検討と複数人でのチェックを経て対応します。
準備と事前検討の重要性
難しいクレームへの対応では、事前の準備が成否を大きく左右します。想定される質問や要求に対する回答を事前に検討し、関係する資料や情報を整理しておくことで、その場での適切な対応が可能になります。
準備すべき内容としては、事実関係の整理、関連する規則や方針の確認、過去の類似事例とその対応、提案可能な解決策の検討などがあります。また、対応の流れやゴール設定も明確にしておきます。「本日の話し合いでは○○を確認し、次回までに○○を検討する」といった具合に、段階的な進行計画を立てることが重要です。
数字やデータを用いた説明も効果的です。客観的な情報を示すことで、感情的になっている相手に対しても、理性的な判断を促すことができます。ただし、数字やデータの提示は、相手の感情を十分に受容した後の段階で行うことが重要です。
継続的対応のためのシステム構築
バナーイラスト/futaba(イラストメーカーズ)

著者:熱海康太(あつみこうた)
一般社団法人日本未来教育研究機構 代表理事
大学卒業後、神奈川県内の公立学校、私立学校で教鞭を取る。
大手進学塾の教育研究所を経て、現職。
10冊以上の教育書を執筆し、全国10,000人以上の先生方に講演を行うなど、幅広く活動している。

