【連載】坂内智之先生の 愛着に課題を抱えた子が伸びるアプローチ~学級担任にできること~#10 「メタ認知」による自己理解を促そう ―実践編その6―
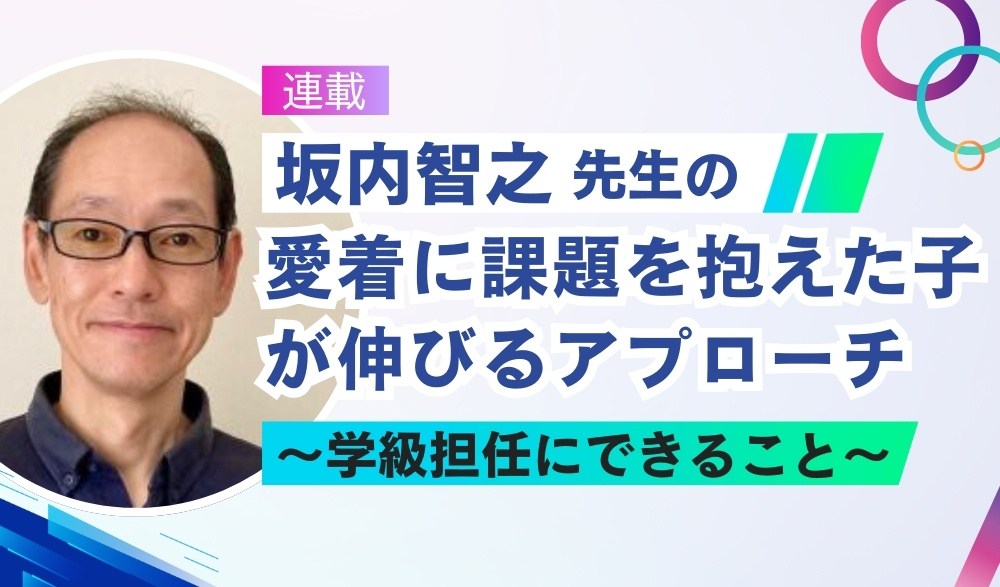
近年、教員たちが対応に苦慮し、学校現場を根底から揺るがしている「愛着障害に苦しむ子どもたち」。そうした子どもたちによって荒れた学級を何度も立て直してきた坂内先生が、今、学級担任に何ができるのかを提案し、これからの学級のあり方について考えていく連載第10回。今回は、愛着障害の子どもたちの「メタ認知による自己理解」を促す取組について考えていきます。
執筆/福島県公立小学校教諭・坂内智之
目次
はじめに
これまで、「愛着障害だな」「愛着の課題を抱えているな」と感じられる多くの子どもたちとどう関わっていくかについて解説してきました。
そんな連載も第10回を迎えた今、私には、子どもたちに対する次のような疑問が湧いてくるのです。
「あなたのその不安はいったいどこからくるの?」「本当にあなたは不安なの?」。
これまでに何度か書きましたが、私は、愛着に課題を抱える子どもと接してきたことで、自分自身も愛着に課題を抱えていたことに気づきました。両親が揃っていて、母親からも末っ子として愛されていた自分が、なぜあれほどまでに「もっと、もっと」と愛情を求め、心の苦しみを抱えていたのだろう、と不思議に思います。
また、私とは反対に、かなり家庭の環境や親の状況が厳しいのに、明るく和やかに学び、生活している子もいます。家庭環境に不安を抱えている子の全てが愛着に課題を抱えているわけではありません。それは、なぜなのか。ひょっとすると子どもたちは、「愛という幻」を追い続けているのではないか。そんなことも考え続けてきました。
今回は「メタ認知」による自己理解という視点から、愛着に課題を抱える子どもへの関わりを捉え直していきます。「メタ認知」のために私がどのような取組を行い、クラスの子どもたちとどのように対話をしてきたかを紹介していきます。
大人の社会から見えてくること
よくニュースで見かけるDVや虐待などの事件。警察や児童相談所などへの相談、訴え、通告の件数は年々増加しています。数値増加の大きな要因は「相談しやすくなった」「通告しやすくなった」ことだと思われますが、大きな社会問題として多くの人に認知されるようになってきた現在も、減少の兆しはありません。
また近年では中学受験をめぐって、両親が幼いころから過剰な学習を強いてしまう教育虐待なども社会問題になってきています。こうした社会問題に伴う大人たちの言動や姿は、愛着に課題を抱える子どもの言動や姿と重なる部分があります。
「自分の思い通りにならないと叩く、殴る」「自分の願望充足のため相手に過剰な期待をかける」「相手だけに非があると考えている」「期待した通りにならないと、裏切られたと感じる」……こうした大人たちの姿は、教室で問題行動を起こす子どもたちの姿そのものです。 これまでは、学校現場における愛着障害への対応や、愛着修復のための様々な取組を紹介してきました。しかし、そうした対応の結果、その子の小中学校時代はうまくいったとしても、それ以降の高校や大学時代にはどうなるでしょうか。その後社会人として生活し、保護者となった際には、誰が彼らをサポートしてくれるのでしょうか。
子どもの長期的な成長を考えるのであれば、その子自身の自己理解、世の中の捉え方を変えていく必要があるのではないか、そう考えています。
鍵を握る「メタ認知」
子どもを不安にさせる要因として、家庭内や学校内の環境には多くの人が目を向けています。しかし、同じ環境に置かれた子どもたちの中でも、不安の感じ方に個人差があるのも確かです。それらは個としての遺伝的特性なのか、生後の生育環境なのか、それとも神経伝達系の違いなのかなど、「なぜ人は不安を感じるのか」が、科学的に解明されるまでにはまだまだ多くの年月が必要だと思われます。
しかし、人は学習を通して自己理解を深め、思考することで自分の行動をコントロールできる生き物でもあります。子どもの愛着の課題を持続的に(大人になっても)解消していけないだろうか、子どもの対応に当たるようになってから、ずっとそう考えてきました。そのカギを握るのが「メタ認知」だと私は考えています。
その理由は自分の過去にあります。なぜ自分は満足できなかったのか、なぜあそこまで自分を強く見せようとしなければならなかったのか、なぜあんな振る舞いをしたのか。
過去の自分と向き合った時、自分自身で課題を解決できる方法があるとしたら、それは自己理解しかありません。もし、あの頃自分のことをもっとよく理解できていたら、もっと自分に満足できていたでしょうし、人を困らせるような振る舞いはしなかったでしょう。自分をよく理解していれば、不安からやってくる多くのトラブルも減らせたはずです。
日本の子育てや教育では、自分を抑えて相手の心情を推し量る「他者理解」を重視しがちですが、これからは自分の心をより深く覗き込み、「自己理解」を高めていくことが大切だと考えています。
そのためには「メタ認知」――自分を外側から客観的に見つめ、理解していく力が鍵となります。
とは言え、子どもたちにこうした「メタ認知」をもたせることはとても困難です。特に愛着に課題を抱える子どもたちは、これまで説明してきたように、自己中心に物事を考えて行動したり、逆に他者のことばかり考えすぎて動けなくなったりするからです。自己理解を高めていくためには、他者の気持ちと自分の気持ちとの違いを見つけていく必要がありますが、愛着に課題を抱える子どもは、つい自分のその場の感情に振り回されてしまいがちです。そうした状態にある子にとって、他者の気持ちに気づき、理解すること、自分を見つめていくことは困難です。
一方、自分の感情や行動を抑え込んでしまっている子どもは、他者の気持ちばかりを慮ってしまい、最も大事な自分自身を見失ってしまっている状態です。こうした子にとっても自分を見つめていくことは難しいでしょう。それでも私は、子どもたちのメタ認知の力をなんとか高めようと、ここ5~6年間試行錯誤してきました。
そうした実践の中で特に重要だったと感じている3つの鍵、「道徳教育」「てつがく対話」「アドラー心理学」について紹介していきます。
メタ認知力向上への鍵・その1 「道徳の授業づくり」

坂内智之プロフィール
ばんない・ともゆき。1968年福島県生まれ。 東京学芸大学教育学部卒業。福島県公立小学校教諭。協働学習の授業実践家で「学びの共同体」から『学び合い』の授業を経て、20年以上にわたり、協働学習の授業実践を続ける。近年では「てつがく」を取り入れた授業実践を行う。 共著に『子どもの書く力が飛躍的に伸びる!学びのカリキュラム・マネジメント』(学事出版)、『放射線になんか、まけないぞ!』(太郞次郎社エディタス)がある。

