理科の授業開きに“ふしぎ”を仕込もう【理科の壺】

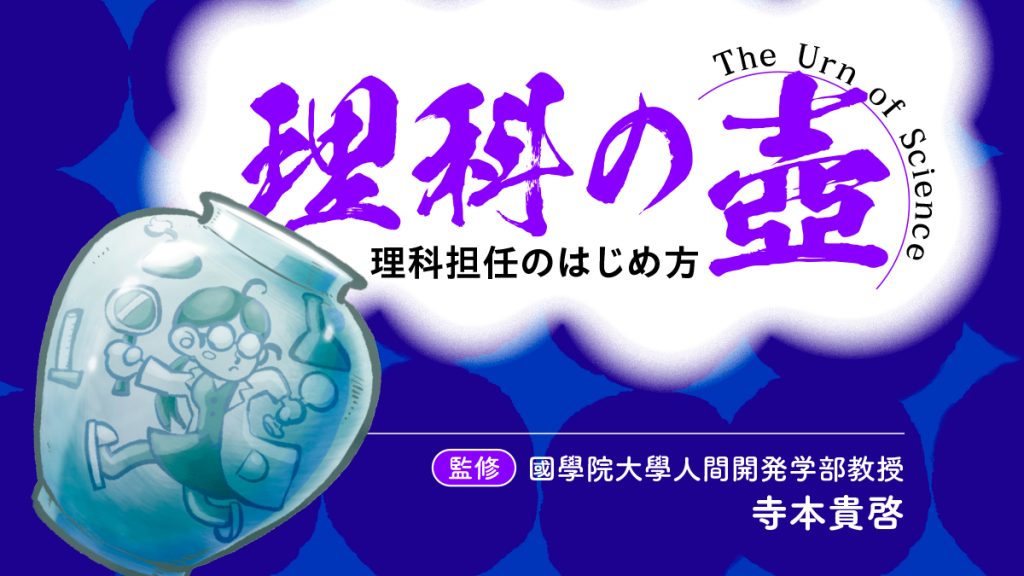
理科の授業開きは、これから理科を始めるにあたって最初にする授業です。授業開きをせずに教科書の学習を進めることも多いですが、あえてこれから行う理科の授業に「ワクワクする」「楽しい」気分を盛り上げる役割のために行います。子どもたちにウケるものや学びのきっかけとなるような授業開きのネタは、事前に考えておくとよいです。今回のネタは、子どもたちに探究の楽しさを体感してもらうため身近なティッシュペーパーを使います。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような“ツボ”が見られるでしょうか?
執筆/東京学芸大学附属竹早小学校教諭・窪田美紀
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
「面白いこと」よりも「つながること」を!
理科の授業を楽しみにしている子どもたちにとって、授業開きはその後の授業に見通しをもち、より楽しみになるための1ステップ。本稿では、そんな授業開きを子どもたちと行っていくアイデアについて考えてみたいと思います。
これからの授業にワクワクして取り組んでほしい!という思いから、子どもたちの目を輝かせるためにとにかく面白いことを、という考え方もありますが、私が目指したいのは「次につながる」ことです。
今回は、子どもたちと一緒に進めていくことで、理科での“ふしぎ(問題)”を解決していくプロセスを自然に体験できることを目指したネタをご紹介します。
ティッシュペーパーは裂け方に違いがある?
裂いてみると⋯⋯
使うのは、一般的なティッシュペーパー。このティッシュペーパーに、繊維の向きがあるのはご存じですか? 試しに、机の上にあるティッシュペーパーを1枚引き出し、真ん中を縦に裂いてみてください。すっと縦に裂けるとき(写真1)と、どうしても裂け目が横にずれてしまうとき(写真2)があります。
これは、ティッシュペーパーの繊維に向きがあるためです。
メーカーによって、中央の折り目に対して平行に繊維が並んでいる場合と、垂直に並んでいる場合があります。


棒状にして、ちぎってみると⋯⋯
4枚のティッシュを同じ向きに重ね、手前から奥に向かってくるくる巻いていくと、ティッシュの棒が出来上がります。巻く前にティッシュをどの向きに置くかによって、両端を握って水平に引っ張ったときに中央でスパッとちぎれる【弱いティッシュ棒】と、なかなか切れない【強いティッシュ棒】を作り分けることができるのです。強いティッシュ棒は、大人でも力を入れないとちぎれないくらいの強度があります。



【実践】子どもたちと一緒に「ティッシュの謎」を解決しよう!
1. 今日使用するものとの出会い
「今日はこれを使います」と箱ティッシュを見せると、「花粉症なの?」という反応をする子どもや「私もたくさん必要だから持っているんだよ」と見せてくる子もいるかもしれません。この活動では、子どもが持っているティッシュは一切使わなくてよいということを伝えておきましょう。
「最初に見てもらいたいものがあるんだ」と伝え、ゆっくりと4枚のティッシュを机上で重ねます。教卓から子どもたちの机まではある程度距離があるため、確実に4枚しか引き出していないことは見えつつも、重ねる向きまでは子どもたちは気づいていないのです。ゆっくりと重ねたあと、丸めます。私が最初に作るのは、なかなかちぎれない【強いティッシュ棒】です。
「ティッシュは薄いけれど、こうやって重ねて丸めると棒みたいになるね。これでもちぎれるかな?」と問いかけると、ちぎれる、ちぎりたいと子どもたちから立候補が相次ぎます。クラスの中から1人選び、ティッシュ棒の両端を持ち、水平に引っ張ってもらいましょう。体の前で横に引っ張るのがポイントです。他の子どもに見えるよう、前に立って挑戦してもらっています。
2. 子どもたちが“ふしぎ”を見付け、活動が始まる
ちぎれないことが分かると、「私ならできる」「今度はぼくが」とさらに立候補が相次ぎます。何度も同じもので試すとボロボロになってしまうのと、ちぎれないだけでは比較対象がないため、一度“ちぎれなかった”という事実を共有し、2つ目のティッシュ棒を作成します。次も同じく4枚を使いますが、今度作るのは【弱いティッシュ棒】です。もちろん、先ほどとはティッシュの角度が90°違うことは子どもたちに悟られないように作業します。
「仕方がないなあ。きっと切れるように,魔法をかけておくからね」と言いながら作業すると、子どもたちは「魔法なんてないよ」「怪しいなあ」「うそだあ」と、作業する私を見ながら言っています。今の段階ではまだ理科的に物事を見ていないのです。何人かは「さっきより強く巻いている」や「重ねたあと空気を抜いていたよね?」など、予想を始める子どももいるでしょう。
【弱いティッシュ棒】は、さほど力を入れずともすぐに真っ二つに切れます。代表として同じ子にちぎる役をお願いすると、先ほど【強いティッシュ棒】をちぎれなかった経験があるので力いっぱいティッシュ棒を引くのです。勢いよく棒が2つにちぎれるのを見ていた子どもたちは驚きますが、いちばん驚くのが挑戦者本人です。そのびっくりした顔をみんなが見ていることで、実際にやっていない子が実感を共有することの一助につながると私は思っています。
驚いた子どもたちはすぐに「ああじゃない?」「こうじゃない?」と話し始めます。ここで教師は意見を板書で整理しながら、『今何を解き明かそうとしているのか(問題)』を確認してみましょう。この段階では『問題』としての文言が先にできていなくても、『予想』と『実験方法』がごちゃまぜに出てきてもよいことにします。教師がそれを整理して板書にしておいて、最後に問題解決の流れとして整理すればよいのです。
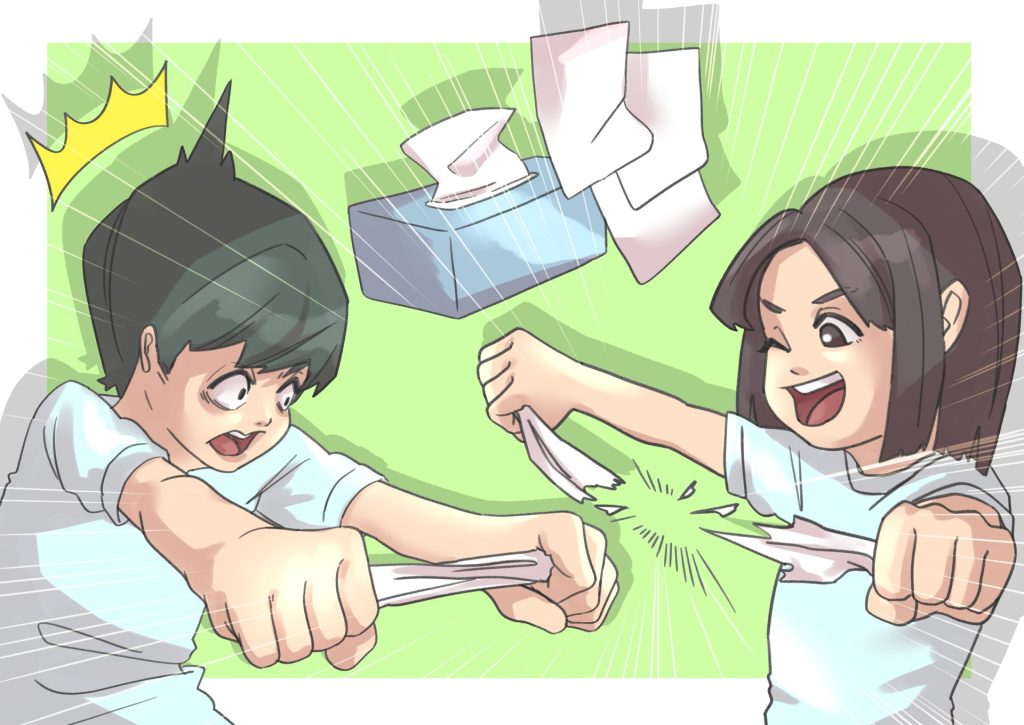
3. 予想と実験で謎に迫る
ここからは子どもたちの考えを存分に取り入れることで、問題解決の世界を子どもたちが切り開いていくことができます。

