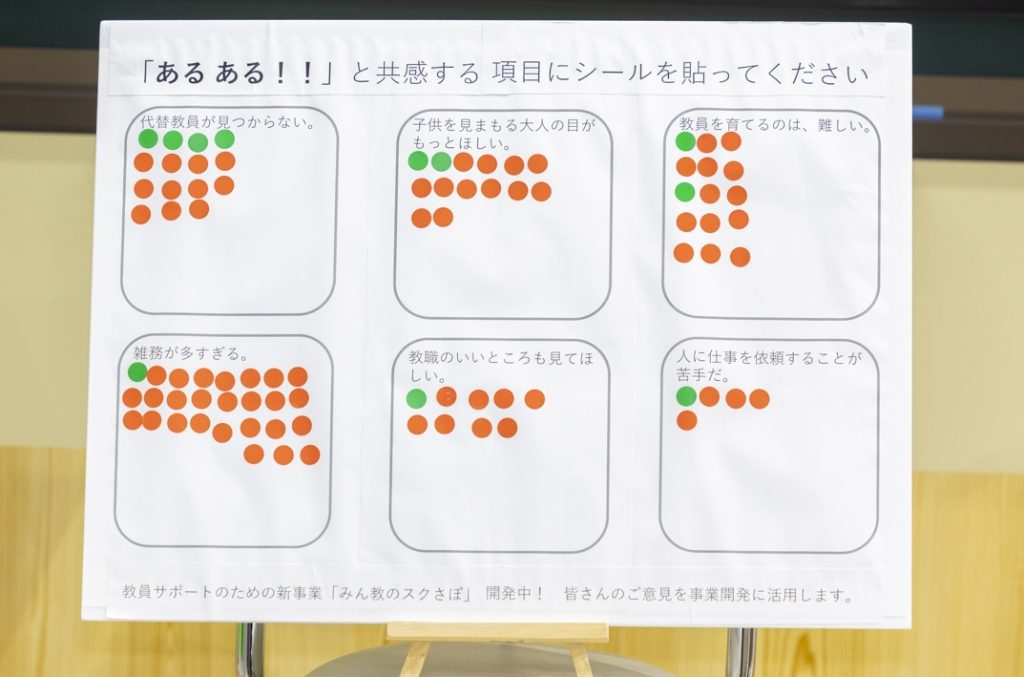学校の人手不足、どうする!? EDIX東京2025の来場者から寄せられた7つの質問への回答を公開
2025年4月23日〜25日に東京ビッグサイトで行われたE D I X東京。最終日に開催された「みん教のスクさぽ」のセミナーでは、本事業にご協力いただいた北海道安平町の教育長・井内聖さんと、みん教の連載でも大人気の元北海道公立中学校校長・森万喜子先生が、E D I X来場者が抱える「学校の人手不足」についてのお悩みに答えてくれました。その内容を紹介します!


答えてくれたのは……

元北海道公立中学校校長 森万喜子
北海道教育大学特別教科教員養成課程卒業後、千葉県千葉市、北海道小樽市で美術教員として中学校で勤務。教頭職を7年務めた後、2校で校長を務め、学校改革を進めた。「ブルドーザーまきこ」の異名をもつ。校長就任後、兵庫教育大学教職大学院教育政策リーダーコース修了。現在は、執筆活動や全国での講演の他、文部科学省学校DX戦略アドバイザー(2023~)、文部科学省CSマイスター(2024~)、青森県教育改革有識者会議副議長として活躍中。単著に『「子どもが主語」の学校へようこそ!』(教育開発研究所)がある。

北海道安平町教育委員会 教育長 井内聖
公立中学校教員を9年務め、幼児教育(私立学校法人)へ転身。幼稚園、保育園、子ども園の園長等を務める傍ら、子どもが育つ地域づくりやまちづくりに取り組む。全国から注目を浴びる安平町立早来学園開校に際しては、教育委員会に出向し、住民議論の段階から関わり、基本構想、基本設計に携わる。2024年5月より安平町教育長に就任。官民連携、公私連携の視点から0歳から18歳までの一貫した教育とまちづくりを進めている。
目次
1問目:非常勤講師がなかなか見つからない
非常勤講師がなかなか見つからず、決定が遅くなりがち。教員を育てるのも難しく、その時間もない。どうしたらいいのでしょうか?(中学校管理職)
井内/今、学校管理職の大きな仕事が「人探し」になってしまっています。でも本来、管理職の仕事は人探しではありませんよね。そして、1人で動いてもどうにもなりません。すでに教育委員会に相談はされていると思いますが、それはぜひ続けてください。その上で、教員免許がなくてもできる仕事がないかということも考えてみてください。きっと、大量にあるはずです。管理職は、教員の手配だけではなく、その仕事を教員がするべきか否かの見定めをすることも大切です。学校や役所の外にネットワークを持って、「こんな仕事があるのだけれど、手伝ってくれる人はいませんか」と、訴え続けましょう。直接的には難しくても、間接的に助けてくれる場合もありますよ。
森/中学校で校長をしていた時には、私も3月になると毎年先生探しをしていました。普段から「こんな学校経営をしています」と周りにアピールをしてきましたし、自分の学校の情報を外にオープンにして、新しく来てくれる先生に安心してもらえるように努めてきました。ただ、これは自治体ごとに違うのは確かですね。「学校のことを発信するな」という方針のところもありますから。でも、こういう時代だからこそ、こちらの情報もオープンにするべきだと私は思います。
また、教員を「育てる」のも難しいということですが、「支える」と考えたら良いのではないかと思います。上から指導するのではなく、新しい人が持つ新しいノウハウを大切に、支えるのです。そして一緒に楽しく仕事をしていく、というスタンスで良いのではないでしょうか。
2問目:短期間、短時間の勤務なら手を貸したい人はいそうだが、どうすればいい?
短期間、短時間などの柔軟な働き方ができるのであれば、潜在的には手を貸したい元教員なども多くいるのではないかと思うのですが、どこから発掘したらいいでしょうか?(教育系大学教授)
井内/短期間、短時間の働き方であれば協力してくれる人はいると思います。ただ、都道府県で採用する先生でやろうとすると難しい。もっと小さい単位の自治体・市町村で採用するならそういう働き方も可能だと思います。
例えば安平町では、児童館の職員を4月と5月の午前中だけ1年生の教室に配置しています。児童館の職員は民間の運営で2か月間だけ採用します。子どもにとっては2か月でも一緒に過ごす先生だと分かります。さらに、子ども園の5歳児の先生は子どもの卒園後、そのまま1年生の教室に半年間入るようにしています。これらの予算は特別支援の費用で賄っています。個別の対応で、特別な支援が必要な児童だけではなく、一人一人に合ったような配慮をしながらサポートしているからです。
市町村の教育委員会に相談してみてはいかがでしょうか? 安平町の例を出して、実際にやっているところがあると言ってみてください。
森/学習支援員など、教員免許を持っていない、教員ではない働き方をしている人はいますよね。その人たちにどういう仕事を任せるか、検討していただきたいと思います。他の人の仕事をなぞるような働き方をしている人が多いのですが、もっといろいろな可能性があるはずです。学校に人手が足りないのはどこも同じ。まずは、そういう視点で、自分の自治体でできることを探すのが近道です。
3問目:特定の役職に仕事が集中する
校務分掌による仕事量に差があります。教務主任である自分に仕事が集中しています。(小学校教員)
森/学校は教務(教育や学習に関する事務)の仕事が多いですよね。たとえ子どもが少なくても、教務の仕事の種類は減りません。先生はまじめな方だと思いますので、まず一個ずつ仕事を箇条書きにしてみましょう。それを他の先生や職員に振り分けます。目的は仕事を減らすことです。今の仕事をどうするかではなく、減らすんです。他の先生とワイワイ話しながら削っていきましょう。事務仕事はやらなくても困らないこともあるはずです。
井内/最終的には、減らすのではなく、やめる・ゼロにする・やらないを目指したいですよね。
例えば、安平町では地域のプリントを配るのをやめてみました。休んだ子への対応に関しては、その日の配付物を配信に変えてみました。地域にも協力してもらい「配付しません」と告知しました。デジタルを使うことでゼロになるかどうかを見ていくためです。減らすのではなく、ゼロにという視点で見てみることにしたんです。教務主任に業務が集中するのは、従来のやり方では避けられないと思うので、学校が省力化できる業務を手放すことにしました。
森/生徒の家庭の立場になってみると、学校から配られた紙がいっぱいになるのは大変なんですよね。逆に配信だったら、必要なときに検索できる。私は、現金の集金もやめました。人数分の集金袋に小銭が入っているのは、数えるのが大変ですからね。一般社会の感覚と学校はずれていることもいっぱいあります。是正していきましょう。

4問目:伴走支援による育成度はどうやって測る?
先生になった後の研修をしています。伴走支援したいと思っていますが、どうしたらその人が育ったと計測できるでしょうか? (教育委員会・指導主事)
森/初任者教員の成長を評価することは、非常に危険なことだと私は思います。初任者自身が自分の課題を見付けることが第一。そのためには、怒られるからこうする、ではなく、自分はこうしたいと思う、と、ちゃんと言える関係性を築けていないといけません。初任者自身にやりたいことがあり、こうやってみよう、という姿勢が形成されるように補佐するのが、伴走支援だと思います。だから、おこなうべきは計測ではなくて、「あなたはどう思う?」 「どうだった?」「なるほどね」と話を聞いて、フィードバックすることだと思います。
井内/必要なのは、ジャッジではなくアセスメント。先生が成長しているかどうかを判断するのではなく、その先生の深い部分まで理解をして、一緒にやっていこうという空気が醸成されて初めて伴走なのではないかと思います。
様々な意見があり、まだ実現には至っていないのですが、私は、教員評価はやめたいと思っています。これからも、主張し続けていきたいと思います。
5問目:教育委員会への上手な伝え方
職場だけでは人材を探すのが大変です。地域、休職者、学生ボランティアなどでどうにか支援体制を組んでいますが、質の維持が困難です。まさに「みん教のスクさぽ」のようなサービスをすぐにでも導入したいのですが、どのように教育委員会に伝えるとよいでしょうか。
井内/自治体と学校現場では、大きく視点が違うところがあります。
学校では子どもが真ん中にいます。一方、自治体は市民が真ん中にいます。自治体にとっての市民は、この町を将来、ふるさととして作っていく存在です。
子どもたちの幼少期が笑顔に溢れ充実したものであれば、大人になった時に自分の出身地に戻ってきます。北海道の場合、大人になったら自分の街を出ていく人も多いのですが、子育てのときには戻ってくることもまた多いのです。「自分の子どもを育てるなら、安平町がいい」と考えるからです。
子どもが大人になるまでに、いちばん長く過ごすのが学校。
この視点だと市民、自治体、教育委員会へ届きます。
学校の先生が、「現場の余裕がない」という言い方で伝えるのではなく、この町、この学校の児童生徒の人生が豊かになってほしいので、人材が必要だと言うのです。地域にはいろいろな年代の、先生以外の大人もいた方がいいのも当然のことです。
森/私はコミュニティ・スクールを推進してきましたが、今の教員の大変さを訴えるだけでは周囲が引いていくんですよね。だから、地域社会全体のストーリーや教育改革として話せると良いと思います。
井内/そして、教育委員会側が「それは分かるけど、どうやってやるの?」って言ってきたら、そこに「みん教のスクさぽ」がある! と、話す(笑)。
森/スクさぽ、試しに使ってみてほしいです!
6問目:私学なので地域との連携が難しい
教員免許がなくてもできる仕事が多すぎて、教員が生徒に向き合う時間を奪われています。かといって、私学なので地域との連携も難しいです。(中学校管理職)
森/まず、文部科学省は、学校・教師が担う業務を3つに分けました。「基本的には学校以外が担うべき業務」「学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務」「教師の業務だが、負担軽減が可能な業務」です。
例えば、必ずしも教師が担う必要のない業務となっている校内清掃が1日15分だとして、1年間で約46時間掃除することになったとしますよね。これは中学の美術の授業時間を超えています。他のことをやった方がいいですよね。
こうやって整理してから、他のやり方はないか、地域に委託できるものはないかなどと考えます。地域との連携が難しいとのことですが、地域は、子どもたちにとって教育の環境として大切なものです。先生と親と私と僕だけではない、地域との関係性というものが子どもには必要。子どもが市民として成熟していくために必要なものだという視点から、考えてみるのはどうでしょうか。
井内/私は20年間、私立の学校法人(幼児教育)にいました。公立と違い、私立の場合、その学校を選んでお金を払ってきてくれているので、保護者は学校にとって心強い協力者です。保護者との繋がりの中から地域の発掘をしていけます。
地域を立地で考えないでください。保護者から耕していくこともできます。学校に対して愛着を持っている人を増やしていけば、地域とつながっていけます。
7問目:外部人材に協力してもらいたくても、壁がある
外部人材に協力してもらいたくても、壁があると感じます。自治体の予算が硬直的であることも一因だと思います。それについて、どう思いますか?(教員養成大学・准教授)
井内/安平町では、学生のインターン生を1年間受け入れています。新卒でいきなり担任は厳しいので、学校に勤めたいと考えている学生を受け入れるインターン制度を設けているのです。
インターンは教員ではなく、契約は1年です。正規の先生だけで学校を回そうとするのは難しいですし、そうして、多様な人材を受け入れる土壌を作ると、学校が強くなります。
皆さん誤解しているのですが、学校にいる大人イコール教師ではありません。学校にいる大人は皆教師だと思っている、その意識を捨てると突破口は見えてきます。学校には教師以外もいっぱいいます。そういう意識転換が必要だと思います。
早来学園は、施設の管理は民間委託で、先生がしなくていいんです。学校イコール教師だという認識を捨てることで学校に教師と地域の人がいる状態になります。
予算のことを言うなら、自治体が出さなくても、国に出してもらうという方法があります。
安平町でも、総務省がやっている地域おこし協力隊や、地域活性化起業人制度などを利用してきました。
森/学校の中に、教員免許を持っている人がエライという意識があるとそれが壁になると思います。司書やカウンセラーの方々は働きやすい? 発言ができている? 教職免許を持った先生の言うことより、軽んじられていない? そこを考えるだけで、みんなにとってプラスになると思います。
管理職や教育委員会などの皆さんは、学校に必要なスタッフについてもっと研究したほうがいい。開拓しましょう。学校にいるスタッフたちと一緒に話して、考えていく場面がもっと必要で、それは楽しい作業になります。一緒に学校を作っていくんですから。
最後に
井内/今、先生が大変なのは事実です。少子化が進んでも、先生は楽になっていません。先生だけが頑張るのではなく、先生をサポートする人が大切です。サポートする人を皆で育てる必要があると思います。私も、このことを声を大にして言っていきます。これからも一緒に頑張っていきます。
森/学校は伝統的に自前主義。「子どもたちに私がやってあげなくちゃ」は実はありがた迷惑なことも多い(笑)。そこから脱却しましょう。私はいつも打開策を探しています。自分の見聞きしたものを組み合わせて、最適なものを考えていれば、何か必ず見つかります。自分の学校の中、自分だけで、何とかしようと思わないでくださいね。
「みん教のスクさぽ」オンライン支援についてはこちらの記事もお読みください
取材・文/「みん教のスクさぽ」準備室