授業が動くのは、子どものひとことから ─対話が深める理科の実験と考察─【理科の壺】

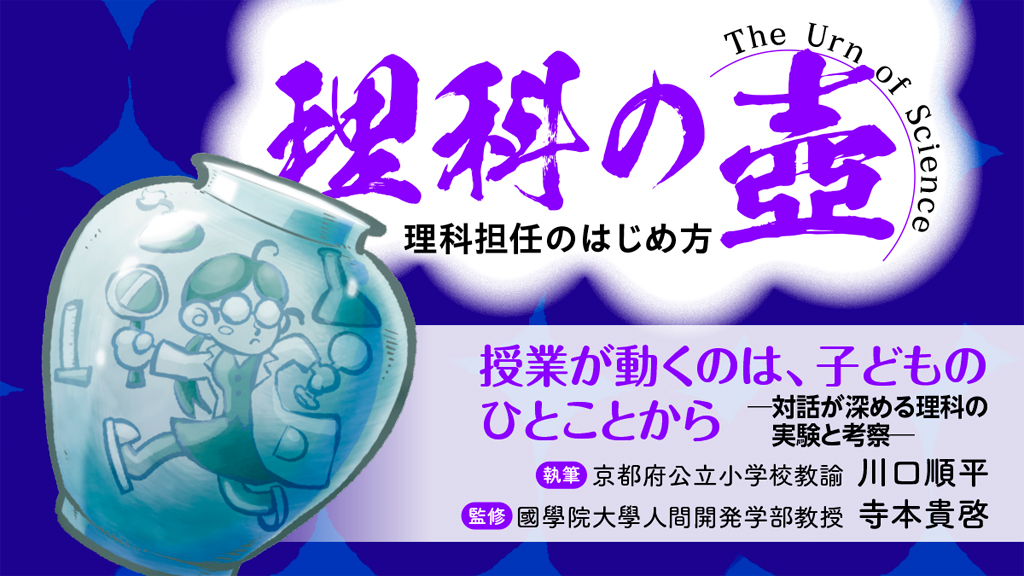
子どもたちが実験を行って結果が異なるとき、みなさんはどう対応していますか?「いろいろ違いがあるけど、実は○○の方が正しいんだよ」と教えてしまっていませんか? でも、本当はあっさり教えたくない。子どもたちに考えてほしい…と思いながら、どうしたらよいかわからない。今回は、実験結果の違いを活かした学びの深め方です。実験の結果が異なるとき、実は先生の言葉一つで子どもたちの学びが深くなるかが決まります。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?
執筆/京都府公立小学校教諭・川口順平
連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓
1.授業中、こんな場面ありませんか?
「うーん、結果が違いすぎる。どうやってまとめよう…?」実験をしてみたけれど、結果が予想と大きく異なったとき、どうしてもその理由を無理に説明しようとしてしまうことがあります。子どもたちが実験結果を見て「うちの班のはすぐに変わったけど、他の班のは変化が遅かった!」と気づくと、「きっと温度が足りなかったんだ」「道具が違ったからだ」など、何とか自分たちの結果を納得させようとします。
このように、実験の結果がバラバラだったとき、「うまくいかなかったな」と感じることもありますが、そこで無理に結果をまとめようとするのは、とてももったいないことなのです。実は、実験の結果がバラバラだったときこそが、子どもたちが深く考え、探究心を高めるチャンスなのです。
2.子どもたちの対話から学びが深まる瞬間
授業を進めていくと、子どもたちが各班の実験結果を比べ合い、意見を交換する場面があります。実験の結果が異なると、「どうしてこんなに違うんだろう?」と疑問をもち、グループ内で意見を交わすことがよくあります。たとえば、ある班では水の色がすぐに変わったのに、別の班では変化が遅かった。子どもたちはそれぞれの班の結果を見ながら、「温め方が違うからだろうか?」、「火を当てた時間の違いかもしれない」と、さまざまな意見を出し合います。
そんなとき、先生が「どうして結果が違ったんだろうね?」と問いかけることで、子どもたちはさらに自分たちの観察を深め、次第に実験の理解が深まります。このように、子どもたちが結果を振り返り、意見を出し合うことで、新たな課題や疑問が生まれ、それに対する答えを探る過程が、学びを深める大きなポイントとなるのです。

