「国語は体育だよ」 【「高校につながる英・数・国」の授業づくり #35】
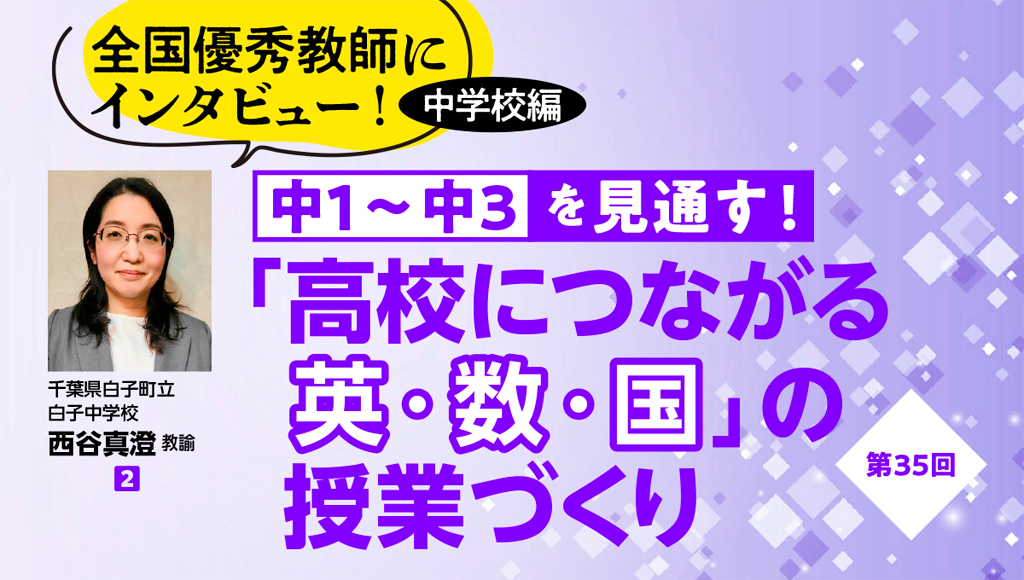
前回から、千葉県の「授業づくりコーディネーター」である、白子町立白子中学校の西谷真澄教諭に、国語の単元・授業の実例やその裏側にある考え方についてお話を伺っています。今回は、前回紹介したような単元・授業を行う意図や、そのような単元・授業を通して育みたい力などについて聞いていきます。

西谷真澄教諭
目次
少し背伸びするくらいの文章を選んで授業
西谷教諭は、前回紹介したような単元の裏側にある、国語の単元・授業づくりの基本的な考え方について、次のように話します。
「私は今、子供たちが社会に出たときに、自力で本が読めたり、自分で文章を書いたりする力(=人から聞いたり、人と話したりする力)を身に付けられるようにすることをめざしています。中でも最も大事にしたいのは、将来何か困ったときに、読書をしたり、他の人に話を聞いたりして、自分で解決できるような主体性を育てたいということです。そのため実際の単元では、自分で何か作るとか、表現することをゴールに設定しながら、その過程で本を読んだり、人と話したりする機会を多くもてるようにしたいと考えています。
目の前の子供たちの実態を見てみると、幼年期の読書体験で終わってしまっている子供や、『自分は本は好きではないので、読書はしません』と言う子供もいます。趣味自体も深く追求していくような趣味がない子も少なくなく、会話の内容が『部活とゲームとSNSしかない』という感じの子供もいます。
そんな子供たちが多用しているSNSには、レスポンスの型のようなものがあり、そこにはめ込んで表現する場合が多いようです。しかし、その型だけでは社会に出て自分の環境とは異なる人とうまく話ができなかったり、話が盛り上がらなかったりするでしょう。それでは彼らの世界が広がりません。ですから、初めて話す人たちにも論理的に表現する力を付けさせたいのです。そうすれば、新しい世界に飛び込むときも何も武器を持っていない状態ではないので、落ち着いて入っていけるだろうと考えるのです。
ですから、教材を選ぶときも少しむずかしめの教材、例えば新聞や雑誌の記事を使うなどして、実際に世の中にある、少し背伸びするくらいの文章を選んで授業をしています。そして、この教材を読んだことで新聞や雑誌に興味をもって、『自分の興味のある別の記事も読んでみた』とか、それによって普段使わない語彙を獲得できたというふうにしたいと意識しています。
とはいえ、いきなり『こんな文章も読んでみよう』『こんな本も読みなさい』と言っても、子供たちは読みません。中学生らしい一般書のようなものも読んでほしいと思うのですが、本を探して読む機会もない子供がいます。そこで年に2、3回、授業の中で前回紹介したような単元や、ビブリオバトルのような単元を行う機会をつくって、慣れない子供たちとは一緒に本を探すなどして、自ら本を探し、触れる機会をつくるようにしています」

