【連載】坂内智之先生の 愛着に課題を抱えた子が伸びるアプローチ~学級担任にできること~#5 愛着障害の子どもの家庭と、どう連携する?ー実践編その1ー
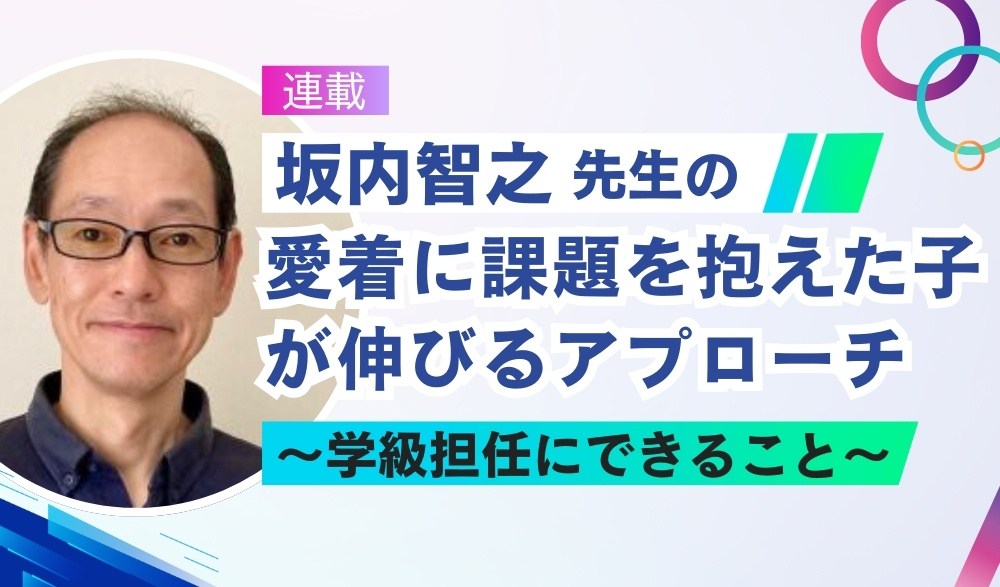
近年、教員たちが対応に苦慮し、学校現場を根底から揺るがしている「愛着障害に苦しむ子どもたち」。そうした子どもたちによって荒れた学級を何度も立て直してきた坂内(ばんない)先生が、今、学級担任に何ができるのかを提案し、これからの学級のあり方について考えていく連載第5回。今回からはいよいよ実践編。切実な課題である家庭へのアプローチについて考えていきます。
執筆/福島県公立小学校教諭・坂内智之
目次
はじめに
「問題が起きて家庭に連絡したのに、保護者がすごく不機嫌で困った」「家庭が原因なのだから、もっと協力してくれればいいのに…」「そもそも、家庭とまったく連絡がとれない……」。
学校での子どもの問題行動の原因は家庭にあると考え、教員は家庭に連絡を入れます。ところが、こうした連携はなかなかうまくいきません。なぜなら、保護者もまた強い困り感をもち、悩んだり苦しんだりしているからです。また、愛着に課題を抱える子どもの場合、えてして親が身近にいる家庭内では問題を起こさず、学校での不適切な行動について保護者が理解できない場合も多いからです。
愛着の課題を抱える子どもたちの対応について、まず私がみなさんにお伝えしたいのは、「家庭との連携を見直しましょう」ということです。家庭との連携はとても難しく、時には事態を悪化させてしまう場合もあります。
今回は、私自身の事例を紹介しながら、家庭との連携とはどうあるべきか、そのために何が大切なポイントなのかについて考えていきたいと思います。
1. あえて家庭との「連携」を緩めよう
私は、強い問題行動のある子どもであっても、基本的にその家庭へ電話しませんし、連絡帳にも書きません。どうしても連絡しなければならない場合――友達に大きなけがをさせてしまった場合や、高価な物を壊してしまった場合には電話してその後の対応について話し合いますが、それも年に1、2回あるかどうかです。
もちろん、クラスを担任したばかりの年度当初は、子どもは毎日のようにトラブルを起こします。それでも担任である自分が対処し、解決できるものであればそこで終わりとし、いちいち保護者に細かく連絡することはしません。
「えっ? 家庭と綿密に情報共有することは大事なんじゃないの?」。そう思われるかもしれませんね。
私が家庭との連携をあえて「緩める」のには、次のような理由があります。
第1の理由は、「保護者は学校から連絡が来ることを、とてもつらく感じる」からです。
かつて、問題行動の激しい子の保護者が、「毎日のように学校から電話連絡があり、夕方電話が鳴る度に動悸が激しくなってつらくなった…」と、ぽつりぽつりと話してくれたことがありました。想像してみてください。家庭にはその子だけでなく、別のお子さんがいるかもしれません。まだ手のかかる幼児がいるのかもしれません。保護者自身の仕事も家事もあるでしょう。
その上、私たち教師が電話するのは、家庭が最も忙しい夕方から夜の時間帯です。仕事から帰って、さあ、夕ご飯の準備をしようとした時、学校からの電話が鳴って、学校でのわが子の問題行動について聞かされます。申し訳なく思い、謝罪します。その電話を切った後、落ち込んだまま夕ご飯の支度に入らなければなりません。どうでしょう、その連絡は、保護者にとって、かなり苦しいものだと感じませんか。中には毎日学校からかかってくる電話で心を病んでしまい、仕事もやめて家に引きこもってしまったお母さんもいました。教師は、こうした保護者の苦痛を想像し、理解していく必要があります。
第2の理由は、連絡の目的そのものについて、よく考え直す必要がある、ということです。中には「連携」となっていない連絡があります。学校内で起こる数々の問題行動、そしていくら対応しても一向に収まらない状況、それらを一方的に保護者に伝えることは、「連携」と言えるでしょうか。
教員が連絡する目的の中には「保護者がもっと責任をもって家庭で指導してほしい」「教師である私の苦労も知ってほしい」「あなたのお子さんのせいで私はこんなに大変なのだ」と伝えたい思いが隠れているかもしれません。そうした「私は大変なのだ」「困っているのだ」「どうにかしてほしい」という思いは、直接言葉には出さなくても、ニュアンスとして伝わります。保護者が「迷惑をかけて申し訳ないな」と感じ取ったとしても、じつは親にできることは限られています。
先生方のつらく苦しい気持ちは十分に分かりますが、連絡するその意図は何か、もう一度立ち止まって考えてみる必要があります。
そして最大の理由は、こうした連絡による親子関係への悪影響が危惧されることです。
学校から連絡があった際、どの親も初めはわが子を諭すように「どうしてそんなことしてしまったの?」「こうしてみたら?」といった言葉をかけることでしょう。ところが、そうした連絡が頻繁に続けば、「またやったの?」「この前約束したよね!」と、その言葉は次第にきつくなっていきます。
私が受け持った保護者の中には「昨年は学校から連絡がある度に、子どもを怒鳴りつけていたんです」と話される方もいます。家庭に頻繁に連絡を入れることは、親子の関係を冷やしていきます。
愛を求めている子どもが、ストレスのたまった親から厳しい言葉を受け続ければ、その心はさらに苦しくなり、冷え切っていくことでしょう。その結果当然、学校での問題行動はさらに大きくなっていきます。
家庭に頻繁に連絡することが連携であり、正義だと考えてこられた方は、いったん立ち止まり、もう1度「連絡が本当に必要なのか」「連絡の目的は何のためか」「連絡することで子どもにどんな効果があるのか」を考えてみることが大切です。保護者にも、まずは安全や安心が必要だからです。
一方で、頻繁な連絡を望む保護者もいます。そうした保護者には、「私から連絡がないときには、お子さんが学校でうまく問題を解決できている証拠ですから安心して大丈夫ですよ」「気になるときにはいつでも連絡をくださいね」といった言葉をかけておくと安心してもらえるでしょう。
2. あえて緩めるからこそ、つながることができる

坂内智之プロフィール
ばんない・ともゆき。1968年福島県生まれ。 東京学芸大学教育学部卒業。福島県公立小学校教諭。協働学習の授業実践家で「学びの共同体」から『学び合い』の授業を経て、20年以上にわたり、協働学習の授業実践を続ける。近年では「てつがく」を取り入れた授業実践を行う。 共著に『子どもの書く力が飛躍的に伸びる!学びのカリキュラム・マネジメント』(学事出版)、『放射線になんか、まけないぞ!』(太郞次郎社エディタス)がある。

