【野口芳宏「本音・実感の教育不易論」第70回】今どき教育事情・腑に落ちないあれこれ(その11) ─不登校、苛め過去最多・「良薬口に苦し(中の2)」─

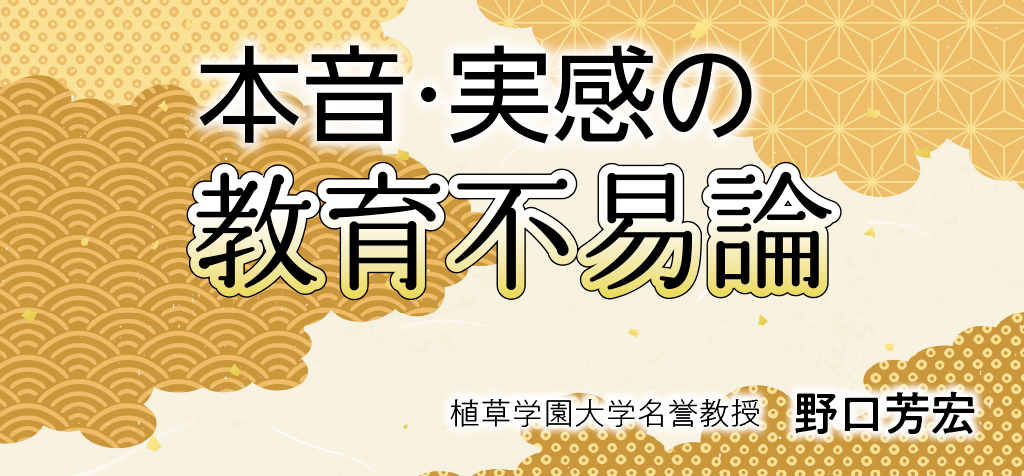
国語の授業名人として著名な野口芳宏先生が、65年以上にわたる実践の蓄積に基づき、不易の教育論を多様なテーマで綴る硬派な連載。今回も不登校児童生徒数、小中高生の自殺者数が増え続けて止まらない事実を受け、教育昏迷の根本的原因について考えていきます。
執筆
野口芳宏(のぐちよしひろ)
植草学園大学名誉教授。
1936年、千葉県生まれ。千葉大学教育学部卒。小学校教員・校長としての経歴を含め、65年以上にわたり、教育実践に携わる。96年から5年間、北海道教育大学教授(国語教育)。現在、日本教育技術学会理事・名誉会長。授業道場野口塾主宰。2009年より7年間千葉県教育委員。日本教育再生機構代表委員。2つの著作集をはじめ著書、授業・講演ビデオ、DVDなど多数。

目次
7、子供と学校の身辺事情 (前回の5を受けて)
令和5年度の公立学校教員の精神疾患休職者は前年比580人増の7千119人の過去最多で、その要因の最多、26.5%が「子供の指導上の問題」、それに次ぐのが職場の人間関係でほぼ24%。
また、小中高校生の自殺者は513人で「過去最多水準で高止まり」だが、一般の自殺者数は減少しているのに「子供の自殺者」が増加していると厚労省の白書は報じた。これらを私は残念ながら、「教育氷河期」という言葉で束ねたのだった。
このような残念なデータを見ていた折に、次のような某紙の「腑に落ちない」5つからなる言葉に出合ったのだった。それらは前回紹介したので①と⑤のみ再掲する。
① 家庭の経済格差が生み出す、子どもの教育格差。
⑤ 本人の努力に関係なく家庭の収入格差がそのまま子どもの教育格差に繋がっている。
①も⑤も「子どもの教育格差」という事実についての紹介文である。これらに触れつつ、読者各位に向けて私は「賛成なら◯を、おかしいぞ、と思うなら✕をつけてみて貰いたい」と書いて前回の5の文章を結んだのだった。
私は、全てに×をつけたのだが、同じ人があるだろうか。ひとりもないかもしれない。あるいは、私が袋叩きにされるかもしれない、とさえ思うのだが、以下に私の考えを記して批判を受けたい。なぜ✕か。
上掲2つの文は、次のように書き替えることができる。
① 子どもの教育格差は家庭の教育格差が生んでいる。
⑤ 子どもの教育格差は家庭の収入格差によるのであって、本人の努力には関係がない。
原文をA、書き替えた文をBとすると、AとBとは、明らかに文の形は異なるが、文意は同じだと私は考える。ニュアンスは異なるが内容は同じだ。いずれも「子供の教育格差」は「家庭の経済状況」が生んでいる、という主張である。
一見していかにも正しい考え方、主張のように思われるのだが、私はここに今の日本の「教育の昏迷、低迷」の要因、少なくとも一因がある、と思えてならない。前掲のA、Bをこのように書いたらどうなるか。
C、家庭の経済格差を無くし、同等にすれば、子供の教育格差は解消される。
D、家庭の経済が豊かになるほど、子供の教育水準は高くなる。
Cに◯をつける人はどのくらいいるか。Dについてはどうなるだろう。大学への入学、進学ということを「教育水準」と考えれば◯をつける人もあろうが、教育水準は学歴そのものではない。 筆者が全てに×をつける理由は単純である。「金が全てを解決する」「全ては本人の周囲、環境の責任」という考え方に私は反対だからだ。前回紹介した5つの文言、文体、文意には「本人のあり方、考え方」が不在なのだ。周囲や環境に対する本人の「見方、考え方、受けとめ方」、つまりは本人の「観」のあり方や、その重要性が欠落している。そのことへの私の無念が、全てに×をつけさせるのだ。
8、責任内在論と、責任外在論
敗戦という空前の悲劇を乗り越え、日本国はこれまた空前の豊かさと、平和と、快適さとを手に入れて現在がある。そう考えると、それは一に掛かって「教育の成功」にある、とも考えられないことはない。だが、これに賛同する人がどのくらいあるだろうか。私の実感として、現在の日本国の繁栄が「教育の成功」に因る、とは残念ながら思えない。「繁栄」「快適」は物質的発展であり、人間としての「精神的発展」という面になると、発展というよりはむしろ「衰退」「貧困」という語の方がふさわしいのではないか、と思うのだ。そして、それは、大きく「教育」に責任があるように思えてならないのだが、どうだろう。
責任が自分にある、という考え方を、私は「責任内在論」と言い、責任は自分にはなく、他にあるという考え方を「責任外在論」と呼ぶことにしている。現代世相は「責任内在論」が痩せ細り、「責任外在論」が肥大化している。責任転嫁の世相である。このこと自体が、「精神的貧困」である。この精神的貧困は、「教育の責任」であり、成果?であろう。以上は「責任内在論」の立場である。
この立場を堅持しつつ、現代あるいは現在の教育昏迷の根本的原因を考えてみたい。
無論のこと、一介の教員としての私の限界内の「ごまめの歯軋り」に過ぎないかも知れないのだが──。
先の教育格差と経済格差論に触れよう。引用した文言からは「責任外在論」のニュアンスを私は感じざるを得ない。子供本人の努力や責任は全く視野から外されている。この論法で進めば、二宮尊徳も、松下幸之助も、野口英世も、豊臣秀吉も存在しなかったことになる。偉人伝に登場する彼らは苦境の中にあってこそ生まれた偉人なのだ。
子供の「主体性」「自主性」の尊重という美辞は戦後の80年を常に牽引してきた言葉だ。が、それらは専ら「我がまま」や「自己中心」「利己」「権利の主張」という「自分本位」「自分第一」「自己主張」の方向の強化に役立ち、「責任外在論」を殖やすことになった。結果として、苛めや不登校や引きこもり、果ては自殺等の「過去最多」を生む悲劇として結実した。一見子供を幸せにする文言のように思えるが、結果は子供を不幸に追いやるという皮肉を生んだ。子供に関わる負の事態の増加は、子供らからの「体を張った告発」のように、私には映るのだ。
子供らは、「このままの教育では駄目だ」「現在の教育はどこかおかしい」「何か大きな勘違いをしてはいないか」と、体を張って叫んでいるように、私には思えて仕方がない。以下、私の「本音・実感」に基づく思いを述べる。批判を乞う。

9、子供の正体、実像の勘違い
常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取組や政策を我が国社会の真ん中に据えて、強力に進めていくことが急務です。
上記は、こども基本法の第一条〔目的〕の解説の二番めに出てくる文言である。この法律によって子供がやがて国家を背負う実力を養えれば嬉しい。それを切望する。
上記引用は解説文の一つであって法文ではないが、この文中の「こどもの最善の利益を第一に考え」という一節が気になる。「何を以て最善の利益とするか」という文言だ。最善というのだが、それが最悪にならなければいいが──とも思う。
この解説の一文に違和感を持つ者は一般にはいないだろう。だからすんなりと読み進めていくのが一般であろうと思うのだが、「こども」という存在をどうとらえて「最善の利益」を決めるのだろうかと考えると事は単純では済まなくなる。
次のような言葉をよく耳にする。
「子供は無限の可能性を秘めた存在だ」
ここにある「無限の可能性」は、一般に良い意味、プラスの意味で使われ、解されているがそれは間違いだ。「無限の可能性」にはプラスもマイナスもある。無限に良くなる可能性も、無限に悪くなる可能性も秘めているという解釈が正しいのだ。
カントの言葉と伝えられる次の言葉が私は大好きで、よく引用する。
「人は人によって人となる」
同じ “人” という字句が3回使われているが、私はこれを次のように解釈している。
「ヒトは、教育によって初めて人間になる」
動物としてのヒトが、社会生活ができる人間に自然にはなれない。教育されることによって初めて人間になれるのだ。自然に体が大きくなる発達だけでは「人間」にはなれない。言葉を覚え、コミュニケ―ション力を身につけつつ成長していく。──だからこそ「教育」が重要になるのだ。教育の成否によってヒトは、善にも悪にも無限に伸びていくのだ。だから教育が重要なのだ。
そこで、「子供」という言葉、その内実をどうとらえるかが問題になる。「子供は天使だ」と解すれば、格別の教育は不要になる。生長さえすれば天使になるからだ。「こどもの最善の利益」という時の「こどもの正体、本質、根本」のとらえかたを誤ると、とんでもないことになる。
私は子供の正体「本質、根本、原点」は「無知、未熟」と解している。その故にこそ、いろいろのことを教え、正し、導く「教育」が必要になってくるのだ。今どき子供の本質を「無知、未熟」などと言ったら、子供の人権を無視した暴言だと袋叩きに遭いそうだ。もっとプラスの、明るい、優しい認識をすべきだ、と言われそうだ。
然らば問いたい。それなら、不登校、苛め、自殺、非行などが、この世に出現する事実は生じない筈ではないか。それらが11年にも亘って「連続過去最多」になどなる筈がないではないか。彼らは、現在の教育が生んだ被害者であり、彼らは残念な形を伴いながら、教育者の我々に教育の在り方を告訴、告発しているのだと、私は考えたい。教育の何かが欠け、誤ったのだ。
ヒトの彼らが、健全な人間になるために必要にして有効な教育を求めていたのに、そうでない教育をされたから苦しんでいるのではないか。そうだとすれば、教育者である我々は「責任内在論」の立場に立って「どこかに誤りがあったのではないか」と自己反省をしなければならないことになる。
不登校や引きこもりの子供らは「生きる力」としての「強さ」も教えて貰いたかったのではないか。だが、今の教育は「強さ」や「鍛え」は古い教育であり、これからは「優しさ」や「温かさ」こそが大切なのだと考えてはいないか。
苛めをするなと口では教えるが、「苛めなどをしたら唯ではおかないぞ」という、強い正義感に基づく真剣かつ恐怖を伴うまでの教育をする教師がいない。子供にとっては、どこを見ても「恐い」ものがない。このようなぬるま湯的な教育の中で、悪の芽を伸び伸びと伸ばしていく不幸を、体を張って教えてくれる教師がいない。そういう教師は、むしろ排除される。
子供の主体性、自主性、個性を尊重し、多様な価値観や立場を認めるという美辞の下に、子供の我侭や独断や偏見や利己心を最大限に許し、認め、妥協をし、その場、その時をやり過ごす。そういう教育界の歪みや保身が子供を不幸に追いやってはいないか。体のいい上辺の優しさや大らかさが教育界に日常化してはいないか。
「こども真ん中社会」「常にこどもの最善の利益を第一に」などという甘い、美しい言葉で、本物の逞しい人間としての教育ができるのか。
本質的に、「無知、未熟」の子供らに、必要かつ有効な本物の教育のあり方が戦前と戦後で大きく変わった。戦前の子供は「親や先生の言いつけを守れ」と教えられた。戦後は「子供の主体性」が重視され、親や教師は支援者に退いた。さて、どっちが子供を本当に幸せにすることができたのだろうか。引き続き考えてみたい。

イラスト/すがわらけいこ 写真/櫻井智雄

