学級の荒れを未然に防ぐ ユニバーサルデザインの学習環境づくり|新任教師のための学級経営講座 #3

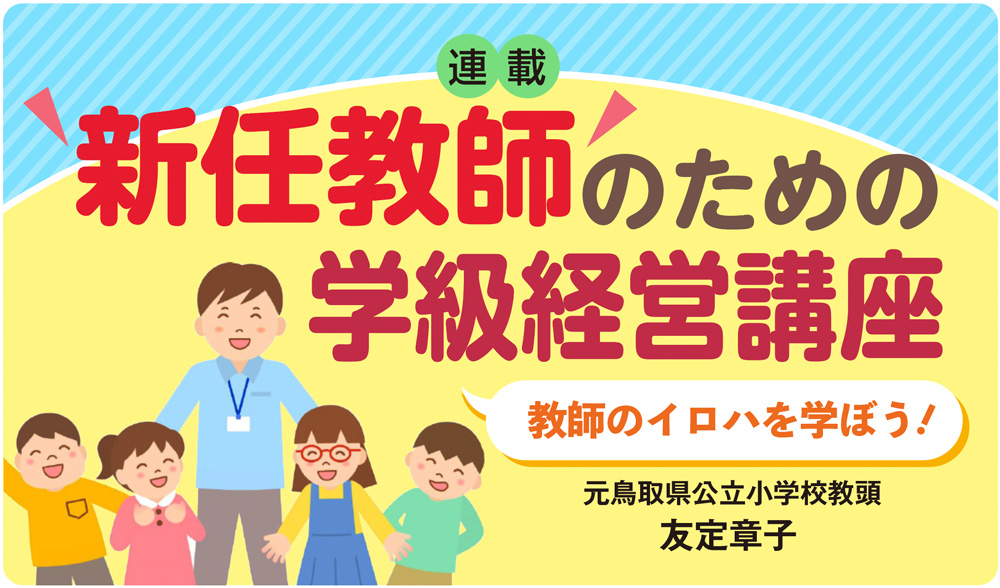
初めて学級担任になった新任教師にとって、「学級経営」は不安なもの。そこで、学級経営の基本が学べる連載をお届けします。毎月の準備や進め方などをその月の学校行事なども絡めながら紹介。鳥取県の公立小学校で、若手教師の育成に尽力してきた友定章子先生が、新任教師でも分かりやすいように解説します。今回は、教室環境とユニバーサルデザインの環境について考えます。
執筆/元鳥取県公立小学校教頭・友定章子
目次
トラブルが多くなる「魔の6月」

学校現場で語られる「魔の6月」という言葉を知っていますか?
6月は、夏を前に気温も高くなり、ジメジメしていて体のだるさを感じる季節です。その上、水泳の学習も始まり集中力が切れやすくなる季節でもあります。子供たちは学級の生活に慣れてきたのに、なぜか落ち着きがなくなり、子供同士の軋轢が表面化したり、いたずらやいじりが増えてトラブルが多くなったりします。そして、教師も子供も他の学級と比較して不満を言い出したりします。
また、運動会や学習発表会等の、大きな行事に向けてがんばった後、喪失感を抱いたり目標を失ったりして、子供たちの気持ちの方向性が急にバラバラになり、勝手な行動が目に余る時期でもあります。反面、子供たちのあり余るエネルギーに対応する教師のエネルギーは減り、疲労感はマックスなのに、解決しなくてはならない問題が次から次へと起きていきます。考えた解決策は結果につながらず、疲弊感と徒労感だけが大きくなっているように感じるでしょう。
「私の力ではどうにもならない!」と叫びたくなっているかもしれません。でも、そう感じているのは、決して若い先生ばかりではありません。どの先生も大なり小なりそんな思いを感じています。即効性のある解決策などあろうはずがありません。
それなら、少し視点を変えてみましょう。問題が起きることは仕方ないとして、問題の数を少しでも減らす、その問題が大きくなる前に手を打つことを意識するのです。
私の場合、
・ユニバーサルデザインの学習環境づくり
・子供との関係づくり
・カウンセリング
・楽しい学習のための教材研究
・養護教諭との連携
に力を入れていました。
その中から、今回は、ユニバーサルデザインの学習環境づくりについて取り上げます。
整った教室環境があってこそ、子供は安心して学習できる
ユニバーサルデザインの学習環境づくりには、2つの側面があります。1つは、学習に集中して臨めるようにするための環境づくり(教室環境づくり)。そして、もう1つは、どの子も学習に向かえるようにするための学習環境づくり(ユニバーサルデザインの環境づくり)です。

1つ目の教室環境づくりとして真っ先に考えるのは、黒板です。白くなっていたり、書いた文字がきちんと消されていなかったりすると、子供たちはげんなりします。また、チョークを置く受け皿が白い粉だらけだったり、黒板下の床が真っ白になっていたり、消したチョークの粉が横の棚に残っていたりする学級は、落ち着きがないことが多いものです。
黒板だけではありません。ゴミ箱がいっぱいになっていたり、鉛筆や消しゴムがあちこちに転がっていたり、掲示物の画鋲が取れかけていたりしたら、子供たちが学習に集中できるはずはありません。また、一人一人の引き出しやロッカー、傘や雑巾などが整理されていない学級も落ち着きがないことが多いと言われています。
街の落書きがある場所やごみが落ちている場所は治安が悪くなるということと同じです。学習する教室の環境が雑然としているようでは、子供たちの心も雑然としてしまいます。
子供たちが帰った後、黒板を一定方向(上から下に)で消し直したり、机を整頓したり、プリント類の書類棚や画用紙の棚をきちんと整理したりすることをお勧めします。
私は、教室の自分の机の中も戸棚の中も子供たちに分かるように整理整頓していました。そして、教室に観葉植物や花を飾ります。居心地のよい喫茶店や職場環境がよいとされるオフィスには、必ず観葉植物が置いてありますよね。人間が吐き出す二酸化炭素を吸って、酸素を供給してくれる植物のおかげだからでしょう。子供たちの心も緑があると落ち着きます。
私が置いていたのは、管理しやすいポトスやアイビー、パキラなどです。100円ショップでも小さなものが売っています。1週間に一度水を上げるだけで大丈夫です。
このように、きちんと整った教室環境の中でこそ、子供たちは学習に集中できるのだと思います。そうは言っても散らかってしまうのが教室です。定期的に教室の環境をきれいにするよう呼び掛けたり、子供たちの机の中やロッカーの中を整頓する時間を設けたりしていました。身の回りの整理整頓が心を整えることにつながると感じます。

