教師の職業がおもしろいわけとは?「教師という仕事が10倍楽しくなるヒント」きっとおもしろい発見がある! #24

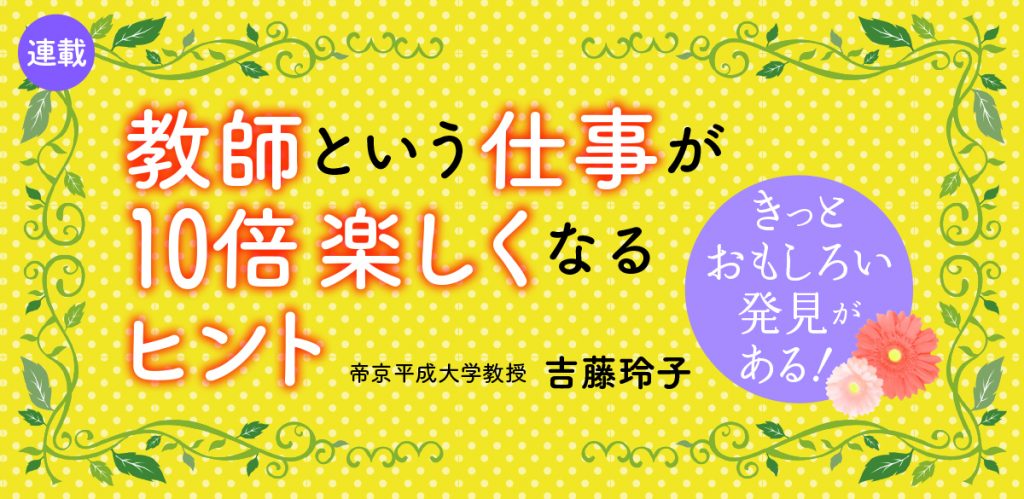
「教師という仕事が10倍楽しくなるヒント」の24回目のテーマは、「教師の職業がおもしろいわけとは?」です。教師という職業は大変には違いないのですが、どの職業も大変なところがあります。教師という職業は、大変なこと以上に魅力的なところがたくさんあり、そこを再認識してはいかがでしょうかという話です。

執筆/吉藤玲子(よしふじれいこ)
帝京平成大学教授。1961年、東京都生まれ。日本女子大学卒業後、小学校教員・校長としての経歴を含め、38年間、東京都の教育活動に携わる。専門は社会科教育。学級経営の傍ら、文部科学省「中央教育審議会教育課程部社会科」審議員等、様々な委員を兼務。校長になってからは、女性初の全国小学校社会科研究協議会会長、東京都小学校社会科研究会会長職を担う。2022年から現職。現在、小学校の教員を目指す学生を教えている。学校経営、社会科に関わる文献等著書多数。
目次
教師という職業はやっぱりおもしろい!
先日、ある人から「よく40年近くも教師という職業を続けてきましたね。大変だったでしょう」と言われました。そんなに大変だったかな? その時々で大変だったこともたくさんありましたが、「ともかく駆け抜けてきたなあ」というのが実感です。
世の中の教師や教育現場に関わる情報を見聞きして、一般の他の仕事をしている人は、教師とは大変な仕事だと思われているのかもしれません。どんな仕事でも大変なことはあると思うので、私は教師だけが特別に大変な仕事だとは考えていません。むしろ「楽しかった」からできたのだと思います。つらいことが先に来ていたら、途中でやめていたでしょう。では、何が楽しかったのか? それは、振り返ってみると、「教えること」「人との関わり」が楽しかったのだと思います。

卒業生との関わり
小学校のときの卒業生との関わりについては、この連載の最初の回に書きました。今でも何人かが近況をSNSで教えてくれています。そして現在、大学で教えていてもやはり卒業生との関わりを楽しんでいます。先生を目指して巣立っていった学生、理想と違って悩んでいる学生の相談にも乗っています。
偶然、人権メッセージの発表会場で、自分のクラスの子供の発表を参観に来ていた卒業生と会ったこともあります。「大丈夫? ちゃんと担任しているの?」の会話から始まり、近況報告をいろいろと話してくれました。自分の人生は一度しかなく、できることも限られていますが、いろいろな人の人生と関われることのおもしろさが教師という職業にはあると思います。教え子との出会いをこれからも大切にしていきたいと思います。

