子供たちと読みたい 今月の本#1 どんな出会いが待っているかな?

今月から全国SLA学校図書館スーパーバイザー・石橋幸子先生にすてきな本を紹介していただく新連載が始まります。1回目のテーマは、「どんな出会いが待っているかな?」です。子供たちがいろいろな出会いの場面に遭遇する様々な本を紹介します。どの本にも子供たちへの応援メッセージが込められています。子供たちの1人読み、先生が読む、読み聞かせなど学級の実態に合わせてください。
監修/全国SLA学校図書館スーパーバイザー・石橋幸子

目次
絵本
絵本は低学年のものと決めつけないで、中学年、高学年の子供たちにもおすすめです。成長段階によって、それぞれの感じ方があるので、その気持ちを大切にしてください。
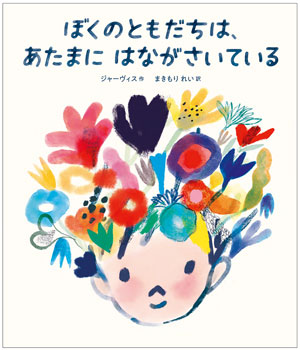
『ぼくのともだちは、あたまに はながさいている』
作/ジャーヴィス 訳/万木森 玲
岩崎書店刊(発行:2023年)
ぼくの友達デイビッドは、頭に花が咲いています。でも、ある日その花が散ってしまいます。そのわけは問わず、悲しそうな友達のために胸を痛め、どうすればいいかを考えます。共感すること、友達にやさしい気持ちで寄り添うことを、小さな子供にも分かるように描いた絵本。
石橋先生のおすすめポイント
題名と表紙を見て、「どういうこと?」と思います。お話の発想がとてもユニークで引き込まれます。どうなるのかとハラハラするのはきっと子供も先生方も一緒です。ひらがなとかたかなだけの表記なので、低学年の子も1人で読めますが、みんなで迫力ある絵を楽しみながら読み聞かせてもらい、わくわくする思いを伝え合ってください。友達を思うやさしい気持ちに共感できるでしょう(全学年向き)。
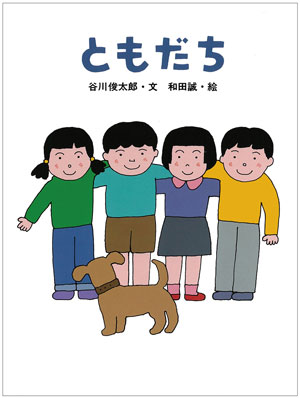
『ともだち』
文/谷川俊太郎 絵/和田 誠
玉川大学出版部刊(発行:2002年)
谷川俊太郎の珠玉の詩と、和田誠のほのぼのとしたイラストによる絵本。よい友は一生の宝であり、生きていくうえで友達がいかに大切かということを、やさしい言葉と楽しい絵によって小さい子にも分かりやすく語りかけます。
石橋先生のおすすめポイント
1行か2行の谷川俊太郎さんの詩に見開きいっぱいのイラスト。いろいろな「ともだち」の姿が描かれていて、誰にもきっと自分に当てはまる場面があります。自分だったらどうするかということを子供たちが考えるきっかけにつながります。全文ひらがななので、1年生から1人で読めます。学年が上がった子供が読むとまた違う思いを抱けるのが魅力です(全学年向き)。
読み物
なかにはルビがなくて、小学生には難しいものもありますが、先生が手助けをしながら挑戦を試みてください。子供たちが本好きになるきっかけになることでしょう。
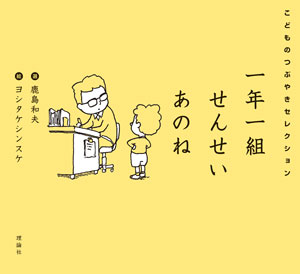
『一年一組 せんせいあのね』
選/鹿島和夫 絵/ヨシタケシンスケ
理論社刊(発行:2023年)
担任の鹿島和夫先生と小学1年生の子供たちとの、いわば交換日記の「あのね帳」。そこから54篇のつぶやきをセレクト。子供たちから生まれた生の言葉がヨシタケシンスケさんの絵とタッグを組み、新たに心を揺さぶります。
石橋先生のおすすめポイント
大好きな家族のこと、愉快な学校での出来事、季節のうつろいなど、1年生ならではの感性に感心したり、くすりと笑ったり……。1年生のときの新鮮な気持ちが伝わってきます。子供たちにその真新しい気持ちを思い出してほしい。ヨシタケシンスケさんのイラストが楽しいのです。どの学年にも、もちろん先生方にもおすすめです(全学年向き)。
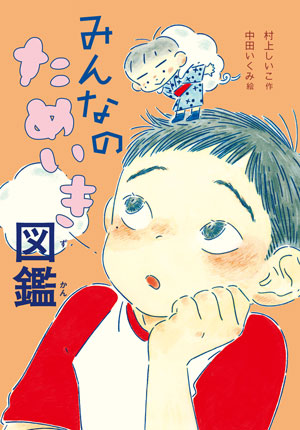
『みんなのためいき図鑑』
作/村上しいこ 絵/中田いくみ
童心社刊(発行:2021年)
授業参観に向けて、主人公のたのちんの班は「ためいき図鑑」をつくることになりました。いっしょの班の保健室登校の加世堂さんもいっしょに図鑑をつくれないかと、たのちんがある提案をしたところ、班のほかのメンバーともめてしまい……ため息ばかり! 家族や友達との関係に揺れる子供の気持ちを、鮮やかに描いた物語。
石橋先生のおすすめポイント
作者の村上しいこさんは読みやすく楽しい話をたくさん書いていますが、この本も題名からしてちょっとびっくりです。そして楽しさを倍増させてくれるのが、中田いくみさんの挿絵。溜息から生まれた「ためいきこぞう」。主人公たのちんとためいきこぞうの会話も関西弁でリズミカルで愉快です。どうやって「ためいき図鑑」ができあがるか、笑いながら読めます。最初の部分やためいきこぞうが登場した場面はぜひ読み聞かせてあげてください(中学年向き)。
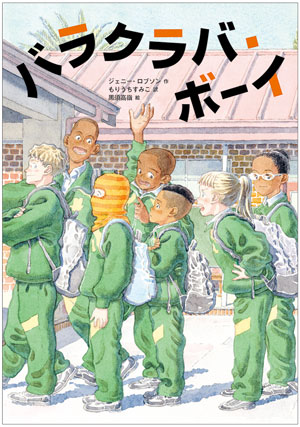
『バラクラバ・ボーイ』
作/ジェニー・ロブソン 訳/もりうちすみこ 絵/黒須高嶺
文研出版刊(発行:2024年)
バラクラバ帽(目出し帽)をかぶった転入生のトミーがやってきました。なぜトミーは帽子をかぶっているの? あの帽子の下には何がかくされているのか? ぼくとドゥミサニの退屈な日々は、「バラクラバ・ボーイ」によって大きく変わって……。
石橋先生のおすすめポイント
まず、表紙と裏表紙を広げて見てください。黄色とオレンジ色の目出し帽をかぶったのが転校生の「バラクラバ・ボーイ」。並んだ子供たち。なんだかとても個性的で楽しそうです。作者はボツワナの方なので、南アフリカの学校が舞台かもしれません。とにかく子供たちの行動、考えることが面白い。国が違っても子供たちの行うことは似ているようです。そして、最後はあっと‼︎(中学年向き)。
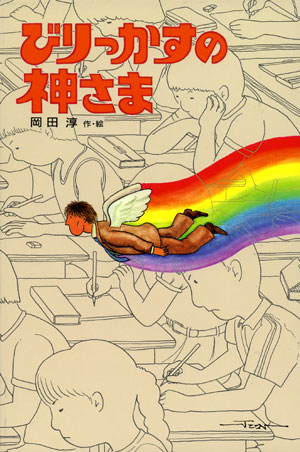
『びりっかすの神さま』
作・絵/岡田淳
偕成社刊(発行:1988年)
成績順で席が決まるクラスに転校してきた始。そこで、始は背中につばさのある男を目撃します。その男はびりの人にだけ見える神様でした。やがて、子供たちは競争や勝ち負けについて考え始めます。一番になるより大切なことを描いた物語。
石橋先生のおすすめポイント
神戸の図工の先生だった岡田淳さんがお話を作り、絵を描いています。ありえない座席の座り方、見えるはずないものが見える状況の物語にぐんぐん引き込まれます。バラバラだったクラスが次第にまとまっていきます。「自分たちのクラスと比べるとどうかな」という見方もできます。物語は14章に分かれているので、1章を読み聞かせても10分程度です。毎日1章ずつ読み聞かせても、最初だけ読んで手渡してもよいですね(中学年以上向き)。
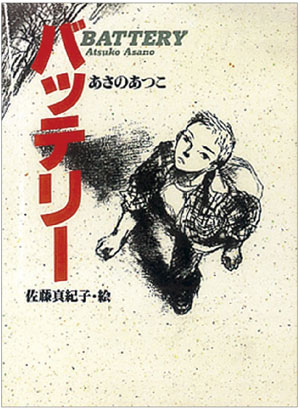
『バッテリー』
作/あさのあつこ 絵/佐藤真紀子
教育画劇刊(発行:1996年)
ピッチャーとして絶対の自信をもち、誰に対しても我を通そうとする巧と、その才能に強く魅かれていく豪。2人は出会い、バッテリーを組み、2人の人生が始まっていきます。最高に熱い物語。
石橋先生のおすすめポイント
30年近く前に出版されて、長く読み継がれてきた物語。野球をよく知らない子でもバッテリーを組む巧と豪の世界に引き込まれます。中学校に向けての話で、チームプレーや固い絆の友情など子供たちの心に響くことでしょう。高学年の子供たちに挑戦してほしい物語です(高学年向き)。
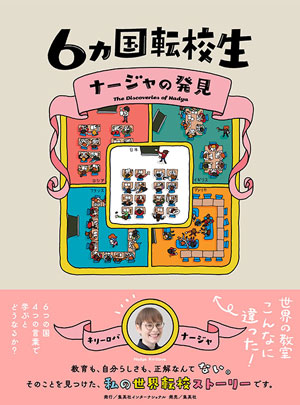
『6カ国転校生 ナージャの発見』
著/キリーロバ・ナージャ
集英社インターナショナル刊(発行:2022年)
ソ連(当時)に生まれ、両親の転勤で世界6か国(ロシア、日本、イギリス、フランス、アメリカ、カナダ)に転校。各国の地元校で教育を受けた著者ナージャの稀有な経験を楽しく追体験! 机の並べ方、筆記用具、テスト、ランチ……世界の教室はこんなに違った! 「ふつう」がひっくり返り、世界の見え方が変わります。
石橋先生のおすすめポイント
日本の学校の当たり前が通用しない。よいなあと思うことがたくさんあるかもしれないし、日本の学校のほうが勉強しやすいと思うかもしれません。初めて知ることが多くて「へえー、そうなんだ」と思うことばかりです。ルビがほとんどないので、先生が部分的に紹介したり、読み聞かせたりするのもおすすめです(高学年向き)。
● ● ●

石橋幸子先生からのメッセージ
子供たちも先生たちも新たな気持ちでスタートする春。「どんな友達と一緒になるかな」「先生はどんな人かな」と子供たちの心はドキドキでしょう。また、転校して新しい学校に仲間入りした人もいるかもしれません。そんな子供たちに、素敵な友達やちょっと変わった先生が登場する本を紹介します。面白い転校生の話もあります。子供の心情を生き生きと描いた絵本、教室の様子が伝わる楽しいお話など、どの本もこの時期の子供たちを応援してくれます。グレードが「全学年」という表示になっている本は、低学年のほか中高学年の子供たちにも読み聞かせたり、紹介したりしてあげてください。中高学年向きの本でも最初の数ページを読み聞かせてあらすじを紹介すると手に取る子が増えますよ。学校図書館の蔵書にない場合は今年度の購入計画に加えてください。そしてぜひ子供たちに一言を添えて、手渡してあげてくださいね。
監修
石橋幸子(いしばしさちこ)
全国SLA学校図書館スーパーバイザー
東京学芸大学非常勤講師、明星大学非常勤講師、和洋女子大学非常勤講師
長年、東京都の小学校教員を務める。また司書教諭として全教員が学校図書館を授業に活用することを目標として学校図書館を経営。退職後は大学で司書教諭の資格を取得する学生を指導。本を読むことも本で調べることも大好き。もっと心が躍るのは楽しい本を子供たちに手渡すこと。本連載が、先生方と子供たちの本の架け橋になればうれしい。
取材・文・構成/浅原孝子
授業で使える312冊の絵本を紹介
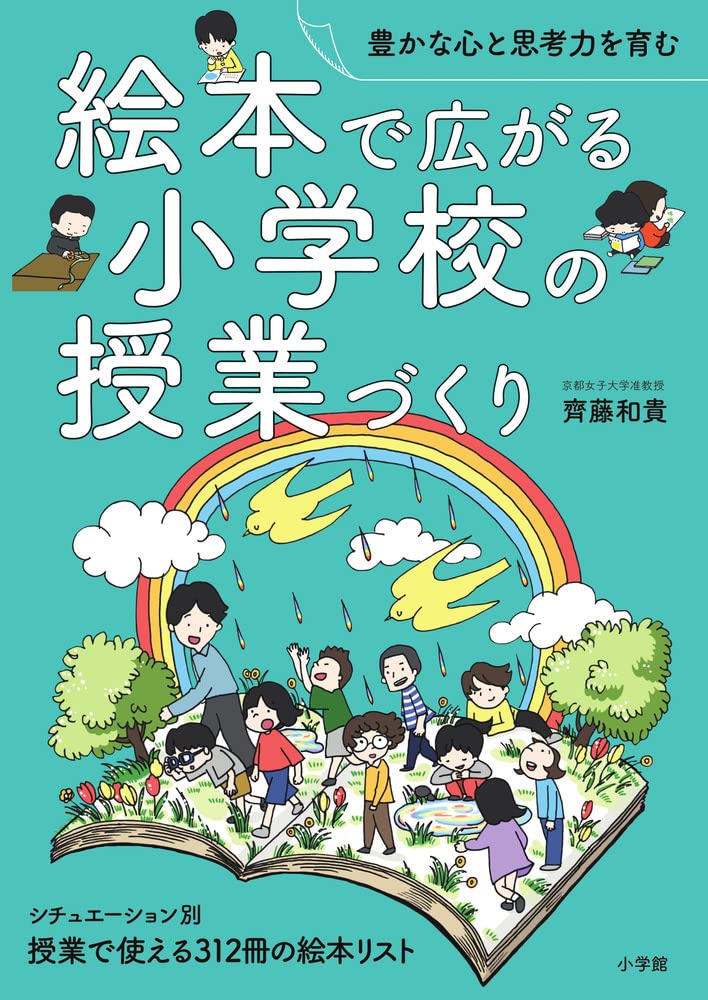
著/齊藤和貴(京都女子大学教授)
司書教諭の経験を生かしながら、長年、学校現場で「絵本を活用した授業」を行ってきた元小学校教諭が、小学校の授業で使える絵本312冊を厳選。絵本を使った実際の授業が、板書や指導案、豊富な写真とともにオールカラーで具体的に紹介されていますので、授業の進め方がよく分かります。
B5判/112頁
ISBN9784098402212
〈著者プロフィール〉
齊藤和貴(さいとう かずたか)
京都女子大学発達教育学部准教授。元小学校教諭・司書教諭。東京都公立小学校及び東京学芸大学附属小金井小学校、附属世田谷小学校で28年間、教育活動や授業実践に取り組む。その間、生活科や総合的な学習の時間を中心に指導法やカリキュラム、評価方法の工夫・改善を図り、「子供とともにつくる授業」の創造に励む。また、司書教諭の経験を生かし、「絵本を活用した授業づくり」にも取り組んできた。

