子どもにとっても教員にとっても安心できる学校を目指して…。チーム担任制を考えてみませんか?
- 連載
- 大切なあなたへ花束を


子どもたちと教員の関わり方がいま、変革の時期を迎えています。学級担任を一人に固定しないで、複数の教員を設定したり、学年全体を複数の教員で受け持ったり。そんな仕組みを導入する自治体や学校が増えてきているのです。インクルーシブ教育の視点からも有益ですし、教員の負担軽減にもつながりますよ、と宮岡先生は語ります。宮岡先生は木村泰子先生に師事し、現在は「みんなの学校マイスター」として講演活動や各校の支援で大活躍中です。
【連載】大切なあなたへ花束を #14
執筆/みんなの学校マイスター・宮岡愛子
チーム担任制の交流研修会で考えたこと
いま、チーム担任制が大きな注目を集めています。子どもへの対応の方法についても、先生たちのよりよい働き方のためにも、メリットが大きいとの実証結果がたくさん上がってきています。
チーム担任制(学年担任制・複数担任制)とは、学級担任を1年間固定せずに、複数の教員が一定期間で交代する仕組みです。
教員に学年の児童生徒全員を見ることを意識づけ、同じ学年だけではなく、複数学年にわたって担任をすることもあります。
私が自分の学校で実際に取り組んだのは、学年チーム担当制でした。
まず名称を「担任」ではなく、「担当」に変えました。学級担任制をやめ、それぞれの学年を担当する教員を2人以上設定し、それぞれがチームになって関わるようにして、学年の子どもを多くの担当で見ていく方法でした。(その詳しい方法については、こちらの記事をご覧ください)
さて最近、私は、チーム担任制にとりくんでおられる兵庫県明石市の貴崎小学校で開かれた、交流研修会に参加してきました。
なんとこの学校、学級担任を1週間ごとに交代しているのです。すなわち、それぞれのクラスに、担任としていろいろな先生が入ることができるのです。
「すごいやん、進んでるやん!」
と正直思いました。私はそこまではできなかったからです。
しかも当該校(貴崎小学校)の校長である中野裕香子先生は、
「みなさん、どんどん(意見を)出し合いましょう、そして、どうしたら進んでいけるかを考えましょう」
と前向きな姿勢です。なんて素敵な言葉でしょう。正解はありません。校長も答えをもっているわけではないのです。全員一丸となって、学校を進めていこうという熱い思いを感じました。
外部から参加した先生たちの間からは、
「教員それぞれのやり方が違っていいの?」
「きちんと子どもを指導できる人が負担になるのでは?」
「何もやらない人が増えるのでは?」
「ルールが徹底しにくいのでは?」
「責任があいまいになるのでは?」
などといった意見が出ました。
でも、これらの疑問は、裏をかえすと…。
「教員はみな同じやり方で、同じように指導をしましょう」
「仕事の量は同じにしましょう」
「みんなで同じルールを守らせるようにしましょう」
「あなたの失敗は、あなたがとってね」
といった、教員の同質化が必要だと思っている人が多いのかな? そんなことを考えていました。
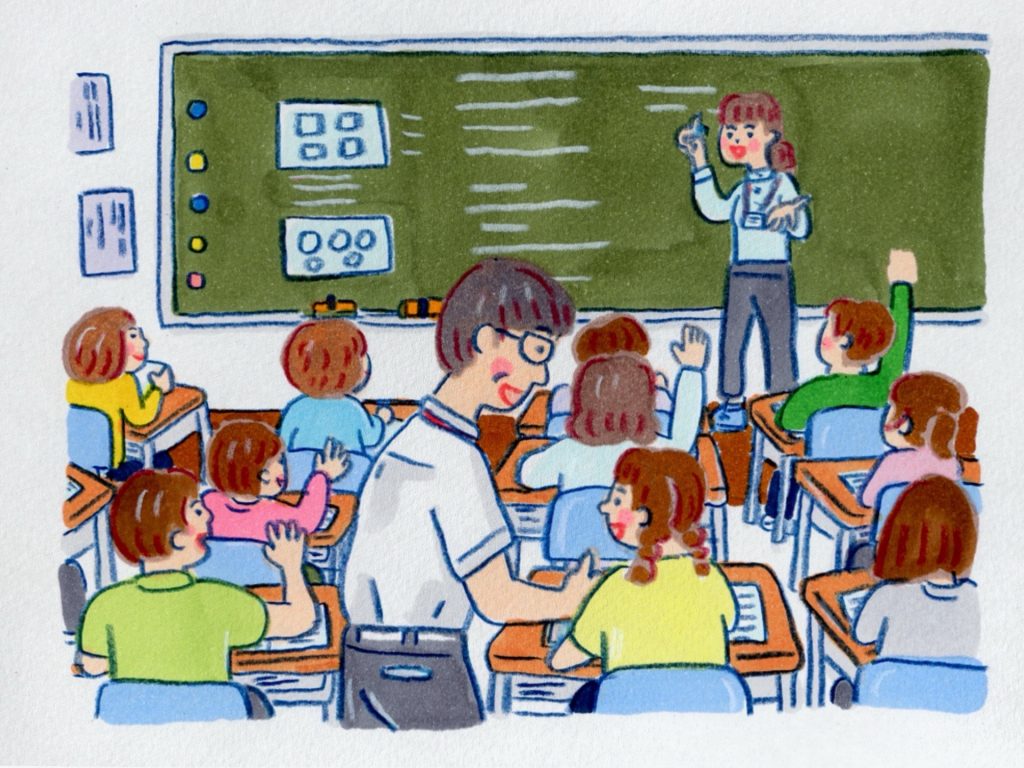
はたして、教員の同質化は必要なのでしょうか? そもそもそれは可能なのでしょうか?
今、私がサポーターとして関わっている学校は、学級担任制です。各学年に3~4クラスある、大きめの中規模校です。
だいたいどの学校も同じだと思いますが、その学校でも教員の年齢的なバランスを整えるかのように、1学年に、中堅ぐらいの教員、1年目の全く初めての教員、若手の教員、年配の教員が配置されています。
しかし、学級担任制の場合、年齢も性別もバラバラな先生を配置する意味はあるのでしょうか? そして、もしも子どもと担任の相性が悪かった場合…。子どもが悩みをもったとき、他のよく知らない先生に気安く相談できるはずはありません。保護者だってそうです。
子どもも大人も、誰に相談するか選択できるところに安心感が生まれるのではないでしょうか。
また一方で、教員の方も悩み事が増えるのではないでしょうか。特に若手の教員は、悩みを一人で抱え込んでしまうのではないでしょうか。他の先輩に相談したとて、しょせんその先輩にとっては、よそのクラスの子どもと先生の問題です。我がこととして考えてくれなかったり、あるいは相談する人によってバラバラの答えが返ってくることもあるでしょう。
私の娘が小学生だったころ、娘の担任の先生と合わずに悩んだことがありました。隣のクラスだったら、もっと子どもは伸びたかもしれないな…。そして、もし隣のクラスの先生に相談したとしても、どうせ担任にも伝えてください、と言われるのだろうな…。
そんなことを考えてしまったことを思い出してしまいました。
研修会のディスカッションでは、チーム担任制の成果と課題点についての意見交換があり、以下のようなことが挙げられました。
チーム担任制の成果
・学級差を軽減することができている
・学級崩壊のリスクを減少させることができている
・複数の目で観察でき、変化に気づく機会が増えている
チーム担任制の課題
・情報の引き継ぎが難しいときがある
・責任の所在が不明瞭になってしまう
・外部から見て、教員の代表者がわかりにくくなる
この成果と課題を読まれてどう感じられますか?
成果の前につく言葉は、すべて「子どもの」「子どもを」です。一方で課題の前につくのは「教員の」ではないでしょうか?
そうです。チーム担任制の悩みやデメリットはすべて、教員たちの考え方一つで解決できるものばかりなのです。私たちが今問われていることは、子どもを主語にデメリットをメリットに変えていくことなのです。
例えば、教師を主語にして考えると、チーム担任で多人数がクラスに関わることで、1人の教員と1人の子どもの関係性は薄くなるかもしれません。
しかし、子どもを主語にして考えてみましょう。その子は、1人ではなく多くの教師と関われます。自分に合った、安心できる相手を選びやすくなるでしょう。
子どもの情報量が多くなることは教師にとって負担になるかも知れません。しかし裏をかえせば、それだけそれだけたくさんの子どものことを知ることができる、ということです。
学級担任制、固定された担任制で同調的に指導をするのではなく、教員それぞれが個々の強みを生かし、補い合える大人のつながりをつくること。それが、子どもに見せるべきものなのです。
教員同士が風通しよく何でも話せる環境づくり。そして、責任はみんなで…というチーム力。すべての子どものことを我が事として捉える当事者意識が必要だと言えるのではないでしょうか。
最後に、今回拝見した交流研修会のまとめとして、中野裕香子校長先生が書かれた文章を紹介します。
チーム担任制は、子どもの多様性が尊重される策(多様な子どもが生きやすい策)であると共に、担任業務を担う教員をはじめ様々な職種で構成されるチーム学校に関わる全ての大人にとっても、多様性に出合う仕組みの一つである。
決して学級担任制よりチーム担任制が良いという論ではない。チーム学校の一環にチーム担任制を工夫して取り入れることで、教職員がチームを組み異なる視点を用いて不登校・いじめなどの子ども支援や子どもの多様性への理解・配慮のある学習指導を行うことができたり、子ども・教職員・保護者・地域住民のみんなで「学校とは」と問い直すことができたりと、チーム学校の仕組みに潤滑をもたらし、子どもや教職員の心理的安全性の向上、メンタルヘルスの保持やエージェンシー(自律・自立に向かう子ども)の育成、延いては、それぞれの人のウェルビーイングに繋がる可能性を、本研究の過程から見出せる。 チーム担任制を手段として、多様性に出合い自分なりのものの見方や考え方を構築し、互いに助け合い、自律と自立に向かう子どもをみんなで育む学校が、チーム学校のひとつの在り方であると言え、チーム担任制を介することでチーム学校としての質の向上が期待できる。
子どもの自殺527人は過去最高、子どもの不登校も過去最高。子どもが安心できる取り組みを学校がつくることは今、最も必要なことです。学校を変えることは社会を変えることにつながります。
私は、(木村)泰子さんと同じ学校だったときに、学年4クラスの担任が学年全部の子どもを見る教科担当制を取り入れました。方法はそれぞれですが、「すべての子どもをすべての教員で見る」という目的を大切にやり切りました。子どもは子どもでいろいろな先生との出会いを楽しみにしていました。そして教員もお互いの弱みをカバーし、強みを出し合うことができました。必要であれば、学年だけでもやることができるのです。あとは、やるかやらないかの、ご自身の決断だけです。
今年度も終わり。来年度が楽しみになる今日このごろです。
イラスト/フジコ

宮岡愛子(みやおか・あいこ)
みんなの学校マイスター
令和7年度あかし教育研修センタースーパーバイザー。社会教育士。私立の小学校教員として教職をスタートするが、後に大阪市の教員となり、38年間務める。教員時代に木村泰子氏と出会い、その後、木村氏の「みんなの学校」に学ぶ。大阪市小学校の校長としての9年間は「すべての子どもの学習権を保障する」学校づくりに取り組んだ。現在は、「みんなの学校マイスター」として活動している。

