ぜひ、他校種の学習指導要領も見ていただきたい【中教審レポートと関係者インタビューで綴る 次期学習指導要領「改訂への道」#03】
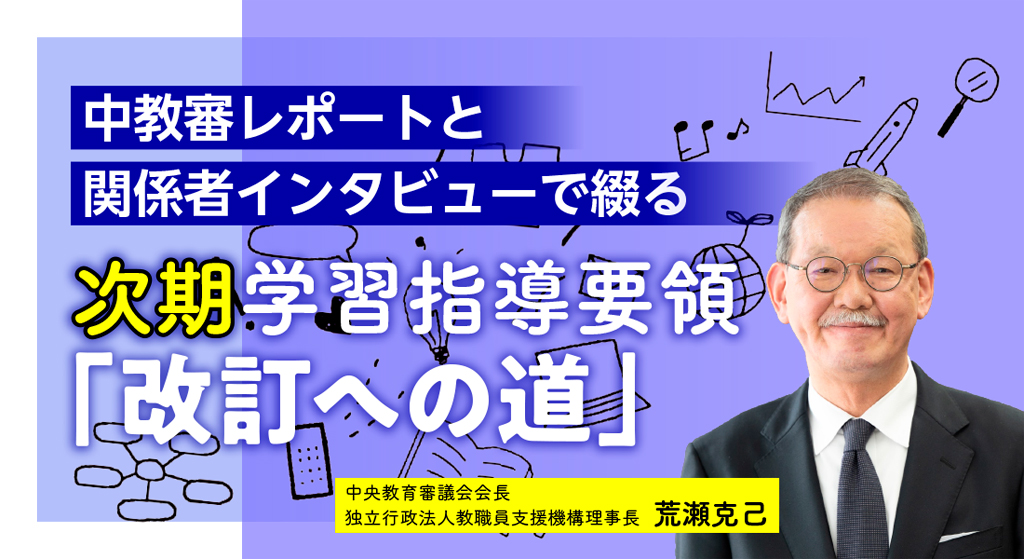
前回は、中央教育審議会(以下、中教審)の会長である、独立行政法人教職員支援機構の荒瀬克己理事長に、今回の諮問文には表れていない重要なポイントなどを中心にお話を伺いました。最終回となる今回は、今後の改訂に向けた議論を見守りつつ、自校の教育を考えていくことになる小中学校の先生方へのメッセージや、今後の改訂に向けて望むことなどを紹介していきます。
目次
中学校では、一人一人の子供のもつ内面の純粋さに目を向けて
どなたにも、幼稚園から高等学校までのすべての学校段階の学習指導要領総則について、目を通していただきたいと思っています。まずはご自身の関わる段階のもの、そして、その前後の段階のもの。そして、初等中等教育全体を見渡す。それによって、発達や成長がどのように捉えられているかが分かります。そこから、現状の把握と課題の発見が始まると思います。
例えば小学校の先生は、幼稚園教育要領と中学校の学習指導要領を、少なくとも総則の部分はぜひ見てください。
幼稚園教育要領には、学びが遊びを通してあるのだということがていねいに説明されています。そして、「幼児期が終わるまでに育ってほしい10の姿」が示されていますが、これはとても感動的です。「⑴健康な心と体」〜「⑽豊かな感性と表現」という10の姿は、義務教育を終え、高校生になった時点でも、はたして身に付いているだろうか、大人でもむずかしいかもしれないと思えることが書いてあります(資料参照)。
【資料】幼児期の終わりまでに育ってほしい(10の)姿(幼稚園教育要領より抜粋)
⑴ 健康な心と体
(幼稚園教育要領より抜粋)
幼稚園生活の中で、充実感をもって自分のやりたいことに向かって心と体を十分に働かせ、見通しをもって行動し、自ら健康で安全な生活をつくり出すようになる。
⑵ 自立心
身近な環境に主体的に関わり様々な活動を楽しむ中で、しなければならないことを自覚し、自分の力で行うために考えたり、工夫したりしながら、諦めずにやり遂げることで達成感を味わい、自信をもって行動するようになる。
⑶ 協同性
友達と関わる中で、互いの思いや考えなどを共有し、共通の目的の実現に向けて、考えたり、工夫したり、協力したりし、充実感をもってやり遂げるようになる。
⑷ 道徳性・規範意識の芽生え
友達と様々な体験を重ねる中で、してよいことや悪いことが分かり、自分の行動を振り返ったり、友達の気持ちに共感したりし、相手の立場に立って行動するようになる。また、きまりを守る必要性が分かり、自分の気持ちを調整し、友達と折り合いを付けながら、きまりをつくったり、守ったりするようになる。
⑸ 社会生活との関わり
家族を大切にしようとする気持ちをもつとともに、地域の身近な人と触れ合う中で、人との様々な関わり方に気付き、相手の気持ちを考えて関わり、自分が役に立つ喜びを感じ、地域に親しみをもつようになる。また、幼稚園内外の様々な環境に関わる中で、遊びや生活に必要な情報を取り入れ、情報に基づき判断したり、情報を伝え合ったり、活用したりするなど、情報を役立てながら活動するようになるとともに、公共の施設を大切に利用するなどして、社会とのつながりなどを意識するようになる。
⑹ 思考力の芽生え
身近な事象に積極的に関わる中で、物の性質や仕組みなどを感じ取ったり、気付いたりし、考えたり、予想したり、工夫したりするなど、多様な関わりを楽しむようになる。また、友達の様々な考えに触れる中で、自分と異なる考えがあることに気付き、自ら判断したり、考え直したりするなど、新しい考えを生み出す喜びを味わいながら、自分の考えをよりよいものにするようになる。
⑺ 自然との関わり・生命尊重
自然に触れて感動する体験を通して、自然の変化などを感じ取り、好奇心や探究心をもって考え言葉などで表現しながら、身近な事象への関心が高まるとともに、自然への愛情や畏敬の念をもつようになる。また、身近な動植物に心を動かされる中で、生命の不思議さや尊さに気付き、身近な動植物への接し方を考え、命あるものとしていたわり、大切にする気持ちをもって関わるようになる。
⑻ 数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚
遊びや生活の中で、数量や図形、標識や文字などに親しむ体験を重ねたり、標識や文字の役割に気付いたりし、自らの必要感に基づきこれらを活用し、興味や関心、感覚をもつようになる。
⑼ 言葉による伝え合い
先生や友達と心を通わせる中で、絵本や物語などに親しみながら、豊かな言葉や表現を身に付け、経験したことや考えたことなどを言葉で伝えたり、相手の話を注意して聞いたりし、言葉による伝え合いを楽しむようになる。
⑽ 豊かな感性と表現
心を動かす出来事などに触れ感性を働かせる中で、様々な素材の特徴や表現の仕方などに気付き、感じたことや考えたことを自分で表現したり、友達同士で表現する過程を楽しんだりし、表現する喜びを味わい、意欲をもつようになる。
幼児期から青年期への発達段階に応じて、「育ってほしい姿」にどのように育てていくのか、近付けていくのか。それが向き合うべき課題でしょう。出発点は幼児期にあり、そこからの過程が重要です。もちろん、そのあとでやり直せないということではありません。人はいつでも、学べば成長します。ただ、必要な時期に必要な学びを体験するのは、とても大事だろうということです。
令和3年に出された中央教育審議会の答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」には、「子供たちを支える伴走者である教師」、「子供の主体的な学びを支援する伴走者としての能力」といった言葉が出ています。伴走とはどうすることか。いつ、どの場面でするのか。いつまで、どこまでするのか。多様な子供一人一人を主語にして、そういったことを考え、さらに同僚と話し合うのは、重要な教師としての学び、研修です。
中学校では、子供たちが大きく成長し、だからこそ自分の思いをもち、他者や社会に対して反発し、反抗することもあるかもしれません。高校入試や部活動もありますし、また、多様な困難や課題が突き付けられていることもあるでしょう。そのようなむずかしい段階だからこそ、関わる人は、一人一人の子供のもつ純粋さに、ぜひ目を向けてほしいと思います。
中学生、高校生は微妙な年齢ですが、15歳と聞くと、私は石川啄木の「不来方(こずかた)の お城の草に寝ころびて 空に吸はれし 十五の心」という歌を思い出します。もちろん、この歌のようなイメージの子供ばかりではないでしょうが、実はそれぞれの子供に「十五の心」があって、その「十五の心」の手前には「十四の心」「十三の心」があるはずです。それが「十六」「十七」につながっていく。そうした子供それぞれに向き合うのが中学校教育であり、だからこそ集団だけではなく個を気遣い、一人一人の子供のもつ内面の純粋さに目を向けていただきたいと思います。
100%近くの中学校卒業生が高等学校に進学します。初等中等教育の最終段階。社会や高等教育につながっていきます。そのための資質・能力を高校の学習指導要領はどのように捉え、どのように育てようとしているのかということもしっかり見ていただければと思います。
そう考えると、高校入試はどういう在り方がよりよいのか、ということも気になってきます。ぜひ中学校からの視点を発信していただければと思います。例えば、不登校の子供は評定が付けられないため、行ける高校が限られたり、高校に行けなかったりします。本当にそれでいいのでしょうか。子供が楽しく学べる状況をどうつくればよいか。
いま、ウェルビーイングが重視されています。改めて、どうしたら楽しく学校に行けるか、そういう学校をどのようにしてつくるか、子供たちにとっても先生方にとっても、大事な問いかけではないでしょうか。

