川上康則先生講演|「こうあるべきの呪縛」に気づいて〜学校を変えるために必要な常識の転換@北の教育文化フェスティバル
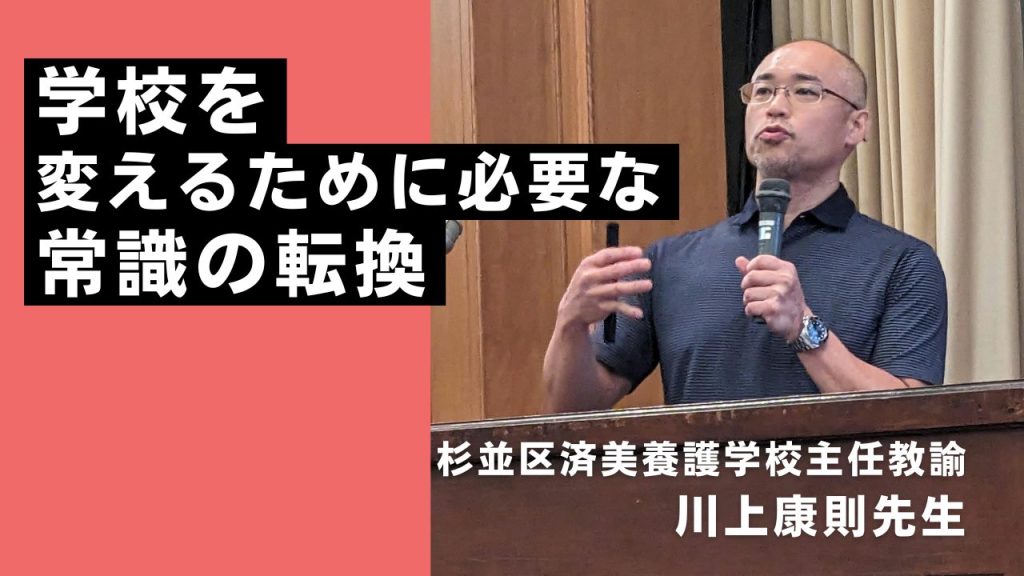
2024年8月10日に札幌市で開催された「北の教育文化フェスティバル」での、川上康則先生による特別支援教育についての講演の後半です。今回は教師の職場環境の話から、意識の持ち方についてお話しいただきました。「そろえる・整える」学校文化から、差異を前提にした文化への転換を提言しています。
取材・構成/村岡明
前半のお話はこちら:
特別支援教育にできること|杉並区立済美養護学校主任教諭 川上康則先生
目次
教師の仕事は「感情労働」
教育現場は「感情労働」の職場です。
教師は日々、子供たちとの関わりだけでなく、保護者との関係づくり、そして職員室での人間関係など、複数の層での感情的な関わりを持つことが求められます。こうした多層的な感情労働の現場では、感情の抑制や忍耐、適度な緊張感が常に必要とされます。
感情労働では、「気持ちの余白」が大切です。子供と向き合う場合であれば、経験によってある程度、気持ちの余白をコントロールできる教師も多いことでしょう。しかし、職員室内の人間関係に関する気持ちの余白を確保することは、どの世代の教師でも困難を感じる課題となっています。
教職を選ぶ人の特徴と潜在的な課題
教職に就く人々には、いくつかの特徴が見られます。まず、比較的真面目な人が多く、人に何かを教えることに喜びを感じる傾向があります。学校への適応度の高い人が多いという特徴も見られます。一見、これらの特徴は教職に適していると思われるかもしれません。
しかし、これらの特徴は同時に、教育現場での課題を生む要因にもなりえます。一般に次のような傾向があります。
- 真面目すぎるがゆえに、「融通が利かない」「善意の押し付けに気付けない」などの傾向
- 教えるのが好きな一方で、人の話は聞かない傾向
- 学校適応度が高いため、学校に馴染めない子供の気持ちがつかめない傾向
- 正直で裏表がない人が多い一方、「話を自分に都合が良いように解釈する」「思っていることをストレートに言い放つ」などの傾向
- チームワークよりも個人での活動を好み、協働・連携・協力には向かない人がいる傾向
これらの特徴は、教師個人の特徴というよりも、この職業を選択した人々に共通して見られる傾向です。これは善いことでも悪いことでもなく、特徴として理解する必要があります。

