川上康則先生講演|特別支援教育にできること〜暴言を吐く子・無気力な子に寄り添う視点@北の教育文化フェスティバル
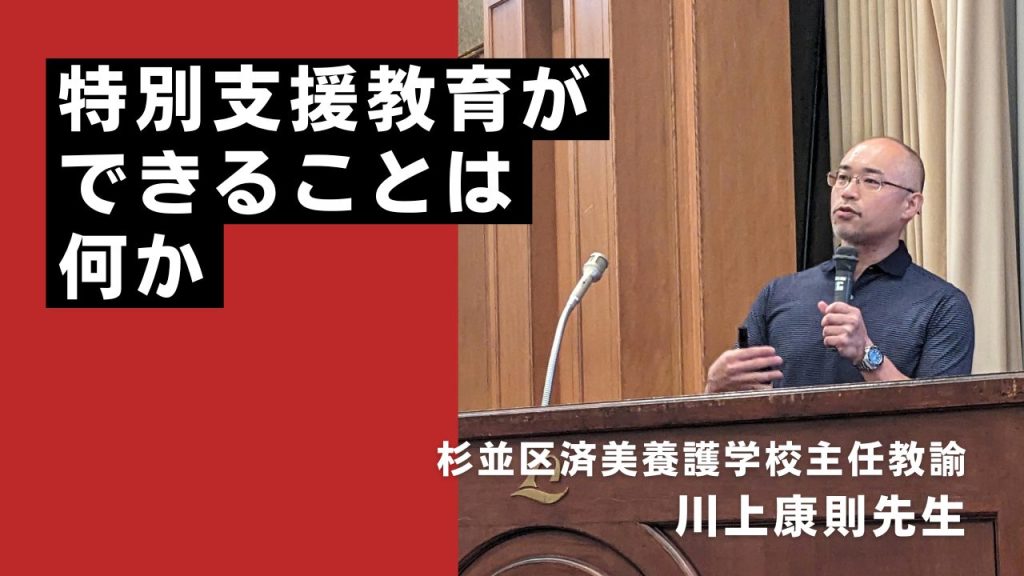
2024年8月10日に札幌市で開催された「北の教育文化フェスティバル」での、川上康則先生による特別支援教育についての講演の内容を2回に分けてお届けします。今回はその前半。暴言を吐いたり、無気力に見えたりする子に寄り添うための視点を、特別支援教育の観点からお話しいただきました。
取材・構成/村岡明
目次
教室が「安全基地」であること
人の意欲の扉は、内側からしか開きません。子供が主体的な行動を起こすには、「安全基地」の役割を果たせる大人が必要です。教室は「わからない」「できない」「難しい」といったことを、気軽に言える場、何かあったときに安心感を与える場である必要があります。この安心感を、「内側から醸し出すことができるか」が教師としての重要なポイントです。
教師には「安全基地」としての2つの重要な機能があります。 一つは「やってごらん」と送り出す役割、もう一つは何かあったときに戻って来られる役割です。この役割は特別なときではなく、日常的に果たす必要があります。
この役割を表す言葉として「オーパッキャマラド」があります。 これは「クラリネットをこわしちゃった」という歌の一節からきています。フランス語で「Au pas, camarade(友よ、一歩一歩行こう)」という意味です。思った音が出ずに焦っている子供に対して、「大丈夫だよ、一つ一つ音が出せるようになろう」と励ます父親の姿勢を表しています。
子供はルールよりもラポールに従う
「指示に従わない」「指導が入らない」などのマイナス表現は、子供の実態を表す言葉ではありません。⼤人側の都合を表した言葉です。
もし「指導が入る」ようにしたいのであれば、子供を変えようとするのではなく、信頼関係(ラポール)作りを意識すべきです。「この先生の話は聞く価値があるな」と思ってもらえなければ、指示も指導も入りません。
そのためには、「あれができない」「これがダメ」などと、子供のマイナス面に目を向けず、良い面を探すようにしましょう。「ないものねだり」よりも「あるもの探し」が大事です。

