「個と集団へのアプローチバランス」インクルーシブ教育を実現するために、今私たちができること #9

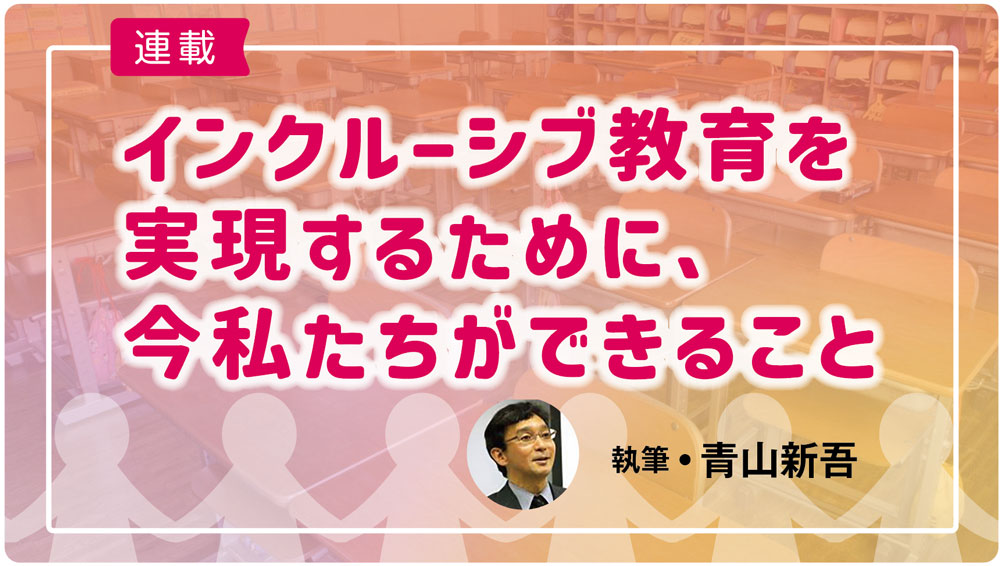
「インクルーシブ教育」を通常学級で実現するためには、どうすればよいのでしょうか? インクルーシブ教育の研究に取り組む青山新吾先生が、現場の先生方の悩みや喜びに寄り添いながら、インクルーシブ教育を実現するために学級担任ができること、すべきことについて解説します。
本連載では、インクルーシブ教育とは、貧困状況にある子どもや性的マイノリティの子ども、外国にルーツのある子ども、不登校の子ども、障害や病気のある子どもなどのマイノリティ属性を含むすべての子どもが対象だとしています。そして、すべての子どもたちが包摂される教育を目指すプロセスがインクルーシブ教育であり、そのためには通常学級の教育をもっと豊かにしていくことが求められているという前提に立っています。
今回は、個と集団へのアプローチバランスについて考えます。
執筆/ノートルダム清心女子大学人間生活学部児童学科准教授・インクルーシブ教育研究センター長・青山新吾
目次
アプローチバランスは難しい
前回の連載第8回では、今、インクルーシブ教育という考え方、言葉が拡がっていること、インクルーシブ教育を進める際、「特別支援教育の視点を取り入れた教育活動」が基盤になることを書きました。通常学級の教育を豊かにすることが、インクルーシブ教育の基盤になるのであり、そのために「特別支援教育の視点を取り入れること」が1つのアプローチになると書いたのです。そして、その際に、個と集団へのアプローチバランスが問われることを指摘しました。
それを読んでくれた若い教員と話す機会がありました。話す中で、
個と集団へのアプローチバランスの大切さ、その通りだと思ったんです。でも、自分は経験が不足しているから、バランスの取り方がすごく難しいです。いろいろな事例を通してバランスについて勉強したいです。
という気持ちが語られました。
そこで今回は、個と集団へのアプローチバランスについてさらに考えてみようと思います。
個別へのアプローチ
以前、出会った子どものことが思い出されました。
平仮名を読むのが難しい、文字を写すことはできるが、形を写している感じで、写した文を読んで理解することにはつながっていないようでした。生活上の様々な事柄について、パッと見て瞬時に判断し「無理! できない!」と取り組まなかったり自信がなくなったりしている様子でした。
恐らく、あちこちの教室に、同じように困っている子どもたちがいるのではないでしょうか。そのような思いになる子どもでした。
当時のケース会議の中で、どのような支援ができるのかについて、関係の方々で「対話」が行われました。いろいろなアイデアが提案されましたが、その「対話」の中で、とあることに気が付きました。「対話」に共通している気付きは「その子どもが一人で取り組めること」を求めているということでした。
子どもが一人でできることを目指すのは、教育の目標としてあり得ることです。
でも、現状を考えてみると、一人でできることだけを要求するだけではなく、「誰かと一緒にできること」に価値を置くことも重要だと思えたのです。
・一人でできなくても大丈夫。
・先生と一緒にしたらよいので大丈夫。
・段々できていけばよいので大丈夫。 等々

個別のアプローチについて、「できる」にバリエーションがあること、そして「誰かと一緒にできること」には価値があることを子どもと一緒に大切にする。そして、このような「対話」を緩やかに行いました。その中で、個別のアプローチが、子どもにとって安心できるためのものへと拡がっていきました。

