心のふれあいをめざして! 小学校での保護者会の工夫アイディア

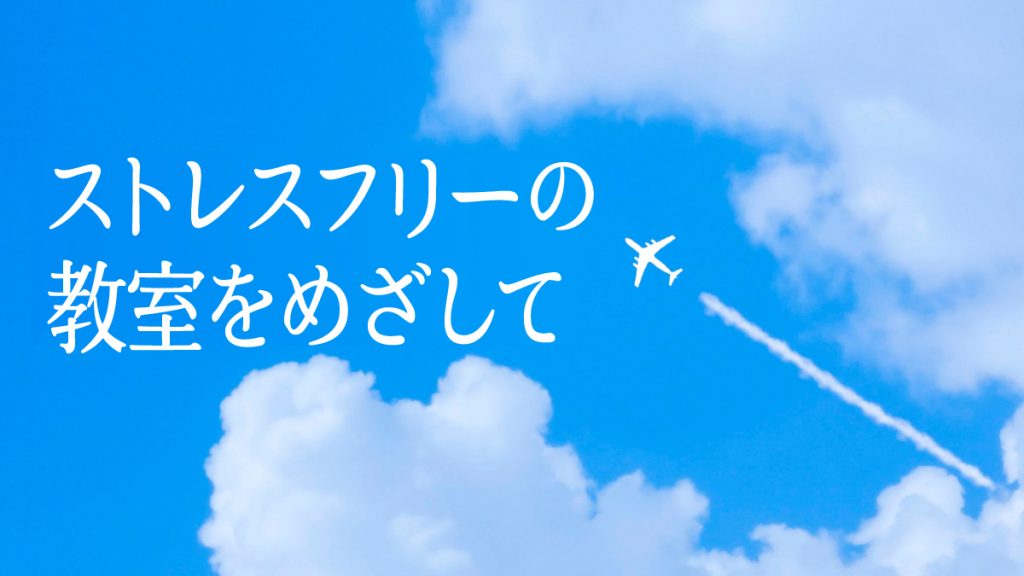
あなたは、保護者会についてどう思いますか? 苦手な意識を持っていたりしませんか? 今回は、先生であれば避けられない「保護者会」についてのトピックを選びました。保護者に関わる対応やストレスは、先生の悩みの多くを占めているのが今日の教育現場です。しかし、先生も保護者も「子どもによりよく育ってほしい」という願いは共通しています。先生と保護者が二人三脚で、ストレスフリーの学級経営を行うためのアイディアをまとめました。
【連載】ストレスフリーの教室をめざして #07
執筆/埼玉県公立小学校教諭・春日智稀
1 得意・不得意がはっきり?
筆者は、先生によって保護者会に対して「得意」「不得意」が大きく分かれるのではないかと考えています。得意な先生は気にならないですが、不得意な先生は「いやだなあ。不安だなあ」というイメージが先行してしまい、心理的負担が大きいのではないでしょうか。もしかすると、過去の保護者会に苦い思い出がある先生もいるかもしれません。
筆者は、こうした得意・不得意に左右されない保護者会を行うためには、会の中にアクティビティを取り入れることを提案しています。
2 なぜアクティビティが必要?
気難しいと思っていたベテランの先生にはいつも緊張してうまく話せなかったが、懇親会をきっかけに打ち解けたことによってユニークに一面を知り、楽に話ができるようになった、という経験は多くの先生にあるのではないでしょうか。これは、双方に「心のふれあい」が起こったからです。
先生も緊張する保護者会ですが、参加する保護者もまた同じ気持ちでしょう。「どんな先生かな」「どんな保護者がいるのかな」とドキドキしながら参加していることと思います。日本の心理学者である國分康孝(1982)は、「人と心のふれあいをもつためには自己を表現せねばならない。」と述べています。先生も緊張、保護者も緊張、では心のふれあいは生まれません。まずは縁あって時間と場所を共有することになった大人たちが自分を表現し、人と感情をわかちあう場面を意図的に創ることが大切なのです。
一色(2020)は、「保護者に対する心理的安全性を高く感じている教師ほど、創造的な教育実践を実施しやすい」と指摘しています。つまり、先生と保護者のよりよい関係づくりに注力することは、結果的に子どもたちへ還元されていくのです。

