インタビュー/木村泰子さん|「働き方改革」の本来の目的を問い直し、職員室の改革から始めよう【今こそ問い直す!先生を幸せにする「働き方改革」とは①】

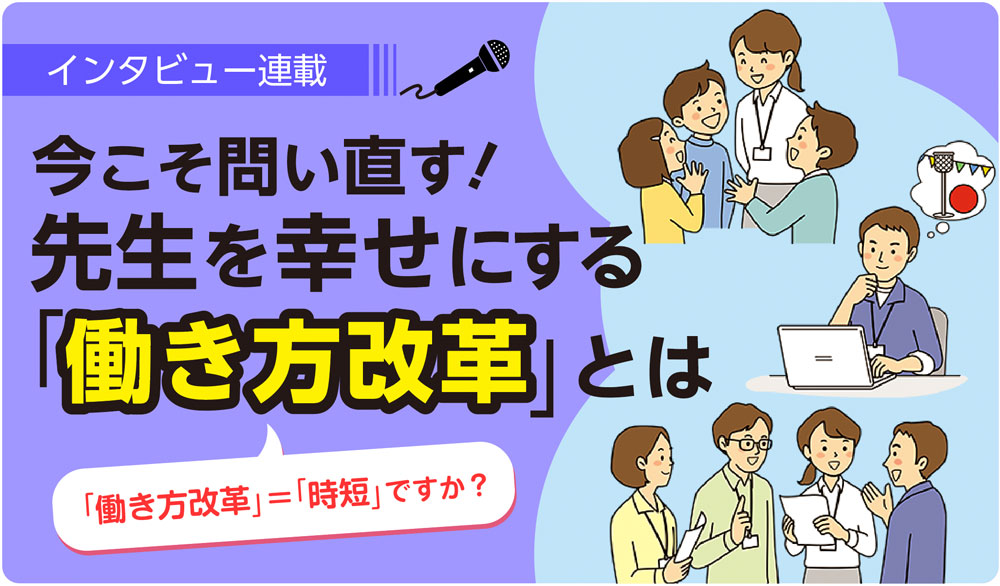
全国の学校で、今進められている「働き方改革」。ともすると時短ばかりが強調されがちですが、本当の意味で教師の仕事にやりがいや楽しさを感じられる改革になっているのでしょうか。学校教育のオピニオンリーダーの方々に改めて「働き方改革」の本質を語っていただきながら、子供も先生も皆が幸せになる「これからの教師の働き方」について考えていきます。連載第1回は、大阪市立大空小学校初代校長の木村泰子先生にお話を伺いました。
〈プロフィール〉
木村泰子(きむら・やすこ)
大阪市立大空小学校初代校長。大阪府生まれ。「すべての子供の学習権を保障する」学校づくりに情熱を注ぎ、支援を要すると言われる子供たちも同じ場でともに学び、育ち合う教育を具現化した。45年間の教職生活を経て2015年に退職。現在は全国各地で講演活動を行う。「『みんなの学校』が教えてくれたこと」(小学館)など著書多数。

目次
「働き方改革」によって学校から奪われているもの
今、全国の学校では「働き方改革」という名のもとで、時短(勤務時間の短縮)が盛んに行われています。それにより、学校から大事なものが奪われている事実に気づく必要があります。
まず、子供の育ちです。コロナ禍の後、運動会を午前中で終わらせるなど、行事の時間を短縮したり、行事そのものを廃止したりする学校が増えました。「『働き方改革』だからこの行事はやめよう」「授業以外のことは先生が大変だからやめよう」となって、多くの教員は毎日淡々と授業だけをしてきました。
その結果、今の職員室には三つの悪があります。それは①ヒエラルキー、②前例踏襲、③同調圧力です。この三つはこれまで隠されていたのですが、「働き方改革」という言い訳ができたことによって姿を表したのです。これらの三つの空気を大人がつくりだすと、子供もその空気の中にはめ込まれます。そんな環境では子供は育ちません。
結果として、全国のどの地域でも、子供のいじめ、不登校、自殺の件数が過去最多です。調査をやればやるほど、毎年過去最多の記録が更新されています。学校は子供が「働き方改革」のあおりを食っていることに、気づかなければいけないと思います。
このままいくと10年後の日本社会がどうなるかを考えてみてほしいのです。今の学校現場で育った子供たちが大人になって、どんな社会をつくると思いますか。きっと面倒なことは何もしない、可もなく不可もない、そんな社会ができあがるでしょう。
さらに、時短は教員たちの活力を奪っています。例えば、子供に寄り添っている若い教員が、運動会は1年に1回しかないから、地域の人と一緒に貴重な学びの場をつくりたい、と提案したとします。そうすると「『働き方改革』だからやめましょう。面倒だから何もしなくていい。何もしなければ保護者は文句を言ってこないから」という声が管理職やベテランから上がります。そうなったら、若い教員は何も言えないし、何もできなくなります。そうやって「働き方改革」は職員室の教員同士を分断しているのです。
ここ数年で、教員の仕事に魅力を感じなくなり、学校を辞めて自分でフリースクールをつくった人が全国に何人も出てきています。私のセミナーに来て、「学校はあきらめて、自分でフリースクールを立ち上げました」と話していくのです。その人たちは子供にとっては「いてほしい先生」なのですが、「早く帰れ」と言われ、やりたいことができない学校にはいてもしょうがないと思ってしまうのでしょう。
このように、今、多くの学校で行われている「働き方改革」のせいで、いじめ、不登校、自殺の件数は増え続け、若い教員はやる気をなくし、学校は貴重な人材を失っています。だからこそ、「働き方改革」をいったん止めなければいけないと思います。
「働き方改革」の目的は「教員が楽になること」ではない
そのうえで、教員の「働き方改革」について改めて考えてみる必要があります。その際に絶対に外してはいけないのは、その目的です。「働き方改革」はあくまでも手段であって目的ではありません。しかし、目的になってしまっている学校が多いのではないでしょうか。
では、「働き方改革」の本来の目的は何だと思われますか。しかも、企業でも病院でもなく、未来の社会をつくる子供たちが学んでいる学校で、教員の「働き方改革」をする目的は何でしょう?
多くのメディア等では、その目的は「先生たちが楽になること」だと捉えていますが、それは違うと思います。「働き方改革」の目的は、教員が楽になることではなく、「誰も取り残さない、子供のための学校をつくること」です。つまり、いじめ0、不登校0、自殺0の、すべての子供が育つ学校をつくるために、教員の働き方を改革するのです。
学校が「働き方改革」を進める理由の一つとして、教員のなり手不足の解消があります。そのために中央教育審議会の特別部会が、教職調整額を現在の4%から10%以上にする案を了承し、文部科学省は2025年の通常国会で教職員給与特別措置法(給特法)の改正案を提出する方針だそうです。教職調整額を4%から10%以上にして待遇を改善するから、どんどん教員になってください、ということのようです。
これに関しては「先生の仕事をなめないでほしい」と言いたいです。教職調整額が少々上がったから、「じゃあ先生になります」と、学生たちは思うでしょうか。
大事なのは、教員が楽しく働けるか、ということです。教員が毎朝学校へ出勤し、 勤務を終えて家に帰る時間が少々遅くなろうと、働くことが楽しかったら、教員は毎日生き生きと働きます。もちろん給料は、下がるより上がった方がいいに決まっていますが、給料が多少上がったら、それで教員の仕事が楽しくなりますか? ならないと思います。
では、どうしたら教員は楽しく働けるのかというと、「すべての子供が育っている事実があれば、先生は楽しい」のです。
例えば、子供たちがみんな学校に来て、ありのままの自分を出しながら過ごし、毎日トラブルが起きても、それによって子供同士がつながり、みんなが納得して「じゃあ明日」と言って家に帰っていきます。納得して家に帰れば、子供は学校でのストレスで保護者に当たり散らすことはないので、放課後、保護者から電話がかかってくることはありません。そして、次の日、子供がみんな元気に「おはよう」と言って学校にやってくる、そんな学校現場に変えることが「働き方改革」の目的です。

