子供たちが本を読みたくなる工夫とは?「教師という仕事が10倍楽しくなるヒント」きっとおもしろい発見がある! #15

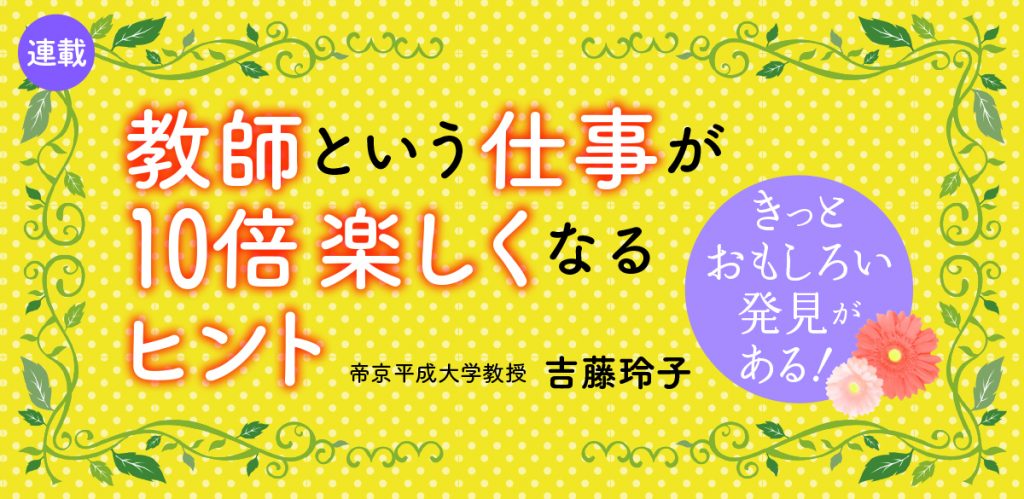
教師という仕事が10倍楽しくなるヒントの15回目のテーマは、「子供たちが本を読みたくなる工夫とは?」です。教師や保護者は子供たちに本を読んでほしいと思っています。しかし、読書のおもしろさを子供たちに伝えることは難しいものです。どのような方法で本のおもしろさを伝えるか、いろいろな工夫についてお届けします。子供たちを本好きにするヒントにしてください。

執筆/吉藤玲子(よしふじれいこ)
帝京平成大学教授。1961年、東京都生まれ。日本女子大学卒業後、小学校教員・校長としての経歴を含め、38年間、東京都の教育活動に携わる。専門は社会科教育。学級経営の傍ら、文部科学省「中央教育審議会教育課程部社会科」審議員等、様々な委員を兼務。校長になってからは、女性初の全国小学校社会科研究協議会会長、東京都小学校社会科研究会会長職を担う。2022年から現職。現在、小学校の教員を目指す学生を教えている。学校経営、社会科に関わる文献等著書多数。
目次
読書のすすめ
「本を読みましょう!」と教員はよく子供たちに言います。保護者も「もっと本を読みなさい!」と子供たちに言うことがあります。読書をすると何がよいのでしょうか? 学校には、必ず学校図書館(図書室)があり、毎日常住ではないかもしれませんが、司書がいます。また、司書教諭が年間の読書指導に関わり、図書委員会などの運営や読書週間の設置などの計画に当たります。
夏休みになると、「また読書感想文が宿題に出た。大変だなぁ」と思う子供も多いでしょう。課題図書などは子供の発達段階に合わせて紹介されるものの、どの本を読んだらよいか分からないという子供もたくさんいます。無理やりの読書の押し付けはかえって本嫌いを増やしてしまいます。読書のおもしろさは、自分の知識が増えること、体験できないようなことを知ることができ、自分の世界が広がることです。ファンタジーや物語文を読めばその世界の登場人物に学ぶことができます。そうはいっても読書のおもしろさを子供たちに伝えることは難しいことです。
私は、司書教諭の資格もあり、また勤務した学校で学校図書館を利用することが多かったので、司書の方とも話をし、いろいろ学ぶことがありました。現在も大学で司書に関わる講座を受け持っています。今回は、読書のおもしろさをどのように子供たちに教えたらよいか、教員も読書を楽しもうということを伝えたいと思います。
絵本のおもしろさ
本を読むときに文字数が多いと「もう嫌だ」という子供がいます。無理して分厚い、文字量の多い本を読ませる必要はないでしょう。絵本から学ぶこともたくさんあります。子供たちが大好きな『はらぺこあおむし』(エリック・カール 偕成社)という絵本は、世界で70以上の言語に翻訳されているそうです。ページの中の絵に穴が空いているなど、楽しい仕掛け本です。このような仕掛け本の絵本はいろいろあります。もし、文字が苦手という子供がいたら、絵本から読書に入ることをすすめます。
絵本にもフィクションとノンフィクションがあります。絵本は、フィクションが多くを占めますが、ノンフィクションの絵本は子供も教師も学ぶことがたくさんあります。『羽田九月二十一日』(野村昇司・作/阿部公洋・絵 ぬぷん児童図書出版)という羽田地区の歴史を書いた絵本があります。あまり知られていない話ですが、戦後、GHQにより強制退去させられた羽田の鈴木新田村の話です。最近できた羽田のイノベーションシティにその史実が詳しく書かれた碑があります。ようやく戦争が終わって、かろうじて生き延びた人々が、何の連絡もなく突然羽田空港拡張のために退去を命ぜられるのです。絵と文で考えさせられ切なくなる絵本です。
絵本は子供のための楽しい読み物というイメージがありますが、奥深いノンフィクションの絵本も数多くあります。ぜひ、ノンフィクションの絵本も学校現場で読書の時間に取り入れてみてください。

