子どもの事実から「校長観」の転換を 【木村泰子「校長の責任はたったひとつ」 #12】

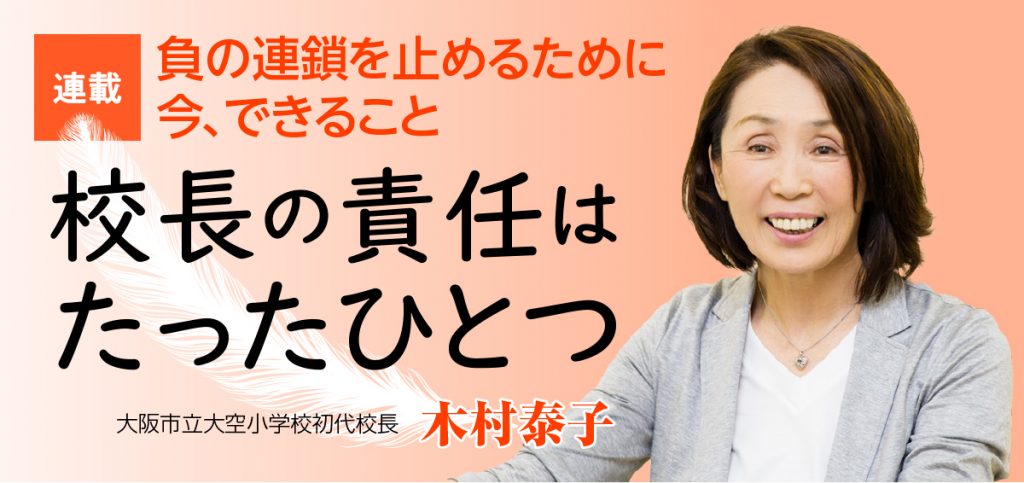
不登校やいじめなどが増え続ける今の学校を、変えることができるのは校長先生です。校長の「たったひとつの責任」とは何かを、大阪市立大空小学校で初代校長を務めた木村泰子先生が問いかけます。
第12回は、<子どもの事実から「校長観」の転換を>です。
校長は動かないほうがいい⁉
校長室でマネジメントに集中していて、「すべての子どもの学習権を保障する学校」をつくることはできません。
最近、全国の校長先生方と学ばせていただく中で、次のような質問を受けることが多くあります。特に、「みんなの学校」の映画を観られた校長先生方からは「校長がこれだけ動いて、先生方がやりにくくないですか?」と聞かれます。
新任の校長先生方は、教頭時代は常に自分から動き回っていたが、校長になるとそうはいかなくて、歯がゆい思いをしていると言われるのですが、どうしてなのでしょうか。
読者のみなさんはどう思われますか?
校長試験の論文で、校長とはこうあるべき、といったこれまでの「校長観」を正解として書いてこられたこともあるでしょう。校長が動くと後がない。校長の後を誰がフォローするのだ。だから、校長は最後に動かないと学校を守れないなどと、私自身も校長になる前はそのように指導されてきたことを思い出します。
また、教頭時代に校長に仕えることで疲弊した結果、校長になったら今度は自分の体験と同様に教頭を支配したくなる。話は飛びますが、姑に仕えた嫁が姑になって嫁いびりをするなどという残念な社会の構図のようだと感じてしまいます。子どもには、自分がされて嫌なことはしないようにと指導しながら、行動が伴わない大人の典型です。
従前の「校長観」は、たまに教室を回るが、それ以外は校長室でほとんど仕事をし、教頭からの報告を受ける、といったものではなかったでしょうか。中には、あまり頻繁に教室を回ると、先生方に気を遣わせるから校長室を出ないとも言われている方もいました。これらの「校長観」の主語は教職員で、校長は教職員を管理監督するのが職務で、教職員の意識を変え、指導力を向上させるのが校長の使命であると、とらえられてきました。
子どもの事実から「校長観」を問い直す
時代は激変しています。現在は、1年間に500人を超える子どもが「自死」し、30万人の小中学生が「不登校」になっている、という子どもの事実を突きつけられている学校現場です。これまでと同様の「校長観」を持って仕事をしていては事態が良くなるわけがありません。
「校長観」を転換するときです。校長ができることは想像以上に多くて、校長にしかできないことがあります。
例えば、自校の教育課程について決める権利はすべて校長にあります。今の制度の中でも校長が教育課程を決めることができるのです。校長の「力」は大きい。だからこそ、その力を存分に発揮して、「すべての子どもの学習権を保障する学校」をつくるための、より良い学校環境をつくっていくことが、今の学校現場のリーダーである校長に求められている重要な課題なのです。

