生成AIは教師自身の意思決定のための壁打ちに使える【実践のポイントを分かりやすく解説! 生成AI活用の授業づくり「まずはココから」#01】
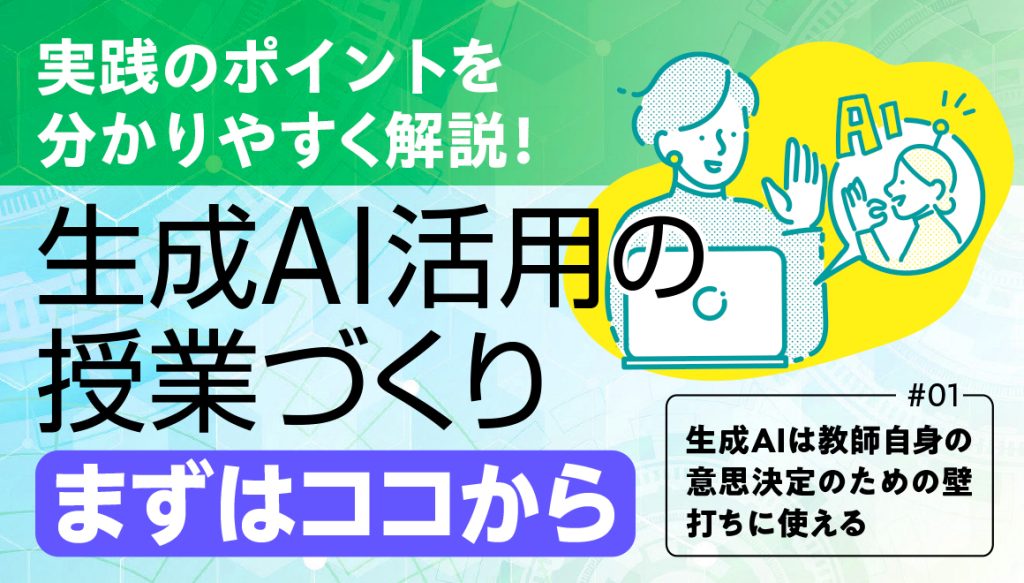
2023年7月4日に文部科学省から「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン」が示され、今年度は全国60校(小・中・高等学校)のリーディングDXスクール生成AIパイロット校で実践研究が進められています。そんな中、すでにアンテナの高い先生方の間からは授業に活用した事例なども聞かれますが、実際のところ学校の先生は生成AIをどのように捉え、どのように活用していけばよいのでしょうか。
この連載では、中央教育審議会初等中等教育分科会のデジタル学習基盤特別委員会の委員長としてガイドラインの策定にも携わった、東京学芸大学教職大学院の堀田龍也教授にお話を聞くとともに、生成AIパイロット校の実践事例を紹介しつつ、そのシステムづくり、授業づくりについて考えていきます。初回となる今回は、まず堀田教授のインタビューを紹介していくことにしましょう。

堀田龍也(ほりた・たつや)
博士(工学)(東京工業大学)。東京学芸大学教職大学院・教授、学長特別補佐。2024年3月まで東北大学大学院情報科学研究科・教授(人間社会情報科学専攻メディア情報学講座情報リテラシー論分野)。文部科学省初等中等教育局・視学委員。国立教育政策研究所・上席フェロー。信州大学・特任教授。
目次
社会インフラとしてのAI活用が当たり前になってくる
生成AIを学習に活用するという話は新しいものですから、学校の先生も「どうしたらよいだろうか?」「使っても大丈夫だろうか?」と過剰に考えているのではないでしょうか。しかし、この状況と同じことは、検索エンジンが生み出され、「Googleで何でも検索できる」という状況になったときにもありました。「こんなものを使ったら、すぐに答えが見付かるじゃないか」「これを使っていたら頭が悪くなる」とまで言っていた人もいました。しかし、そう言っていた人自身も今、間違いなく検索エンジンを使っているはずです。
例えば電車に乗るときに、Suica(のような交通系ICカード)を使うとか、掃除をするときにルンバ(のようなロボット掃除機)を使うといったことも同様で、出た当初は違和感があったかもしれませんが、必要に応じて使うことがごく普通になってきました。それと並行して精度が上がってきたわけです。検索エンジンにしても、出た当初には的外れな検索結果が出てくることもあったでしょう。あるいはロボット掃除機だって出た当初にはうまく機能してくれないところもあったでしょう。交通系ICカードだって、使える範囲は限られていたでしょう。しかし多くの人が使ううちに、どんどん精度も汎用性も上がってきたわけです。
生成AIもまだ誕生して間もないために、今は使うことに対して警戒をしている人がいるかもしれませんが、多くの人が使ううちにごく普通に活用されるものになっていくでしょう。Chat GPT4も話題が出てから1年少々になりますが、年単位ではなく、1か月、2か月という単位でどんどん精度が上がってきています。他の生成AIも新しいものが出され、しのぎを削り合っていくうちに精度が上がってきており、社会インフラになってきています。
そうなると、私たちは直接、生成AIを使うだけではなく、知らないうちに生成AIを活用しているということも起こるでしょう。例えば、「Googleの裏側で、生成AIが働いて検索している」という状況も起こるわけです。裏側に潜って働くような形ですね。そうなると、活用するとかしないとか言っていられない状況になってきます。例えば自動車に乗っていて渋滞が生じたら、AIが信号制御をするなどの実用化が始まっているわけです。そのように、バックグラウンドで動くAIがどんどん出てくることになります。
現時点ではまだ精度が今一つであるため、十分な機能を発揮してはいませんが、今後、精度が上がってくるにつれて、社会インフラとしてのAI活用が当たり前になってくるのです。
生成AIは我々が「お~!」と思うようなこともときどきやる
そのような現状がある中で学校教育に目を向けると、先生は非常に多忙で、どの現場も人手不足です。しかし、そもそも労働人口が減少し、税収が減る中で、公務員である先生を増やすことは簡単にはできません。そう考えると、先生の仕事を手伝ってくれるようなテクノロジーは必要です。掃除を手伝ってくれるロボット掃除機と同様に、書類の作成を手伝ってくれるような生成AIも必要だろうと思います。細かいチェックは人間が行い、最後の判断は人間がするにしても、ざっくりした文章の作成をやってくれるようなことを、助手の代わりに生成AIがやってくれると非常に便利なわけです。
現時点で子供に生成AIを使わせるには課題がありますが(それについては後述)、先生は大人ですから、もっともっと使っていくべきだと思います。使っていけば、「ああ、まだこれくらいのことしかできないのか」ということが分かるし、「これくらいのことなら、こう使えそうだ」ということも判断できるようになります。毎日使っていれば、半年も経つとずいぶん精度が上がってくることが体感できるはずです。
社会全体を見渡すと、今や知的業務をしている人が生成AIを使わないということはないでしょう。かく言う私自身も、生成AIを使わない日はありません。もちろん100%の答えは出してくれないけれども、7、8割方こうではないかと言えるような答えは出してきます。あるいは、たまに間違ってはいることもありますが、自分が考えていることとは異なることを示してくることもあるので、「なるほど、そういう見方もあるな」と考えるためのヒントになる場合もあります。そのため、自分が意思決定するための壁打ち(ビジネス用語で、自分の考えや悩みなどに対するフィードバックをもらうこと)に使うことができるわけです。
ですから、私は講演などでも先生の活用の仕方についてお話をしています。例えば、「小学校1年生の落ち着きのない子の通知表の所見を書いてください」と問いを投げると、結構ちゃんとした所見の文章を書いてくれるのです。申しわけありませんが、初任者の先生よりも良い文章を書くことができると思います。ただし、その文章はあくまで一般論であり、先生の目の前にいる気になる「その子」のことではありませんから、「その子」と「その子の保護者」に伝えるための所見はもちろん担任の先生が書かなければなりませんが、参考になる言い回しや文例は生成AIが書いてくれるのです。
例えば、所見で落ち着きのない子供のことを、「落ち着きがありません」と表現する先生はいないでしょう。「とても活動的で~」とか、「常にいろいろなことに興味をもって~」というように表現するはずです。それくらいのことを生成AIは十分やってきます。それこそ「教育技術」にあるような教育記事も、ネット上にあるものであれば、次々に学習していくわけです。ですから今後は「教育技術」も、生成AIを上手に活用しながら次々に情報提供していかないといけない時代になるのではないかと思います(笑)。
それくらい、社会インフラとしてすごいスピードで普及していきますから、先生も社会から遅れないためにも、自分の仕事に活用すべきだと思います。もちろん最終判断は先生自身が行うことが大前提ですが、そこそこの仕事を手伝わせることはやってみるとよいでしょう。教師という仕事は専門職ですから、そんな専門職のやることを生成AIが簡単にやれるわけはないのです。ですから生成AIに仕事を取られるなどと心配する必要はないのですが、その専門職の我々が「お~!」と思うようなこともときどきやります。そのように頼れるところもあるのです。
先日、女性校長会で講演をしたときに、そんな生成AIをたとえて「ちょいちょい間違うけれども、人のよい教頭先生だと思ってください」とお話ししたら、大笑いしていただけました。ちょいちょい間違うこともあるからチェックはしなければいけないし、最終判断はあくまで校長の仕事なわけですが、いてもらったほうが助かるし、たまには自分と異なる意見も出してくれて役立つ存在だということです。そのように考えて、大人である先生は使っていくべきだと思います。

